「今日はどうしても勉強が頭に入らない」そんな頭が回らない状況に覚えのある受験生も多いでしょう。
思考力が鈍った状態を放置すると、成績低下ばかりか焦りと不安が重なり、さらに集中できない悪循環に陥ってしまう場合もあります。
そこでこの記事では、脳の働きを妨げる原因を整理し、今日から実践できる改善策を解説します。
原因を見極め、効率的に学習を進める準備をしましょう。
受験勉強中に頭が回らないと感じるのはなぜ?考えられる原因
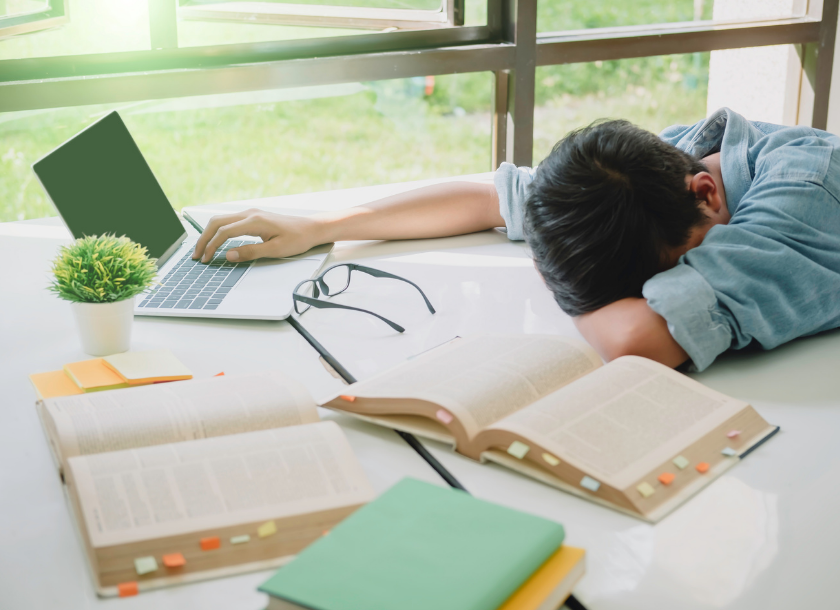
まずは、受験勉強中に頭が回らないと感じる主な原因について解説します。
自分に思い当たることがないか客観的に振り返ってみましょう。
睡眠不足・疲労による脳の働き低下
夜更かしや慢性的な睡眠不足で脳に十分な休息が取れないと、日中の思考力・集中力は著しく低下します。
必要な睡眠時間には個人差がありますが、一般的に毎日6~8時間ほどの睡眠が望ましいとされます。
勉強中にぼーっとしたり頭が全然冴えないと感じる場合、まず睡眠不足や体の疲労が原因ではないか疑ってみましょう。
睡眠不足が続くと脳の記憶力や判断力まで正常に働かなくなりやすく、「考えているつもりでも頭に入ってこない」という状態に陥りがちです。
前日の夜にしっかり眠れていない、日々の疲れが蓄積しているといった場合は、まず休息を優先することが大切です。
栄養不足・体調不良が原因の場合
人間の脳の主なエネルギー源はブドウ糖(糖分)です。
朝食を抜いたり食事内容が偏って血糖が不足すると、脳に十分なエネルギーが行き渡らず思考が鈍くなってしまう場合があります。
また、鉄分不足による貧血など体調不良があるときも、頭に十分な酸素が届かずにぼんやりしがちです。
栄養バランスの取れた食事を摂れているか、朝ごはんを抜いていないか、最近体調不良はないかなども原因として確認しましょう。
勉強環境や生活習慣の乱れ
勉強する環境が整っていないことも、頭が回らなくなる一因です。
例えばスマホの通知音が頻繁に鳴ったり、机の上が散らかっていたりすると、その都度注意力がそがれて集中が途切れてしまいます。
また生活リズムの乱れも見逃せません。
夜型の生活や不規則な勉強時間は、体内時計を狂わせ脳のパフォーマンス低下に直結します。
自宅の勉強スペースの状態や、自分の生活習慣も一度見直してみましょう。
ストレス・不安などメンタル面の影響
受験へのプレッシャーや将来への不安といった心理的ストレスも、「頭が回らない」大きな要因です。
強いストレス状態では脳の認知機能が低下し、集中しようとしても頭に入ってこなくなります。
例えば「落ちたらどうしよう」「間に合わないかも」といった不安が常につきまとっていると、勉強に向かっても上の空になりがちです。
また、まじめな受験生ほど「休んではいけない」と自分を追い詰めすぎて心が疲れてしまうケースもあります。
メンタル面の不調がないか、自分の心の状態にも目を向けてみましょう。
必要以上に自分にプレッシャーをかけすぎていれば一度息抜きする勇気も大切です。
なお、集中力低下や気力の落ち込みが2週間以上続くような場合は、うつ症状などの可能性もありますので早めに専門医に相談することも検討してください。
頭が回らないときの改善策・対処法

原因に心当たりがあれば、まずは脳をしっかり休ませることを最優先しましょう。
その上で、必要な栄養補給や軽い運動によって脳の働きを高め、短い休憩や環境調整で集中しやすい状況を作ります。
また勉強方法を工夫して科目や作業内容を切り替えることで脳をリフレッシュさせ、ストレス発散やリラックスも取り入れてメンタルケアを行いましょう。
以下に具体的な改善策を順に紹介します。
十分な睡眠と短い仮眠を取る
勉強の効率を取り戻すには、何より十分な睡眠が必要です。
毎日できるだけ6~8時間程度の睡眠時間を確保し、試験前でも極力夜更かしは避けましょう。
「睡眠不足が続いている」という自覚があるなら、それが頭が働かない主因です。
まずは思い切って寝る時間を増やし、脳の疲労を回復させてください。
どうしても忙しくて睡眠時間が足りない日が続く場合や、勉強中にどうにも頭がボーッとして冴えないときは、途中で15~20分ほどの短い仮眠(パワーナップ)を取るのも有効です。
勉強に区切りをつけて一旦目をつむれば、起きた後に頭がスッキリしているのを実感できるでしょう。
栄養補給と水分補給・適度な運動
脳がしっかり働くための土台として、栄養と水分を欠かさないようにしましょう。
勉強前や休憩中に意識的にブドウ糖を補給すると脳のエネルギー切れを防ぐことができます。
たとえばチョコレートや果物など手軽に糖分が摂れるものを少量食べるとよいでしょう。
糖分を補給することで眠気を和らげ集中力を維持できます。
ただし摂りすぎは血糖値の急上昇で眠気につながるため、あくまで少量にしましょう。
さらに、休憩時間には適度な運動も効果的です。
長時間座りっぱなしで勉強していると血流が悪くなり脳にも酸素が届きにくくなります。
休憩のたびに軽くストレッチをしたり、外に出て数分散歩したり、その場で体をほぐす体操や深呼吸をしてみましょう。
体を動かすことで滞った血行が促進され、脳に酸素と栄養が行き渡って頭の働きがクリアになります。
勉強前に5分ほどストレッチや軽い筋トレをする習慣をつけると、その後の勉強に集中しやすくなるでしょう。
勉強環境を整え、メリハリのある学習をする
頭の切り替えがうまくいかないと感じるときは、勉強する環境そのものを見直すことで集中しやすくなる場合があります。
まず、周囲の環境から余計な刺激を減らしましょう。
勉強中はスマホの電源を切るか別の部屋に置いて通知が目に入らないようにします。
どうしても気になってしまう人は、家族にスマホを預けるのも一つの方法です。
また、机の上は今取り組んでいる科目に関係ない本や雑貨類は片付けて、必要最低限のものだけに整理整頓してください。
視界に入るものが多いと脳が無意識に情報を処理しようとして疲れてしまうため、物理的に散らかっていない状態を作るだけでも集中力は高まりやすくなります。
次に、勉強時間の区切り方を工夫して脳にメリハリをつけることも大切です。
人間の集中力には限界があり、どんなに集中力が高い人でも長時間持続させるのは難しいものです。
したがって、一定時間ごとに短い休憩を入れてリセットする方が結果的に効率よく勉強できます。
おすすめは、50~60分勉強したら5~10分休憩するといったサイクルを作る方法です。
5分程度でも席を離れて目と脳を休ませれば、次の勉強にまた集中しやすくなります。
逆に休憩なしで何時間も続けていると脳が疲れ切って「机に向かっているだけ」で頭に入らない状態になりかねません。
短い休憩を挟むことで集中力をリセットし、長い目で見て勉強効率を維持しましょう。
勉強法を工夫し、頭の切り替えを図る
「どうしても今日は頭が回らない」というときは、勉強内容そのものを工夫して脳をウォーミングアップしましょう。
難しい問題に何十分も行き詰まってしまうと、余計に焦って悪循環に陥ります。
そういう時こそ難問に固執せず、今の自分の集中度でも取り組める作業に切り替えることがポイントです。
たとえば、暗記事項をまとめた単語カードの整理や、教科書の音読、ノートの清書・要点整理など、頭をあまり使わなくてもできる作業から始めてみます。
英語の長文が頭に入らないなら、まず単語の意味調べだけでも進めてみるといった形です。
こうした単純作業をこなしているうちに脳のエンジンが温まってきて、「もう少し勉強できるかも」と感じる瞬間が出てきます。
そのタイミングを逃さず、徐々に本格的な勉強モードに移行していきましょう。
簡単な問題を解いているうちにスイッチが入り、気づけば難しい問題にも取り組めていたということもあります。
ストレスを解消しメンタルケアも忘れずに
勉強に追われて心身が緊張しっぱなしでは、頭の働きも鈍ってしまいます。
意識的にリラックスする時間を作ることも、結果的に勉強効率を上げる重要な対処法です。
勉強の合間にミニリフレッシュを取り入れましょう。
例えば休憩のたびに肩や首をゆっくり回して全身を伸ばすストレッチをする、窓を開けて深呼吸を数回繰り返すだけでも効果があります。
呼吸が浅くなっていると脳に十分な酸素が行かずぼんやりしてしまうため、意識してゆっくり鼻から息を吸って吐く深呼吸をすると頭がスッキリします。
また、好きな音楽を1曲だけ聴いてみたり、その場で軽く体を動かしたりするのも緊張を和らげるのに役立ちます。
要は張り詰めた脳と心に少しゆとりを与えることがポイントです。
加えて、あまりにストレスが溜まっていると感じるときには思い切って勉強から離れてしっかり休養を取ることも必要です。
ストレス発散法は人それぞれですが、軽い運動や入浴、好きな本を読む、友人や家族と少し会話するなど、心がリラックスできる時間を持ちましょう。
心に余裕が戻れば不思議と頭の回転も良くなり、集中力もアップします。
メンタルケアは怠らず、心の健康も合格への大事な要素だと考えてください。
本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾
生活リズムや学習環境を自宅で整えるのは簡単ではありません。
医学部専門予備校 京都医塾なら、あなたの学習と日常をサポートし、合格への最短ルートを提示します。
頭が回らない原因を根本から断ち切り、安定した学習リズムを習慣化できます。
学寮×生活管理で勉強のリズムを整える
医学部専門予備校 京都医塾の学寮は、起床から就寝まで医学部受験生の一日の行動を学習に最適化するよう設計されています。
朝はスタッフが起床をサポートし、夜は十分な睡眠時間を確保します。
自宅では難しい規則正しいリズムを寮生活で自然に身につけ、脳がフル回転する朝型習慣を確立します。
これにより「夜更かしで翌日ぼんやり」という悪循環を断ち切れます。
完全個別カリキュラムで苦手分野を克服
医学部専門予備校 京都医塾では、到達度テストや面談で一人ひとりの学力と生活状況を分析し、13名体制の専属チームが「完全個別カリキュラム」を作成します。
苦手単元はマンツーマン指導で徹底克服、得意科目は演習量を増やして伸ばすなど、日々の時間割まで調整して効率を求められることが特徴です。
寄り添いサポートで学習のメンタルも安定
長期戦となる医学部受験ではメンタル管理が合否を分けます。
医学部専門予備校 京都医塾では、担当2名(担任・副担任)と教務スタッフ1名が、学習計画だけでなく生活・進路の悩みまでサポートします。
週次カウンセリングでストレス度合いをチェックし、必要に応じて学習ペースを微調整することも特徴です。
模試結果が振るわない時も原因分析と対策案を提示するため、一時的なスランプに左右されません。
まとめ
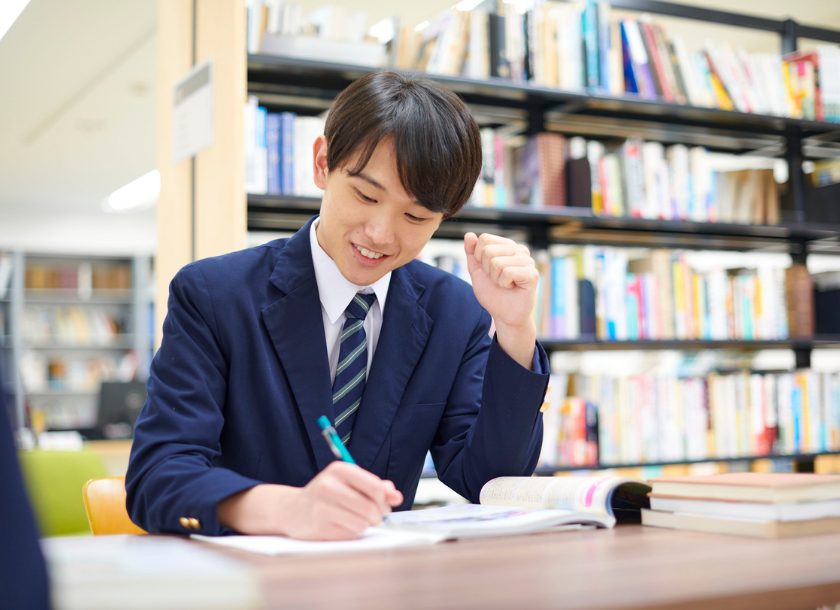
今回の記事では、勉強中に頭が回らなくなる主な要因と、それぞれの具体的な改善策を解説しました。
生活リズムを整え、集中を妨げる原因を取り除いていけば思考力は着実に回復し、学習効率も高まります。
しかし、生活と学習を一人で管理するのは簡単ではありません。
医学部専門予備校 京都医塾なら、学寮での朝型リズム作りから個別カリキュラムまで提供し、医学部受験生が勉強だけに集中できる環境を整えています。
それを実際に体験できるのが、「1泊2日医学部合格診断ツアー」です。
実際の授業などを体験し、あなた専用の学習プランと合格までのロードマップを無料でご提案します。
交通費・宿泊費も無料なので、迷った今こそお申し込みください。


