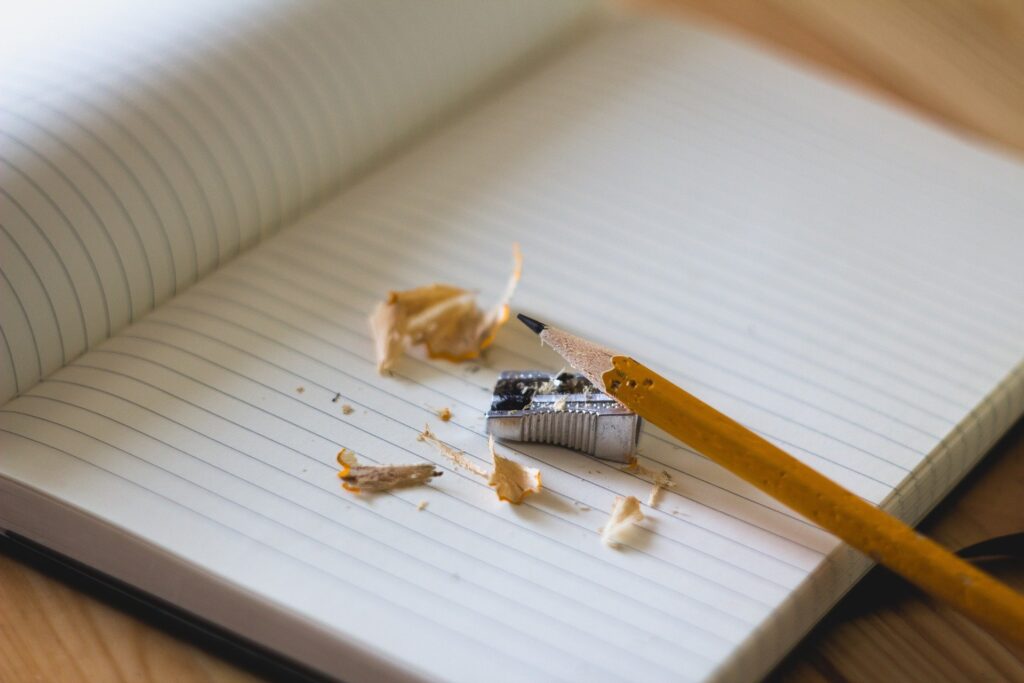医学部の受験にあたって一筋縄では行かないのが、小論文の試験です。
文章を書くのが得意な人にとっては得点源となりますが、そうでない人にとっては苦手な分野になってしまう場合もあるでしょう。
そこで今回は、医学部入試における小論文試験のポイントなどを徹底的に解説していきます。
医学部入試の小論文とは
ここでは、医学部の小論文試験とは具体的にどのような試験なのかを医学部の小論文試験について詳しく見ていきましょう。
なぜ医学部入試では小論文が課されるのか?
大学入学共通テストや各私立大学医学部が行う一般入試が学力のみを受験生に問うのに対し、小論文試験は医学部における心構えや医師としての資質・適性を問うために実施されます。
例えば、医療ミスの増加や医療界の不祥事など、医療に携わる人間のコンプライアンスを受験生がどのように受け止めているのかを大学側が確かめるための設問が用意されます。
加えて、受験生が医師となるうえで患者と向き合える責任感や道徳観・倫理観をどの程度備えているかという点を試す目的もあります。
単純な一問一答形式の問題ではなく、「医療とは何か?」や「死生観について記せ」など抽象的なテーマについて、自分の立場と根拠を述べる出題がなされるのも小論文試験ならではの特徴です。
小論文の5つの出題パターン

医学部の小論文は、大きく分けて5つの出題パターンに分類できます。
ここでは、医学部入試における代表的な小論文の出題パターンについて解説していきましょう。
課題文読解型
こちらのパターンでは、出題された課題文の要約や文章に対する意見論述が課されます。
課題文の読解が前提となるため、課題文を正確に読み取れていなければ求められている答案を作成できません。
例えば、最先端医療に関する資料が示された後に今後の現場医療の展望を問われたり、高齢化社会における医療問題や介護問題を論述する設問が出題されます。
テーマ型
テーマ型の設問では、基本的に資料から何かを読み取るのではなく「○○について述べなさい」といったようにシンプルな問いについて自身の意見を論述していくのが特徴です。
この設問では単純な医療問題に関する問いのほか、自分の将来像や社会問題など様々な観点から論述を求められることがあります。
テーマ型の設問は問題がシンプルであるがゆえに難しく、該当するテーマの予備知識が無いと情報が少なすぎて論述の幅が限られてしまいます。
日常的に時事ネタの解説本に触れるとともに、医療系のニュースをチェックするなど広範囲にアンテナを広げておく必要があるでしょう。
現代文型
現代文型の小論文試験は、一部の大学のみで課されるパターンです。
こちらのパターンでは主題に関する複数の設問がなされ、それぞれに回答していく形式をとります。
小論文の試験というよりも、国語の現代文に近い形式なのが特徴です。
現代文型の小論文を課す大学を受験する際は、国語の学習とセットで小論文の対策を進めていくと一石二鳥となるでしょう。
英文型
英文型の小論文試験では、英文の課題文を読んだ上で自分の意見を論述する力が求められます。
英文読解力とともに英語で文章を作成する能力が必要なのが特徴ですが、一般の学部とは異なり医療・科学雑誌などで使われる専門単語が頻出するため、それらに不慣れだと読解が追いつきません。
そのため海外、とりわけ英語圏の医療系・自然科学系の情報に触れておくことが合否の分かれ目となります。
一見すると非常に難易度が高い出題パターンに思えますが、テーマを推測できればそれにともなって単語それぞれの意味も類推できます。
場数を踏んで解法に慣れておくとよいでしょう。
なお、こちらの出題パターンは群馬大学をはじめとする国公立大学の後期日程試験によく見られます。
図表分析型
図表分析型は、その名のとおり図や表からデータを読み取り分析する出題形式です。
こちらのパターンでは、将来的な人口動向や高齢化率、感染症による重症・死亡率など、様々なデータが提示された実例があります。
受験者は提示された図表の内容を正確に把握し、そこから読み取れる課題や傾向を論理的に考察していくことが求められます。
特徴的な小論文を出題する大学
医学部を受験する人の中には、併願受験で複数の医学部を受験する人も多く見られます。
併願受験を希望する場合、一度に複数大学の小論文対策をしなければならないため、それぞれの大学の出題傾向についても把握しておきたいところです。
そして、併願先の中に特徴的な小論文を課す大学があるなら、なおさら出題傾向について把握しておく必要があります。
ここでは、そのような独特な小論文を出題する大学として代表的な2校を紹介します。
順天堂大学
順天堂大学医学部では例年、写真や絵を見て、そこから自分が考えたことを記すというユニークな小論文問題が出題されます。
例えば、ロンドンの駅構内で階段を上る男性の写真を見せて「この人物の前にどんな世界が広がっているか」を800字で論じさせる問題が実際に出題されました。
(出典:東洋経済オンライン)
医学・医療に直接関係のない視覚資料がテーマになるため戸惑う受験生も多いですが、医師としての資質を問う試験の一環であることを踏まえて論じることが求められます。
愛知医科大学
愛知医科大学医学部の小論文試験のテーマは、毎年ユニークなことで有名です。
基本的には与えられた資料から情報を読み取り論述するパターンが多いですが、時には物語を創作したり川柳を解釈したり、イラストを見て考察させたりと多様な問題が出題されます。
実際に、「3年間交際し結婚を約束した恋人に別れの手紙を書け」といった創造力を試す問題が出題されたこともあります。
(出典:キャリコネニュース)
こうした傾向から、愛知医科大学を併願校とする場合は特に過去問演習で出題形式に慣れておくことが重要です。
医学部小論文対策の重要ポイント

小論文を書くうえで大事なポイントには、どのようなものがあるのでしょうか。
医学部の小論文対策は早めに着手するのが肝心です。
一般的には、高校3年生の夏頃から小論文対策を本格化させ、一次試験突破後に再度集中的な練習を行う受験生が多い傾向にあります。
以下では、小論文を書くうえで重要となるポイントを具体的に解説していきます。
日々の積み重ねが大切
最初に解説する小論文を書くうえで大事なポイントは、日々の積み重ねに関する事柄です。
ここでは2つの観点から説明しますので、参考にしてください。
普段から医療に関する情報を取り入れる
何かを論評し表現するためには、根源となる知識・情報が必要となります。
医学部の小論文でも同様で、普段から医療や社会に関する情報に触れていないと、いざ出題されたときに筆が止まってしまうでしょう。
そのため、日頃から医療・介護に関するニュースをチェックして知見を蓄えることが、試験を突破するための最良の習慣となります。
医療系・介護系のニュースの中でも特に大きな話題となった出来事は、医学部小論文で題材になりやすいので必ず押さえておきましょう。
適切な表現方法を身につける
適切な表現方法を身につけることも、小論文を書くうえで必要な要素です。
先ほど、小論文を書くためにはテーマに関する情報収集が重要だと説明しましたが、表現方法が稚拙だとその内容も相手に正しく伝わりません。
どんなに出題テーマを深く読み解き、豊富な知識や自分なりの見解を持っていても、それを論理的かつ明瞭に文章化する力が足りなければ高い評価にはつながりにくいです。
小論文の書き方を練習する際は、メディアから発せられるメッセージを読み解き論評する能力を磨くとともに、「どうすれば自分の考えが他者に伝わるか」を常に意識して何度も訓練しましょう。
志望校の過去問に目を通しておく
続いて小論文を書くうえで大事なポイントは、過去問に関する事柄です。
言うまでもありませんが、過去問は今後出題されうる問題の宝庫です。
過去問を研究することで志望校の出題傾向が把握できるとともに、難易度の感覚もおおよそ掴むことができるでしょう。
また、小論文試験を課している大学の場合、過去問に取り組んでおくことが早い対策となります。
実際に問題用紙に向かって答案を書いてみることで時間配分にも慣れ、本番でも落ち着いて取り組めるようになります。
添削してもらう
最後に小論文を書くうえで大事なポイントは、第三者に添削してもらうということです。
小論文はあくまで自身の視点で物事を論評しますが、それゆえに思わぬ欠点や主観的な偏りが生じてしまうことがあります。
ひどいときには、論文の前後で主張が矛盾してしまい、結局何が言いたいのか分からなくなってしまうこともあるでしょう。
そういったときに助けになってくれるのが、第三者の視点です。
自分の小論文について客観的な立場から添削してもらうことで論述の精度が上がり、論評のバリエーションも広がります。
文章のプロや指導者からフィードバックを受ければ、自分では気づけなかった改善点が明確になり、大きな実力向上が期待できます。
小論文の書き方講座を受講する
小論文の対策としては、独学だけでなく専門の「書き方講座」を受講することも効果的です。
プロの指導者による講座では、小論文の構成や論理展開の型、テーマの掘り下げ方などを体系的に学ぶことができます。
また、講座内で実際に小論文を書いて提出し、講師から添削・指導を受けることで、短期間でも飛躍的に表現力を高めることが可能です。
独学では気付きにくい癖や弱点も、第三者の視点で指摘してもらえるため、効率よく改善できます。
最近ではオンライン形式の講座も充実しており、自宅にいながら質の高い指導を受けられるので、必要に応じて活用を検討するとよいでしょう。
本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾
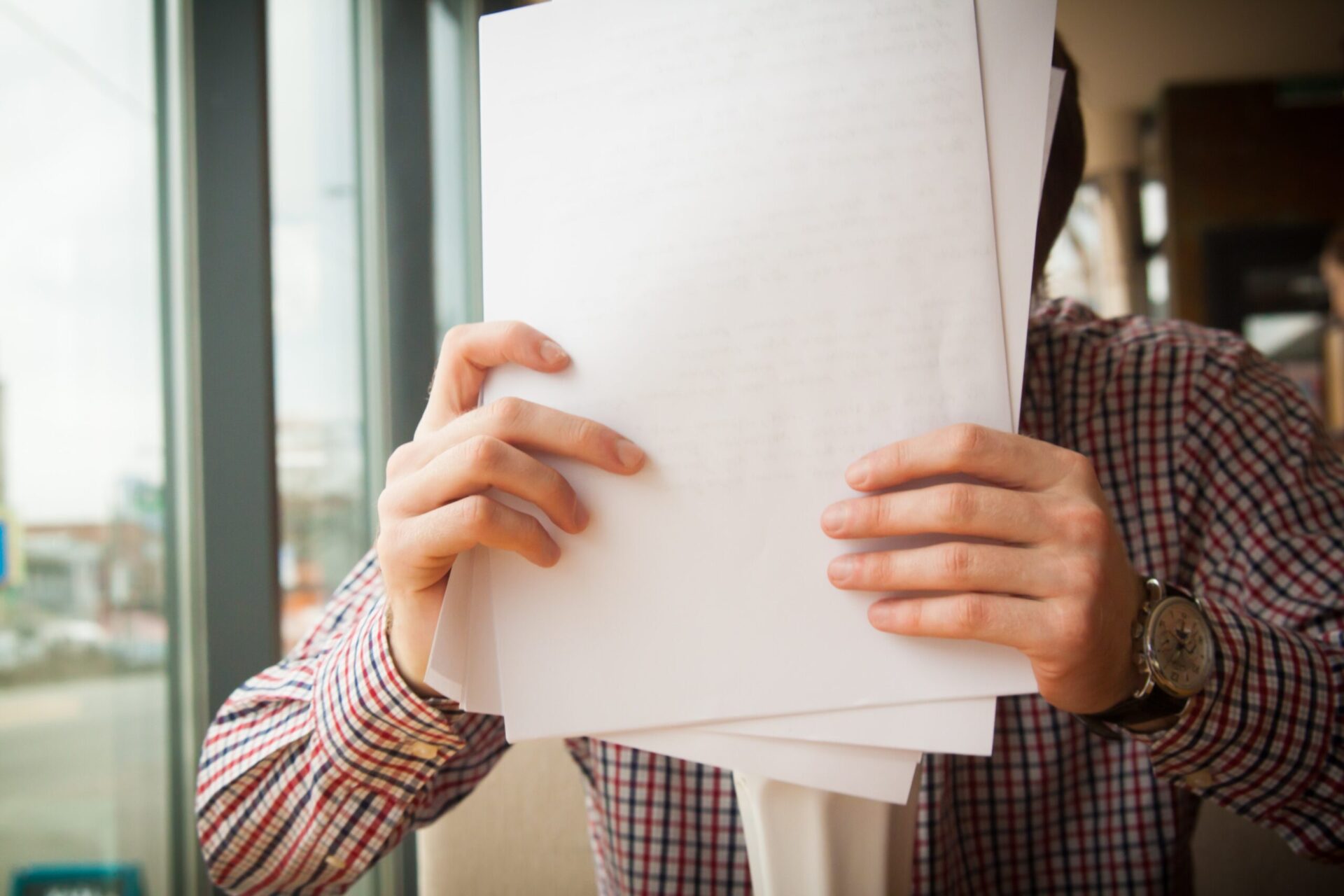
医学部の小論文試験突破には独特の対策が必要です。
医療や社会の知識を日頃から蓄え、論理的な文章表現力を磨くことが重要ですが、一人で対応するには限界があります。
そこで頼りになるのが医学部専門予備校 京都医塾です。
13名の講師チームによる徹底指導
医学部専門予備校 京都医塾最大の強みは、生徒一人に平均13名のエキスパート講師陣がチームで指導にあたることです。
講師陣は京大など難関大学出身で専門知識を磨いたプロばかりで、各科目の情報を共有して指導方針を統一しています。
もちろん、英数理科から小論文・面接まで各教科ごとに専門講師が担当し、あらゆる面から生徒を支えます。
科目間のバランスをとりつつ、一人ひとりの弱点や必要分野を見極めて重点指導を行い、着実に医学部合格へ導きます。
医学部合格へ導く個別カリキュラム
医学部専門予備校 京都医塾では、徹底的な学力分析に基づき、一人ひとりに最適な合格までのロードマップを作成します。
完全1対1の個人授業と少人数の集団授業を組み合わせ、その生徒の現状や目標に応じて、どの時期に何をどこまで学習するかまで綿密に計画します。
教科ごとに内容や進度を変えたオーダーメイドカリキュラムで、効率よく実力を伸ばせるのが特徴です。
しかも、学習の進捗に応じて随時カリキュラムを柔軟に見直し、常に最適化している点もポイントです。
合格まで徹底的に寄り添いサポート
医学部専門予備校 京都医塾の指導・サポートは、生徒が医学部に合格するまで一切途切れません。
入試直前期の不安や緊張がピークに達する時期こそ、講師陣が最後まで手厚く寄り添い支えます。
例えば、受験当日には講師が試験会場まで同行し、直前の質問対応や会場案内までしてくれる「入試会場特別サポート」も行っています。
こうした万全の体制で学習面はもちろんメンタル面まで徹底的にサポートし、生徒を志望校合格へと導きます。
まとめ
今回の記事では、医学部入試の小論文について、その意義から代表的な出題パターン、効果的な書き方のポイントまで詳しく解説しました。
医学部の小論文試験は学力だけでなく受験生の人間性や論理的思考力を見るものであり、日頃から医療・社会分野の知識を蓄えつつ論述の練習を重ねる総合的な対策が重要です。
とはいえ、いざ小論文を書こうとすると「どう書けば評価されるのか」「準備は十分か」と不安になることもあるでしょう。
そんな時こそ心強い味方となってくれるのが医学部専門予備校 京都医塾です。
プロ講師陣による体系的かつ最適化された指導で、知識面・表現面の両方を効果的に伸ばすことができます。
1泊2日医学部合格診断ツアーでは、マンツーマン授業の体験や校舎・寮の見学ができるだけでなく、現在の学力を詳細に分析します。
しかもこのツアーは完全無料で、交通費・宿泊費も京都医塾が全額負担しますので、遠方の方も安心です 。
自分の現状を客観的に知り、今後の戦略を立てる絶好の機会となりますので、本気で医学部合格を目指すならぜひ活用してみてください。