模試の判定で志望校に偏差値が届かず、短期間で偏差値を10上げたいと考えている受験生もいるでしょう。
この記事では、そんな焦っている受験生に向けて、短期間で効率良く偏差値を上げる勉強法を解説します。
偏差値アップに必要な得点や勉強時間の目安、現在の学力帯による難易度の違いを知り、戦略的に学習を進めましょう。
逆転合格を掴むための具体的な計画づくりにぜひ活用してください。
目次
偏差値を10上げるのは可能?必要な得点と勉強量を知ろう
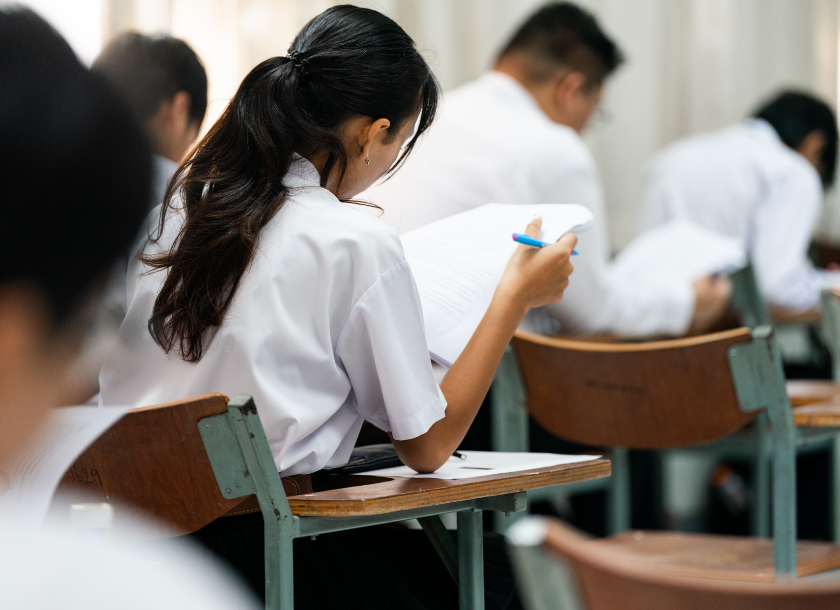
偏差値を短期間で10アップさせるのは簡単ではありませんが、正しい方法で努力すれば十分に達成可能です。
まずは、偏差値を10上げるために必要な得点上乗せや勉強時間の目安を知りましょう。
また、自分の現在の偏差値帯によって上げやすさに差があることも理解しておく必要があります。
ここでは、偏差値10アップに必要な点数・勉強量と、現在の学力別の達成難易度について解説します。
偏差値10アップに必要な得点・勉強時間
偏差値を10上げる基準は模試や試験の難易度によって異なりますが、100点満点換算でおよそ20点の得点上乗せが一つの目安とされています。
つまり、現在の試験で平均点との差が20点縮まれば偏差値が約10上昇すると考えられます。
また、それだけの得点アップを実現するには相応の勉強時間が必要です。
一般に偏差値1アップにつき各科目30~50時間の学習が目安と言われることもあるため、単純計算で偏差値10アップには1科目あたり300~500時間の追加学習時間が必要になります。
これは5教科全体で偏差値を10上げる場合、最低でも数ヵ月の集中した勉強期間が要ることを意味します。
もちろん個人の基礎学力や勉強の効率によって必要時間は前後しますが、「偏差値10アップ=各科目20点前後の得点アップ」という難易度を把握したうえで、計画的に学習時間を確保しましょう。
偏差値の上げやすさは現在の学力次第
偏差値の上げやすさは、現在の学力水準によって大きく異なります。
一般に、偏差値が低いほど上げやすく、高いほど上げにくい傾向があります。
例えば、偏差値40から50に上げる場合、1000人中の順位が841位から500位(上位50%)になるイメージですが、偏差値60から70に上げるには158位から22位(上位2%程度)へ食い込む必要があります。
後者のように上位層で偏差値を上げるには、周りも実力者揃いの中でさらに頭一つ抜ける必要があるため難易度が高く、時間もかかります。
一方で、偏差値50未満の層は基礎を固めるだけで大きく伸びる余地があります。
実際、基礎的な問題を確実に解ければ偏差値50台半ばまで到達可能であり、裏を返せば偏差値55未満の人は基本問題での取りこぼしが原因とも考えられます。
まずは現在の自分の偏差値帯を客観的に把握し、それに応じた戦略を立てましょう。
偏差値が低めの人ほど基礎固め中心の学習で効率良く伸ばせますが、偏差値60前後の人は応用力強化や難問対策にも時間を割く必要があります。
短期間で偏差値を10上げる勉強法のコツ【基礎・弱点・習慣】

ここからは、短期間で偏差値を10上げるための具体的な勉強法のコツを5つ紹介します。
偏差値アップを実現するには、単に闇雲に勉強時間を増やすだけでなくポイントを押さえた効率的な学習が重要です。
以下の観点から、成績を効果的に伸ばす方法を解説します。
基礎を固めて簡単な問題を落とさない
偏差値を大きく上げる第一歩は、基礎を徹底的に固めることです。
教科書レベルの基本事項や頻出の典型問題を「絶対に落とさない」状態に仕上げましょう。
入試や模試では、基本的な問題を確実に正解できるかどうかが合否や偏差値を左右します。
簡単な問題でミスをしないようになれば、それだけで偏差値が上がることもあります。
特に現在偏差値50に届いていない場合は基礎力不足の可能性が高く、応用問題に取り組む以前にまず土台を強化することが必要です。
各科目の基本を完全に理解・暗記し、類題演習で確実に得点できるようにしておけば、偏差値50前後までの底上げが狙えます。
基礎を固めることで「簡単な問題を絶対に落とさない」状態を目指しましょう。
暗記すべき事項は100%習得する
英単語や古文単語、理科や社会の重要用語・年号など、暗記によって得点に直結する分野は短期間で点数を伸ばすために重要なポイントです。
暗記すべき知識は漏れなく頭に入れるつもりで徹底的に覚えましょう。
暗記すべき事項を完璧にしておけば、解ける問題が飛躍的に増えるため、その分得点・偏差値も上がりやすくなります。
特に理科・社会などの科目は、前提知識が単元ごとに独立しており、暗記量に比例して得点力が向上しやすい科目です。
理社の偏差値が低い人はこの機会に総復習して一気に底上げしましょう。
暗記の効率を上げるために、語呂合わせなどの工夫も取り入れつつ、暗記すべきものは残さず習得するという意識で取り組んでください。
苦手科目・分野を分析して重点攻略
総合偏差値を効率良く上げるには、自分の苦手科目や弱点分野を集中的に伸ばす方法もあります。
成績が伸び悩んでいる場合、得意科目よりも苦手科目に大きな伸びしろが残されていることもあるためです。
苦手科目ほど対策によっては大幅な点数アップが見込めるため、まずは模試や定期テストの結果を振り返って自分の弱点を正確に洗い出しましょう。
科目全体だけでなく、科目内の特定単元で極端に正答率が低い部分もチェックします。
そして、それらの弱点科目・分野に優先的に学習時間を投下して集中的に復習・演習を行います。
基本事項の抜け漏れを補い、苦手意識を克服することで、総合偏差値の底上げにつながります。
自分で弱点分析をするのが難しい場合は学校の先生や予備校の講師に相談し、学習すべき優先順位を客観的に判断してもらうのも良いでしょう。
分析を誤ると努力が空回りする恐れがあるため、弱点を正しく見極めた上で重点攻略に取り組んでください。
模試・過去問を活用し弱点を見直す
定期的に模試や過去問に挑戦し、自分の実力を測定・分析することも偏差値アップには欠かせません。
模試を受けっぱなしにせず、解き直しと振り返りにより弱点を見直しましょう。
模試の結果が返ってきたら、間違えた問題の原因を一つひとつ分析します。
「知識不足」なのか「解法ミス」なのか「ケアレスミス」なのかを分類し、それぞれに対策を講じましょう。
例えば、知識不足であれば該当範囲の復習と暗記を、解法ミスなら類題演習で解法プロセスを再確認するといった具合です。
加えて、志望校の過去問も積極的に活用します。
志望大学や学部によって出題傾向や問題形式は異なるため、秋以降の入試対策では各大学の過去問演習が最適です。
第一志望だけでなく受験予定の複数大学の過去問を何年分も解いて、出題パターンに慣れておきましょう。
過去問演習では本番と同じ時間配分で解く訓練をすることで、時間配分の感覚も養います。
解いた後は模試と同様に間違えた問題の解説を熟読し、なぜ誤答したのか分析して次に活かします。
過去問演習と弱点の潰し込みを繰り返せば、実戦力が高まり点数の安定感も増すでしょう。
毎日の勉強習慣と学習環境の整備
短期間で偏差値を上げるためには、毎日の勉強習慣づけと学習環境の最適化も重要です。
まず、勉強を日課にしましょう。
平日・休日を問わず毎日決まった時間に机に向かう習慣を作ることで、学習効率が上がり知識定着も良くなります。
集中できる学習環境を整えることもポイントです。
自宅で誘惑が多い場合は、学校や予備校の自習室・図書館などを活用して強制的に「勉強せざるを得ない環境」に身を置くのも効果的です。
周囲に勉強している人がいる環境では自分のモチベーションも維持しやすくなるでしょう。
偏差値10アップの勉強計画【残りの期間別】

志望校合格までの残り時間に応じて、学習の進め方や重点を置く内容も変えていく必要があります。
ここでは入試までの残り期間別に、偏差値10アップを目指す勉強計画の例を紹介します。
残り半年以上ある場合、3~6ヵ月前、直前1~2ヵ月前の3つの段階に分けて、それぞれの時期に取るべき戦略を見ていきましょう。
自分の今置かれている状況に合わせて計画を立て、効率良く学力を伸ばしてください。
入試半年以上前:基礎固めと弱点克服に注力
入試まで半年以上の時間がある段階では、基礎固めと弱点克服にじっくり取り組むことが重要です。
基礎が不十分なままではいくら勉強時間をかけても偏差値は伸び悩みます。
そこで、まずは各科目の教科書範囲を一通り復習し、基本事項や公式、重要単語を漏れなく習得しましょう。
未習得の単元やあやふやな知識がないように、参考書や問題集の基本レベルをこの時期に完璧に仕上げることを目標にします。
また、自身の模試結果などを分析し、科目ごとの弱点分野を洗い出しておきます。
時間に余裕がある今のうちに、苦手科目や苦手単元に集中的に時間を割いて克服しましょう。
たとえば英語長文が苦手なら単語力を増強し、数学の図形分野が不得意なら基礎問題からやり直す、といった具合に弱点補強にじっくり時間を使います。
学習計画の管理もこの時期から徹底します。
半年以上という比較的長期の受験勉強は長期戦なので、大きな目標だけでなく週単位・月単位の目標も設定しましょう。
「今週中に数学の〇〇分野の問題集を終える」「今月は英単語を○○語覚える」といった具体的な短期目標を立てることで、進捗状況が把握しやすくなりモチベーション維持につながります。
入試3~6ヵ月前:応用問題演習と実戦力強化にシフト
入試まで残り数ヵ月(約3~6ヵ月)となった段階では、基礎固めに加えて応用力の養成と実戦的な演習にシフトしていきます。
基礎が固まった科目から順に問題集や過去問に取り組み、応用問題への対応力を高めましょう。
ここで重要なのは、ただ解くだけでなく間違えた問題の徹底復習をすることです。
応用問題集や過去問演習で出会った問題でミスしたものは、解説を読み込んだ上でもう一度自力で解き直し、完全に解法を自分のものにします。
難しい問題も含め、解けなかった問題を必ず解けるようにする反復練習が偏差値アップには欠かせません。
また、本番を意識した模擬試験の活用も増やしましょう。
夏以降であれば各予備校のオープン模試や実戦模試など志望校レベルの試験を積極的に受験し、自分の実力を客観視します。
模試では時間配分や試験特有の緊張感に慣れる訓練もできますし、判定を通じて弱点発見にも役立ちます。
さらにこの時期、過去問演習も本格化させます。
志望校の過去問はもちろん、併願校や同レベル大学の過去問にも触れて多様な問題に慣れておきましょう。
残り数ヵ月で一気に偏差値を伸ばすには、本番さながらの演習量を積み、実戦力を鍛えることが大切です。
入試直前1~2ヵ月:過去問演習と総復習で仕上げ
入試直前の1~2ヵ月は、新しい参考書や問題集に手を出さないことが重要です。
直前期の不安から「もっと難しい問題集に取り組んだ方がいいのでは」と思うかもしれませんが、それまで使ってきた教材を完璧に仕上げることをおすすめします。
新しい教材に手を出すと解き方の違いに混乱したり、解けない問題が多く自信を失ったりするリスクがあります。
直前期は目新しいことに手を広げず、今持っている教材を繰り返し復習して完全に理解することを目指してください。
具体的には、これまで解いた問題集や過去問の誤答箇所を総ざらいし、解き直して全問正解できるようにします。
弱点だった単元の復習プリントやノートも見直し、知識の抜け漏れを最終チェックしましょう。
また、暗記科目の総仕上げにも適した時期です。
入試直前に得点アップが見込めるのは理科・社会など暗記要素の強い科目であり、用語や年号を覚えれば覚えるほど本番の得点につながります。
もし理社の点数がまだ低いようであれば、この残り1~2ヵ月で徹底的に暗記に注力し、大幅な点数アップを狙いましょう。
ただし暗記するだけではなく、必ず問題演習もセットで行い、覚えた知識を実際の問題で使える状態にしておくことが大切です。
本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾
医学部合格には偏差値アップだけでなく、効率的に成果を出す学習環境が欠かせません。
医学部専門予備校 京都医塾は、受験生を多角的なサポート体制と徹底した学習管理で後押しする医学部専門予備校です。
入試本番から逆算したオーダーメイドカリキュラムと到達度チェックで、限られた時間を合格力に変える仕組みが整っています。
一人ひとの実力に合わせた個別カリキュラム
医学部専門予備校 京都医塾では、入塾時の学力診断をもとに講師担任+教務スタッフ2名=計3名が担当であなた専用の学習ルートを設計します。
到達度テストと面談で進度を微調整し、弱点の対策と得意分野のさらなる効率アップを目指します。
限られた残り時間を一点突破ではなく全科目の底上げに変える設計力こそ、短期間で偏差値を伸ばせる理由です。
学習と生活を丸ごと支える寄り添いサポート
医学部合格には継続力が不可欠です。
医学部専門予備校 京都医塾では、学習計画はもちろん生活リズムやメンタル面まで毎日フォローします。
朝の声かけで学習スイッチを入れ、夜は学習記録を確認してフィードバックに活用します。
定期面談で目標の軌道修正とモチベーション維持を図り、保護者への進捗共有も可能です。
学習に集中できる環境と手厚いサポートで、短期間の偏差値アップと志望校合格を強力に後押しします。
合格実績と診断ツアーで最短ルートを可視化
医学部専門予備校 京都医塾は、毎年国公立大学から私立大学まで多数の医学部合格者を輩出しています。
合格データを分析して導き出した「合格までの王道プロセス」を、あなた専用カリキュラムに落とし込めるのが強みです。
入塾前に参加できる無料「1泊2日医学部合格診断ツアー」では、学力診断と志望校分析を通じてギャップを数値化し、プロ講師が合格までのロードマップを設計します。
まとめ
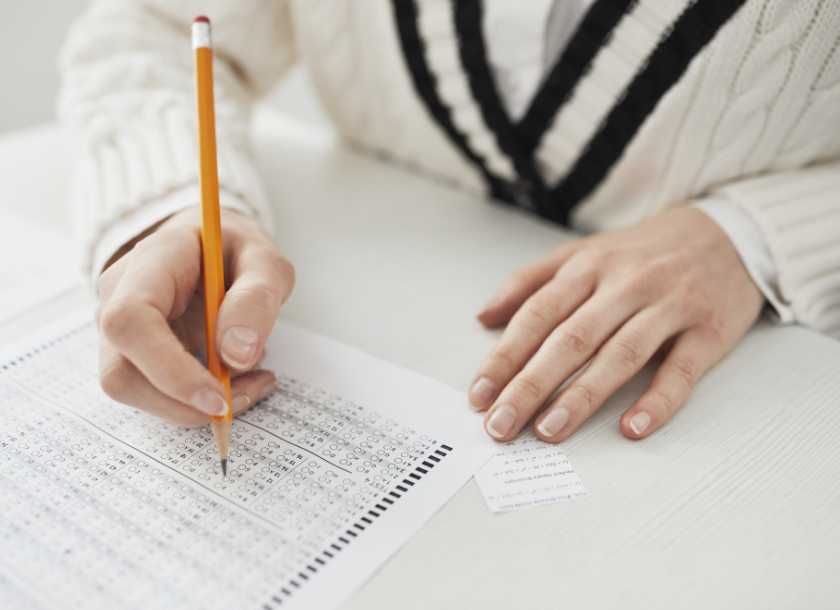
偏差値を10上げるためには、基礎徹底や弱点克服などを着実にこなすことが必要です。
この記事では、必要な得点と勉強時間の目安や学習のコツ、残り期間別の学習計画まで具体的に解説しました。
「何を、いつ、どのくらい」やるかを可視化し、日々の学習行動を最適化することが偏差値アップにつながります。
一方、独学では計画の精度や継続力に不安が残り、途中でスケジュールが狂ってしまうリスクもあります。
そんな課題を根本から解決できるのが医学部専門予備校 京都医塾です。
個別カリキュラムやICTを活用した学習管理により、勉強時間の確保からメンタル面までサポートします。
現在実施中の「1泊2日医学部合格診断ツアー」では、授業体験と学力診断をもとに合格までのルートを具体化できるため、限られた時間で偏差値を伸ばしたい受験生に大きなメリットがあります。
交通費・宿泊費無料で参加できるこの機会を活用し、あなたも最短距離で医学部合格をつかみ取りましょう。


