医学部の受験において、共通テストで思うような得点が取れなかったとき「もう合格は無理なのでは」と不安になるでしょう。
特に6割前後の得点率しか出せなかった場合、データを見る限り国公立大学医学部の合格は厳しいといえます。
しかし、少ないながらも共通テストでの6割の得点率で合格を勝ち取った例もあり、「絶対無理」とは限りません。
今回の記事では、共通テストでの6割の得点率だった場合の医学部合格の可能性と戦略について解説します。
目次
国公立大学の医学部の平均ボーダー得点率
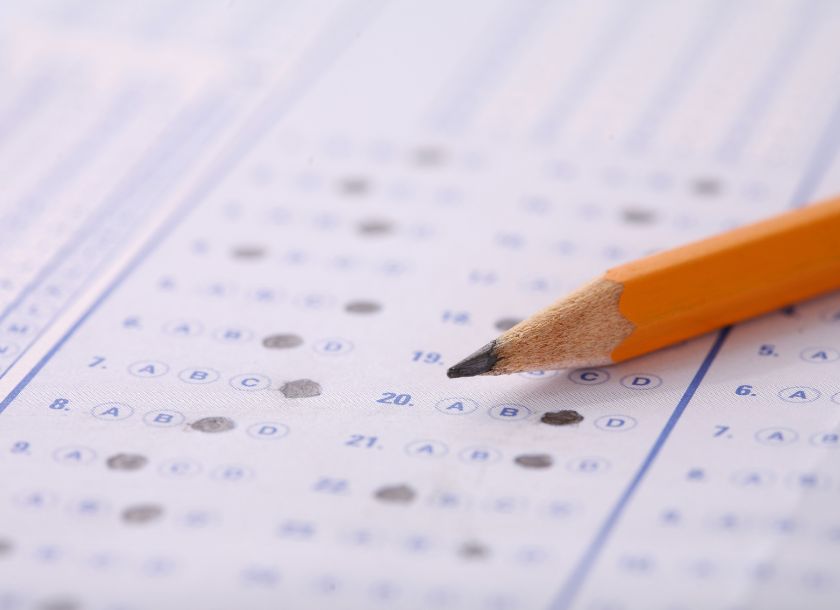
まずは国公立大学医学部に50%の確率で合格するとされる、「ボーダー得点率」の平均について見てみましょう。
なおデータについては、2025年度のデータを用いています。
| 大学名 | 2025年度ボーダー得点率 |
| 東京科学大学 | 95 |
| 東京大学(理Ⅲ) | 93 |
| 京都大学 | 91 |
| 大阪大学 | 90 |
| 浜松医科大学 | 90 |
| 名古屋大学 | 89 |
| 北海道大学 | 88 |
| 九州大学 | 88 |
| 鹿児島大学 | 88 |
| 千葉大学 | 92 |
| 神戸大学 | 87 |
| 大阪公立大学 | 87 |
| 東北大学 | 87 |
| 秋田大学 | 87 |
| 福井大学 | 87 |
| 奈良県立医科大学 | 86 |
| 三重大学 | 86 |
| 名古屋市立大学 | 86 |
| 横浜市立大学 | 85 |
| 岡山大学 | 85 |
| 広島大学 | 85 |
| 京都府立医科大学 | 85 |
| 新潟大学 | 85 |
| 信州大学 | 85 |
| 滋賀医科大学 | 85 |
| 筑波大学 | 84 |
| 徳島大学 | 84 |
| 熊本大学 | 84 |
| 金沢大学 | 83 |
| 岐阜大学 | 83 |
| 和歌山県立医科大学 | 83 |
| 鳥取大学 | 83 |
| 山口大学 | 83 |
| 群馬大学 | 83 |
| 山形大学 | 82 |
| 札幌医科大学 | 82 |
| 佐賀大学 | 82 |
| 長崎大学 | 82 |
| 宮崎大学 | 82 |
| 愛媛大学 | 82 |
| 富山大学 | 81 |
| 島根大学 | 81 |
| 香川大学 | 81 |
| 福島県立医科大学 | 80 |
| 高知大学 | 80 |
| 旭川医科大学 | 79 |
| 弘前大学 | 79 |
| 大分大学 | 76 |
| 琉球大学 | 76 |
※参照:国公立大学医学部の共通テストの合格ボーダーラインの推移
共通テストで6割の得点率だと医学部合格が厳しい理由
ボーダー得点率の平均データから明らかなように、共通テストで6割の得点率だと医学部合格が厳しいことがわかります。
以下で、ほかの要因も含めてもう少し具体的に共通テストの得点率と合格の可能性の関係について解説します。
医学部合格者の多くが共通テストで6割をはるかに上回る得点を取っている
表から見てもわかる通り、国公立大学医学部の共通テストのボーダー得点率は平均で約80%、最も低い大学でも75%を超える非常に高い水準です。
ボーダー得点率は一般的に「50%の確率で受かるライン」として算出されているため、「この得点率以下だと合格できない」というわけではありません。
また、二次試験の結果によってはこれより低い得点率でも合格する可能性もあるでしょう。
しかし一般的な医学部に合格できる受験生の水準として「共通テストの得点率は8割以上が基本」と考えられます。
6割の得点だと「足切り」で二次に進めない可能性がある
多くの国公立大学医学部では、「第一段階選抜」が実施される可能性がある点も共通テストで6割の得点率だと合格が難しい理由の一つです。
第一段階選抜はいわゆる「足切り」と呼ばれ、あらかじめ公表した倍率を超えた場合や設定された得点を下回る場合に一次試験不合格となり二次試験に進めなくなるものです。
すべての大学が足切りを行うわけでもなく、毎年実施するとは限りません。
しかし「二次試験の受験者数を絞る」という目的上、共通テストの得点率が6割程度だと挽回のチャンスもなく、そもそも二次試験に進めない可能性が高くなってしまいます。
二次試験での逆転は現実的に難しい
もし足切りの実施がなかったりなんとか足切りを突破できたりしても、「最終合格」が目的である以上、二次試験を合わせた得点でほかの大部分の受験生に勝たなければいけません。
そのためには、二次試験でほかの受験生を凌ぐ「圧倒的な得点力」が求められます。
共通テストで取れる得点が6割程度の学力では、二次試験で大逆転するのは非常に難しいのが実情です。
共通テストで6割の得点率で医学部を目指すには?

ここまでの話を読んで、「やっぱり共通テストで点が取れなかったら医学部合格は不可能なのか」と思う受験生もいるでしょう。
しかし「6割の得点率で医学部に合格した」という話もあり、「難しいが可能性はある」ともいえます。
次に、共通テストの得点が低かった場合でも医学部合格に近付くための方法について解説します。
共通テスト比率が低い大学を狙う
各国公立大学の全体に対する共通テストの得点の割合は平均で見ると50%弱ですが、大学ごとに20%〜90%と大きく異なります。
そのため、以下のような共通テストの得点比率が低い大学を選ぶと二次試験で挽回できる確率が上がります。
▼共通テストの得点比率が全体の1/3以下の大学【2025年度】
- 東北大学
- 京都大学
- 大阪大学
- 山梨大学
- 金沢大学
- 千葉大学
- 名古屋市立大学
- 岡山大学
ただし二次試験の比重が高い大学は難易度が高い場合も多く、「本来の実力が出せなかった」「得点が低かったのが二次試験にない文系科目」などのケースでない限り挽回は難しいと考えられます。
足切りの可能性が低い大学を探す
「足切り」実施の有無は年度によって変わる可能性があり、これまで足切りがなかったからといって今後もないとは限りません。
しかし、これまで足切りの実施が少ない大学や倍率が低めの大学を選んで出願すると二次試験に進める可能性が増えるでしょう。
例えば、広島大学や山形大学の前期試験では、2023年度から2025年度まで一度も足切りは実施されていません。
得意・不得意科目に合った傾斜配点の医学部に出願する
多くの大学では、共通テストの科目ごとの配点を高く、または低く設定する「傾斜配点」を設定しています。
そのため、得点が高かった科目の配点が高く、低かった科目の配点が低い大学を選ぶことで、より高得点を狙いやすくなります。
得意・不得意科目の差が大きかったり、マークミスなどで特定科目の得点だけ低くなってしまったりした場合には、失点をカバーできる可能性が上がるでしょう。
私立大学医学部の併願を検討する
国公立大学より前に私立大学前期の出願が始まるスケジュール上、共通テスト後の私立大学医学部への路線変更は合格難易度が高い後期試験などを短期間で対応することになり難しいでしょう。
しかし「共通テスト直前期で模試の結果が悪かった」という場合には、共通テストが必要ない私立大学医学部への方向転換も検討する余地があります。
学費の面で私立大学への進学が難しい場合には、日本学生支援機構(JASSO)の貸与型奨学金や民間機関・大学独自の奨学金についても検討してみましょう。
地域枠の受験を検討する
「国公立大学の医学部に進学できれば場所は問わない」と考えるなら、地域枠の受験を検討してはどうでしょうか。
医学部の地域枠は、卒業後に指定された地域の医療機関で一定期間勤務する義務があり将来的な勤務地やキャリアプランに一定の制約が生じます。
そのため、一般枠と比べて出願者が少なく、倍率や合格最低点が低い大学も多くあるため合格の可能性が上がります。
共通テストで6割の得点率で合格するために二次試験で必要な得点は?

ここで、「二次試験で挽回」するためにはどのくらいの得点率が必要かについて実際にシミュレーションを行ってみましょう。
共通テストの配点比率が低い東北大学で、共通テストの得点率が約6割だった場合にボーダー付近に届く配点の例が以下の通りです。
| 科目 | 配点 | 得点 | |
| 共通テスト(一次試験) | 外国語 | 100 | 75 |
| 数学 | 100 | 70 | |
| 理科 | 100 | 70 | |
| 国語 | 100 | 47 | |
| 地歴公民 | 100 | 51 | |
| 情報 | 50 | 37 | |
| 共通テスト(一次試験)合計 | – | 550 | 350(62.7%) |
| 二次試験 | 英語 | 600 | 537.5 |
| 数学 | 600 | 537.5 | |
| 理科 | 600 | 537.5 | |
| 面接 | 400 | 320 | |
| 二次試験合計 | – | 2200 | 1933 |
| 総計 | – | 2750 | 2278(82.8%) |
このように、二次試験(学科)で約9割の得点を取ることができればボーダーラインに届くと考えられます。
本気で医学部合格を目指すなら京都医塾
共通テストの得点が思うように伸びず、「このままでは間に合わないのでは」と不安を抱えている受験生へ。
限られた時間の中で合格を現実にするためには、戦略的な学習環境とプロの支援が必要不可欠です。
京都医塾は、医学部合格に特化した医学部専門予備校として、これまで数多くの合格者を輩出してきました。
特筆すべきは、偏差値40台から医学部へ合格した生徒の実績もあるという点。
高い専門性をもとに、今の学力からでも合格を目指すことが可能です。
偏差値40台からでも医学部合格を可能にする完全個別戦略の学習体制
共通テストで6割前後の得点率だったとしても、戦略と環境次第で医学部合格は狙えます。
京都医塾では、実際に偏差値40台から医学部に合格した生徒が多数おり、その秘訣は生徒ごとに設計された「完全オーダーメイドの学習戦略」にあります。
英数理それぞれの理解度に応じたレベル別の授業クラスは細かく分かれており、得意な教科は高レベルで鍛え、苦手な科目は1対1の個人授業で基礎から補強するという柔軟なカリキュラムが組まれます。
生徒ごとに最大13名の講師チームが担当し、週ごとの進捗を確認しながら学習内容をリアルタイムで最適化するため、無駄なく合格に直結する学力を身につけることができます。
出願戦略から面接対策まで、合格に必要なすべてを徹底サポート
共通テストの得点が伸びなかった場合、出願戦略と二次対策でどこまで巻き返せるかが勝負になります。
京都医塾では、大学ごとの出題傾向や配点、入試日程や移動時間まで考慮した上で、最も現実的かつ合格に近づける出願校を提案します。
願書の記入や志望理由書の作成、小論文や面接の対策においても、生徒任せにせず、講師と担任が二人三脚でサポート。
出願の進捗管理や面接での表現の指導など、実際の試験までにやるべきことを明確にし、抜け漏れのない状態で本番に臨める体制を整えています。
勉強以外の不安や負担を最小限に抑えることも、京都医塾の強みです。
全国から参加多数、1泊2日で受けられる「医学部合格診断」
今の自分の実力で、医学部合格が現実的かどうかを正確に知りたい。
そんな受験生に向けて、京都医塾では「1泊2日医学部合格診断ツアー」を実施しています。
初日に行われる学力診断をもとに、講師と担任が現状を分析し、個別の合格戦略を設計。
翌日には実際の授業を体験し、医学部専門予備校としてのサポート体制を直接確認することができます。
校舎から徒歩5分の専用学寮で宿泊でき、学習に集中できる環境をそのまま体験できるのも大きな魅力です。
交通費・宿泊費は全額京都医塾が負担するため、遠方からの参加者も安心してご参加いただけます。
自分に何が足りないのか、どこをどう伸ばせばいいのかを、短期間で明確にできる貴重な機会です。
まとめ
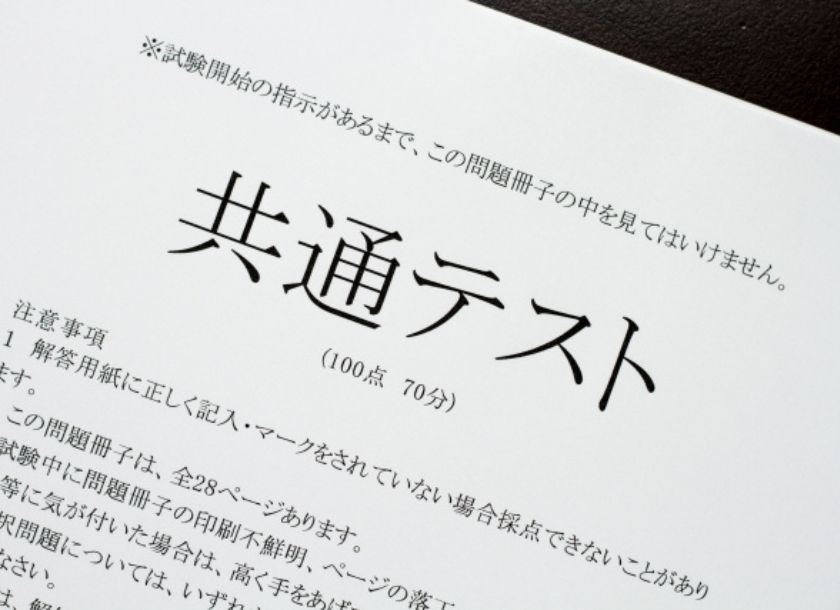
共通テストで6割という得点率は、一般的なボーダーから見れば確かに高いとは言えません。
しかし、得点比率の低い大学を狙うことや、二次試験に強みを持たせる戦略を取ることで、まだ合格の可能性は残されています。
そのためには、現状の学力を正しく把握し、無駄のない努力を重ねることが不可欠です。
京都医塾の「1泊2日医学部合格診断ツアー」は、そのための最初の一歩となります。
参加は無料で、交通費と宿泊費もすべて支給されるため、受験生・保護者ともにリスクなくご参加いただけます。
医学部合格を本気で目指すなら、現状を変える行動が必要です。
自分の可能性を知り、最適な学習戦略と出会うために、ぜひ京都医塾の「1泊2日医学部合格診断ツアー」にお越しください。


