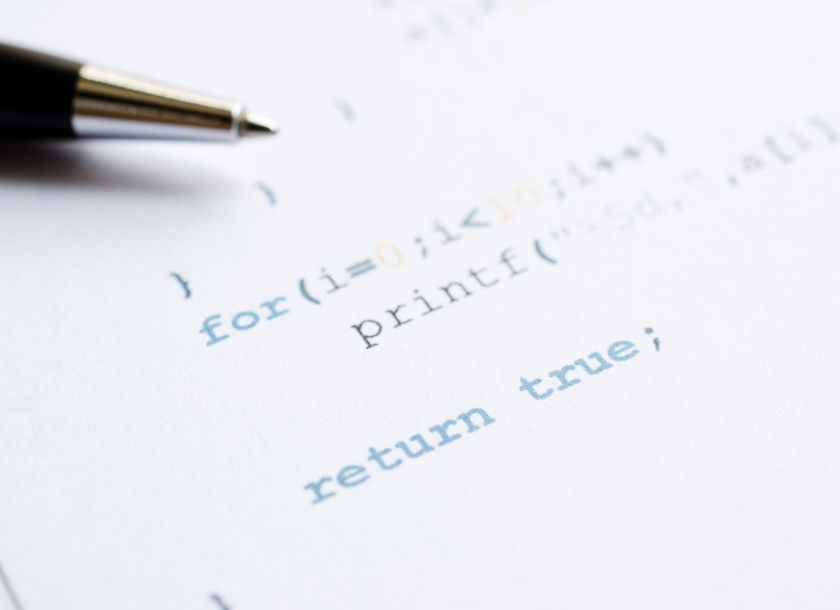共通テスト「情報Ⅰ」は、概ね10%前後の配点と少ないですが、落とすと合否に響く取りこぼせない科目です。
今回の記事では、情報Ⅰの4分野である「情報社会・情報デザイン・プログラミング・ネットワーク」を横断し、頻出キーワードと得点アップのコツをわかりやすく整理しました。
法律名の覚え方から擬似言語DNCLの読み解き方、夏までに覚えること、秋からの学習プランまで、医学部志望の理系受験生が60分で90点を目指すための実践的な暗記ポイントをまとめました。
目次
情報社会の問題解決で覚えるポイントと重要用語
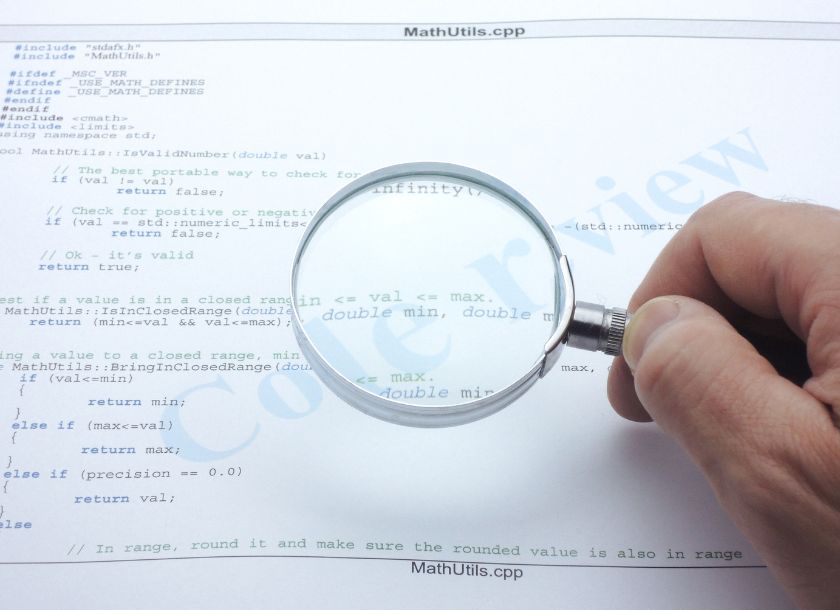
この分野で問われるのは「適切に情報を扱う姿勢」と「関連法令の基礎知識」です。
個人情報保護法や著作権法、不正アクセス禁止法などは、法律名+目的というペアで覚えると定着が早まります。
たとえば以下のような内容です。
- 個人情報保護法:個人データを正しく管理し、本人の権利を守る
- 不正アクセス禁止法:アクセス権限を持たない操作を禁じる
これらの法律は実生活のニュースと結び付けると忘れにくくなります。
さらに情報セキュリティ三要素(機密性・完全性・可用性)は、「鍵を掛ける・壊させない・いつでも使える」の3語で置き換えるとイメージしやすいでしょう。
頻出キーワード一覧(情報倫理・セキュリティ)
キーワードは「攻撃の種類」と「対策ツール」をセットで覚えると実戦で活きます。
例として、フィッシング詐欺と二要素認証、コンピュータウイルスとウイルス対策ソフトがあります。
この脅威と盾の対応表を作っておくと、選択肢問題で迷いません。
定義と具体例で覚えるコツ
用語カードを作る際は、「語句・定義・最新ニュース・対策」の順に並べてみてください。
例えば、以下のように具体例で覚えることもおすすめです。
- パスワードリスト攻撃
- 流出したID・PWを使う
- 大手ECサイトの不正購入事件
- ID連携を避ける
自分事として状況を思い浮かべれば、ただの暗記が「判断力」に変わります。
コミュニケーションと情報デザインで覚えるポイントと重要用語
ここではデータを「どう表し、どう変換するか」がテーマです。
ビットとバイト、二進数と十六進数、画像の解像度や音声の標本化いずれも公式そのものはシンプルです。
| 媒体 | 計算式 | 暗記ポイント |
| 画像 | 縦×横×色深度 | 1Byte=8bit換算を忘れず |
| 音声 | 周波数×量子化×時間×チャンネル | kHz→Hz変換に注意 |
ポイントは「数字と用語を結び付け、すぐ計算できるか」にあります。
試験では画像の容量や音声データ量を問う設問が頻出。
例題を「自分のスマホ画像なら?」と置き換えて計算してみるだけで、理解が深まります。
ディア・データ表現の用語チェックリスト
メディア・データ表現の用語チェックリストは以下の通りです。
- ビット/バイト:1バイト=8ビット
- 解像度とピクセル:画質のきめ細かさを示す指標
- 可逆/非可逆圧縮:元に戻せるか否かで目的が異なる
一覧は最小限に絞り、「計算で扱う数字」と合わせて暗記するのがコツです。
図表・計算系問題を解くポイント
計算式は「画像=縦×横×色深度」「音声=周波数×量子化ビット数×時間×チャンネル」を丸暗記し、そのうえで単位変換を覚えましょう。
ビット⇔バイト、秒⇔ミリ秒など、途中で単位が変わる設問が定番です。
計算練習はストップウォッチで1問1分を目標にすると試験時間配分の感覚がつかめます。
コンピュータとプログラミングで覚えるポイントと重要用語

配点が最も高い得点源です。
共通テストの擬似言語 DNCL は日本語メインで、基本は「順次・分岐・繰り返し」の三つの制御構造を読み取れるかどうかです。
- 順次:上から下へ命令をそのまま実行
- 分岐:条件によってAまたはBを選ぶ
- 繰り返し:条件を満たすまで同じ処理をループ
コードを「日本語の手順書」として音読すると流れがつかみやすく、ミスを減らせます。
擬似言語DNCLの基本構文と用語
DNCLの文法は「表示する(変数)」「もし〜ならば」「〜の間繰り返す」など、直感的な日本語が多いのが特徴です。
教科書の例文を3行ずつ書き写し、手でトレースするだけでも理解は進みます。
ポイントは「配列は0番から始まり、変数宣言は不要」といったローカルルールを覚えておくことが重要です。
それだけで読解スピードが上がります。
アルゴリズム・データ構造の頻出語句
線形探索は「上から順に探す」、二分探索は「真ん中を基準に半分ずつ探す」。
この2手法と、順次→分岐→繰り返しの制御構造を組み合わせれば、多くの設問は解けます。
解説を読む際は「手で図を描き、処理の流れを可視化」すると頭に残ります。
「配列の要素がどう動くか」を色ペンで塗り分けるのもおすすめです。
情報通信ネットワークとデータ活用で覚えるポイントと重要用語
ネットワーク技術とデータ分析が合流する分野です。
序盤は用語暗記中心、終盤はグラフやアクセスログを読んで答える設問が続きます。
ネットワーク・セキュリティ関連語
OSI7階層の上位3層(アプリケーション・プレゼンテーション・セッション)がTCP/IPでは1つの「アプリケーション層」に統合されることを押さえておきましょう。
| OSI層(上→下) | 役割(共通テストレベル) | 代表プロトコル例 | TCP/IP層 | 代表プロトコル例 |
| アプリケーション層+プレゼンテーション層+セッション層 | アプリケーション間のデータ交換・表現形式・接続管理を規定する | HTTP、SMTP、FTP | アプリケーション層 | HTTP、SMTP、FTP |
| トランスポート層 | 通信の信頼性や流量制御を担当する | TCP、UDP | トランスポート層 | TCP、UDP |
| ネットワーク層 | 経路選択と論理アドレス(IP アドレス)を扱う | IP、ICMP、ARP | インターネット層 | IP、ICMP、ARP |
| データリンク層 | 同一物理媒体上のフレーム転送を扱う | Ethernet、PPP | ネットワークインタフェース層 | Ethernet、PPP |
| 物理層 | 電気・光信号やコネクタなど物理的仕様を扱う | 100BASE‑T、Wi‑Fi | ネットワークインタフェース層 | 100BASE‑T、Wi‑Fi |
※TCP/IPモデルではOSIの最上位3層(アプリケーション/プレゼンテーション/セッション)を1つのアプリケーション層にまとめています。
※参照:基本情報技術者試験
データベース・統計活用のキーワード
SQLの基本は「SELECT [取得したい要素] FROM [使用テーブル] WHERE [条件文]」の三段構えとして覚えておきましょう。
実際に簡単な構文を書いてみると理解が早まります。
また、平均値・中央値・最頻値は、数直線上に並べてみると違いがひと目で分かります。
共通テスト情報Ⅰの出題傾向と勉強法
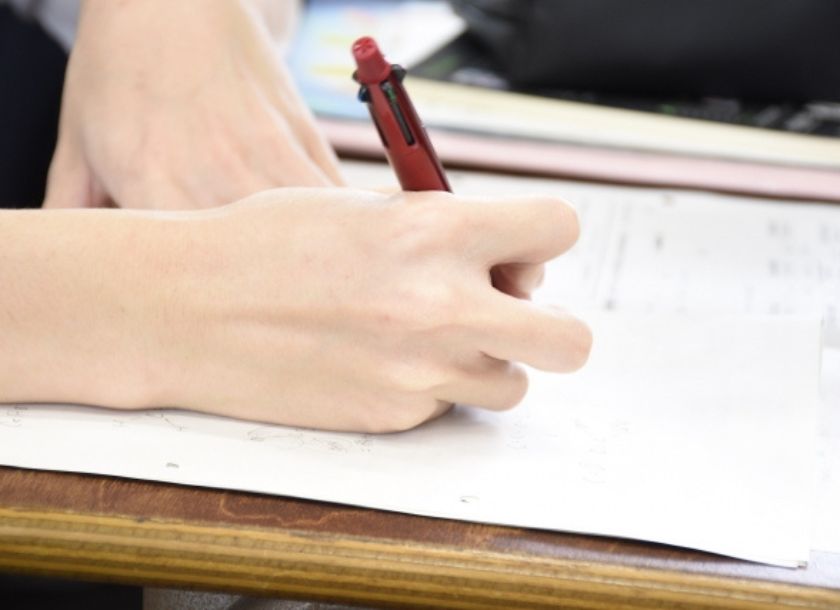
続いて、出題傾向と勉強法を解説します。
試験は大問4つ・60分、文章量が多いため、知識問題を即答できるかどうかがタイムマネジメントとして重要です。
配点・試験時間と問題構成
試作問題では「情報社会20点・情報デザイン30点・プログラミング25点・ネットワーク25点」。
プログラミングとネットワークで計50点の比重があるため、ここを落とすと一気に失点します。
60分で約40問を解くには「最初の10分で知識系を片付け、残りを思考系に回す」程度のペースが理想です。
暗記と思考問題を両立させる学習計画
受験までの学習計画として、季節ごとに覚えることをまとめると主に以下のイメージです。
- 春(3〜5月):教科書用語を2周/一問一答開始
- 夏(6〜8月):用語完了→簡易読解問題に着手
- 秋(9〜11月):試作・予想問題で時間感覚を養成
- 冬(12〜1月):過去問総仕上げ/弱点カード再確認
このこまめな復習が点数を押し上げます。
模試は解きっぱなしにせず、間違えた問題をカード化し1週間後に再チェックすると弱点の対策ができるでしょう。
本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾
情報Ⅰは「覚えることが多いのに配点は低い」と敬遠されがちですが、医学部合格の鍵は取りこぼさない科目を1つでも増やすことです。
医学部専門予備校 京都医塾では、英数理の得点力を伸ばしつつ情報Ⅰを短期で仕上げる独自ノウハウを用意しております。
教科間のバランス管理から演習量の最適化まで、忙しい受験生でもムダなく得点を伸ばせる環境が整っています。
13名の講師チームが科目バランスを徹底管理
医学部専門予備校 京都医塾では生徒一人を約13名の専任講師が担当し、毎週のカンファレンスで進度と理解度を共有します。
数学で演習が増えれば英語は復習中心に切り替えるなど、教科ごとのウェイトを細かく調整。
疑問が出た瞬間に教科担当へ質問できる体制が、情報Ⅰのような後発科目でも「後手に回らない」学習リズムを実現します。
講師同士が横につながっているからこそ、学習の偏りや抜けが素早く補正できることが合格率62%を支えるチーム指導の強みです。
一人ひとりに最適なオーダーメイド指導
入塾時の診断テストで弱点と得意分野を可視化し、その場で個別カリキュラムを作成します。
英語は最上位、化学は基礎など科目ごとに細かくクラス分け。
模試や小テストの結果をもとに週単位でプランを更新するため、「やるべきこと」が常に明確です。
短期間で情報Ⅰの用語暗記を終えたいなら、暗記フェーズを集中配置し、翌週から演習モードへ切り替えるそんなフレキシブルさで時間を最大限に活用できます。
集中力と生活習慣を鍛える最適環境
校舎には自分専用の自習ブースがあり、教材を置きっぱなしで毎日同じ席に座れます。
遠方生向けには徒歩5分の学寮を完備し、起床・就寝時刻まで管理。
紙教材と連動したタブレット学習システムで、電車の移動中も一問一答動画で情報Ⅰの用語を確認できます。
こうして「学ぶ・休む・定着させる」のサイクルを生活ごとデザインすることで、最後の1点まで積み上げる集中力を養います。
まとめ
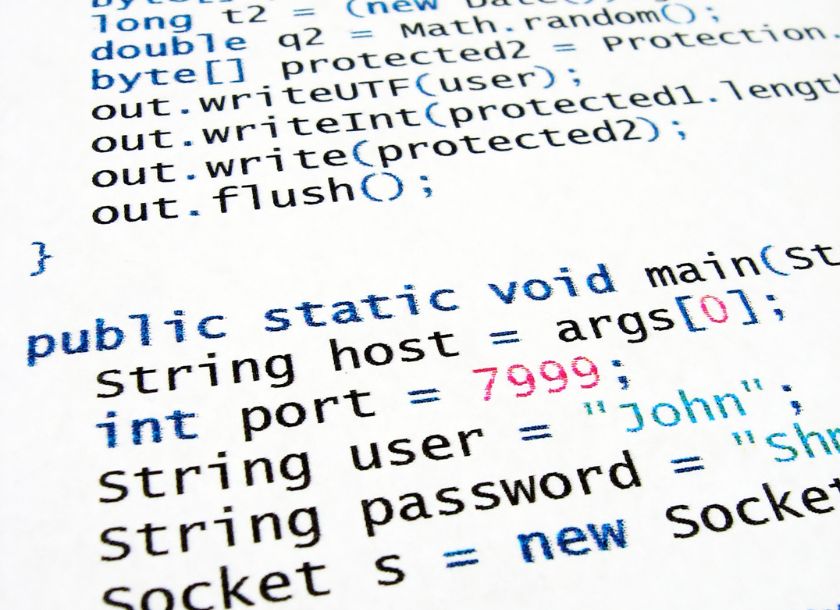
情報Ⅰは知識系と思考系が混在し、限られた60分で40問前後を解き切るスピードも要求されます。
今回の記事では、法律・セキュリティ用語のペア暗記、ビット換算やSQLの計算・読解力、そして夏まで暗記→秋以降演習という時期別対策を紹介しました。
情報Ⅰの配点は概ね10%前後でも、ここを取りこぼさないことが合格ラインを押し上げます。
今なら交通費・宿泊費不要で「1泊2日医学部合格診断ツアー」に参加可能です。
お申込みはオンラインから可能なのでぜひご参加ください。