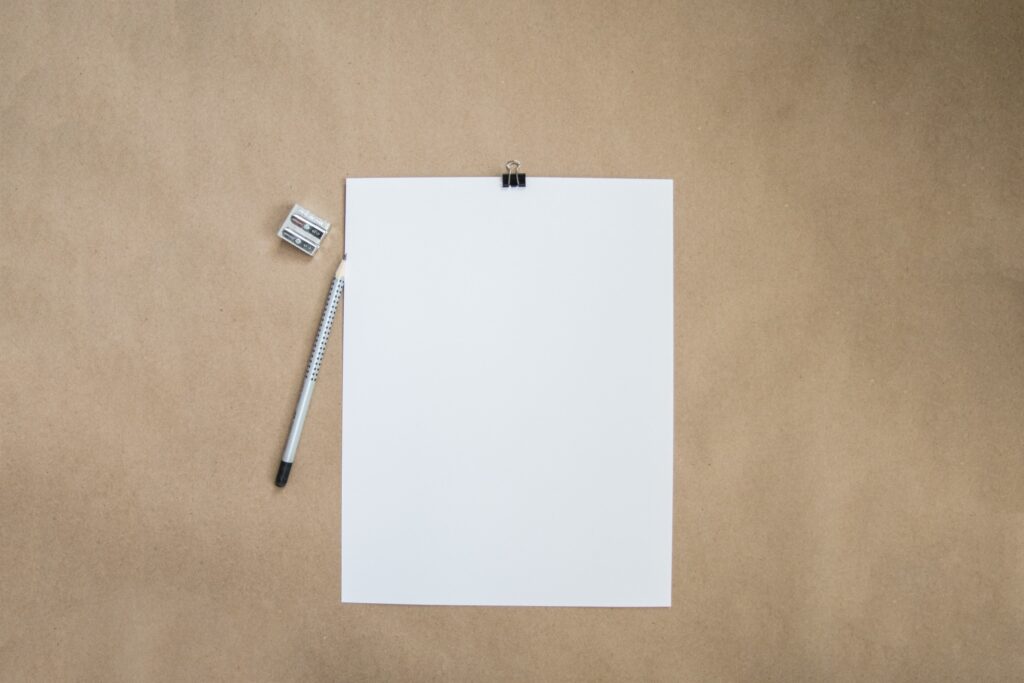医学部受験をする上で欠かせないのが医学部模試です。
医学部模試とは、医学部合格に向けた実力を測るために行われる模擬試験のことで、入試本番前に何度も受験しておくことで大きな効果が期待できます。
しかし、数多くある模試の中から最適な模試をどのように選んで受験すべきか、なかなか分からないという人も多いでしょう。
ここでは、医学部模試の選び方や受験のポイント、模試のメリットとデメリット、模試の活用方法について解説していきます。
目次
医学部模試の種類と概要
医学部受験生向けの模試にはさまざまな種類があり、大きく2つに大別されます。
1つ目は共通テスト対策の模試(マーク模試)、2つ目は国公立大学二次試験や私立大学一般入試対策の模試(記述模試)です。
マーク模試は、大学入学共通テストや国公立大学医学部の一次試験対策としてマーク式で出題される模試です。
2021年度からセンター試験に代わって共通テストが実施されるようになり、過去問の蓄積が少ないこともありました。
現在でもセンター試験と比べれば共通テストの実施年数は浅いため、共通テスト形式のマーク模試を積極的に受験し、問題形式や時間制限に慣れておくことが重要です。
記述模試では、論述形式の問題を含む記述式の模試となります。
内容としては、医学部受験生であれば学部や志望校に関係なく受ける価値のある良問が揃った模試や、大学ごとの医学部の出題傾向に沿った大学別模試などがあります。
例えば、大手予備校が提供する医学部二次試験対策模試には、全国すべての医学部を対象とした模試も存在します。
このような模試では、自分の学力の傾向に合った医学部を判断する材料にもなり、志望校選びにも役立てることができます。
医学部模試を受けることのメリット

医学部模試を受けることには多くのメリットがあります。
ここでは代表的なメリットをいくつか紹介します。
試験本番の雰囲気を疑似体験できる
試験本番のように時間制限のある中で問題を解くため、本番さながらの緊張感をもって模試に臨むことができます。
試験本番では、そのようなプレッシャーがかかった状況の中でいかにミスなく問題を解き、高いパフォーマンスを発揮できるかが鍵になります。
最初に受ける模試では緊張したり、勉強が不十分だったりして思うような力を発揮できないかもしれません。
しかし、模試を何度も経験することで試験への「慣れ」を生み出すことができます。
模試を繰り返し受けることは、結果的に自身のパフォーマンス向上につながるのです。
自分の今の実力が分かる
模試の最も重要な特性として、現時点での自分の実力を客観的に分析できるという点があります。
模試を受ければ、どれだけ基礎学力が身についているか、苦手な科目や科目ごとの苦手分野、さらに苦手な出題形式などを詳細に把握することができます。
学校の定期テストでは出会えないような難問にも挑戦できるため、本当に自分がその範囲を理解しているかどうか、普段の勉強では気づきにくい弱点を発見できるでしょう。
また、全国の多くの受験生が受ける模試では偏差値や合否判定が提示されるため、自身の志望校に対して今どの程度の位置にいるのかを知ることもできます。
弱点克服・学習戦略の立案に役立つ
模試を受ける大きなメリットとして、自分の弱点を明確にし、今後の学習戦略を立てられることが挙げられます。
模試の結果から苦手な分野や問題傾向が浮き彫りになるため、受験生は「どの科目のどの分野を重点的に強化すべきか」を具体的に知ることができます。
例えば模試の復習を通じて間違えた問題を分析すれば、自分に不足している知識や解法の癖が見えてきます。
その分析結果をもとに勉強方法を修正したり、新たな目標を設定したりできるため、模試は今後の学習計画の指針として大いに役立ちます。
このように、単に現在の成績を知るだけでなく、次のステップにつなげられる点も医学部模試の重要なメリットです。
大学ごとの出題傾向や予想問題が分かる
各大手予備校が開催している、いわゆる「本番模試」や「オープン模試」を受ければ、自身の志望大学の出題傾向や予想問題を把握することができます。
これらの大学別模試では、本当にその大学を第一志望としている受験生が多く受験している可能性が高いため、模試の判定結果から自分の合格できる可能性が見えてきます。
模試の結果を受けて、本番までに何を勉強すれば良いのか、学力の伸ばし方や対策すべき分野を知ることができる点も大きなメリットです。
志望校に特化した模試を有効活用し、出題傾向に沿った対策を進めましょう。
時間配分の感覚が身に付く
医学部模試では本番に近い出題傾向と問題数、そしてそれに見合った時間制限・配点設定がなされています。
そのため、試験当日の時間配分の感覚を養うことができます。
模試には易しい問題から難しい問題まで幅広いレベルの設問が揃っているので、どの問題にどれだけ時間を使うべきかという判断力も鍛えられます。
本番で時間配分を誤ってしまうと、解けたはずの問題で得点を逃し合否に大きく影響する恐れがあります。
模試受験を通じて本番同様の雰囲気の中で練習を積み、このような実力以外の部分でのミスを減らすことが大切です。
医学部模試を受けることのデメリット
どんなに有用な医学部模試でも、受験にあたってはいくつかのデメリットも存在します。
メリットだけでなくデメリットも把握した上で、模試を受ける計画を立てましょう。
費用がかかる
医学部模試を受けるデメリットの一つ目は、費用がかかるということです。
一般的に模試は1回受験するごとに5,000円~7,000円程度の受験料が必要になります。
複数回受ければそれだけ費用の負担も増えるため、本当に自身にとって必要な模試を見極め、最小限の回数に絞って受験すると良いでしょう。
多くの高校では大手予備校の模試を全生徒に受験させるケースもあります。
学校での模試受験の機会を大切にし、計画的に勉強を進めれば、個人で追加の模試に申し込む回数を減らすこともできます。
判定結果によっては、一喜一憂してしまう
二つ目のデメリットは、模試の判定結果に一喜一憂してしまうリスクです。
医学部模試では通常AからEまでの合否判定が出ますが、模試の結果はあくまで現時点での実力を表す指標に過ぎません。
最初はE判定でも入試本番で合格するケースは珍しくありませんが、判定結果に振り回されて勉強に悪影響が出てしまうことがあります。
例えば、A判定が出て安心し油断してしまったり、逆にE判定で落胆して必要以上に志望校のレベルを下げてしまったりすることです。
判定結果はあくまで目安と捉え、一喜一憂するのではなく「今後自分がすべきこと」を客観的に把握する材料にしましょう。
どうしても自分では冷静に判断できない場合は、学校の先生や予備校の講師に相談し、第三者の意見をもらうのも有効な手段です。
医学部模試の効果的な受験戦略

医学部模試を最大限に活用する受験戦略を持つことが、合格に近づくために重要です。
ここでは、模試を受ける際に意識しておきたいポイントを解説します。
模試の判定を気にしすぎない
先述の通り、模試の判定はあくまで現時点での実力を示す一つのデータです。
受験直前期の模試でない限り、判定結果に神経質になる必要はありません。
高校3年生の1年間は学力が大きく伸びる期間なので、夏頃の模試でE判定だったとしても冬までにA判定まで成績を上げることも十分可能です。
E判定だからといって可能性を諦める必要はないですし、逆にA判定だからといって油断することも禁物です。
たまたま自分と相性の良い問題が出て高得点になっただけという場合もあります。
判定は目安と割り切り、今後の勉強に活かす姿勢が大切です。
志望する医学部を明確にしておく
模試を受ける際は、自分の志望する医学部を明確にしておきましょう。
判定結果そのものを気にしすぎる必要はありませんが、模試で得られるデータは志望校を絞り込む上で貴重な判断材料になります。
特に国公立大学医学部志望の場合、大学によって共通テストと二次試験(個別試験)の配点比率が異なります。
記述模試で好成績を収めたのであれば、二次試験重視の大学では合格可能性が高まるといった具合に、自分の成績傾向に合った志望校選びの参考にもなるのです。
共通テスト対策模試と二次試験対策模試の両方の結果を見比べ、必要に応じて志望校のランクを上げ下げすることも視野に入れておく必要があります。
受けっぱなしにしない
医学部模試を受ける上で最も大事なのが、模試を受けっぱなしにしないということです。
模試には質の高い良問が揃っています。
受験しただけで満足するのではなく、必ず復習を行いましょう。
復習によって自分の弱点に気づいたり、勉強法の改善点を見つけたりすることができます。
模試の問題を解く中で、どこでつまずいたのか、どう考えて解答に至ったのかを振り返り、次回以降の模試に生かしましょう。
できれば模試を受けた当日中に見直しをするのが理想的です。
時間を置かずに復習すれば、解いている最中の思考プロセスも記憶に新しいうちに確認でき、より効果的に理解を深められます。
模試を受けっぱなしにするのは非常にもったいないことなので、必ずその日のうちに復習し、模試で得た課題を次の勉強に役立ててください。
医学部模試の活用方法
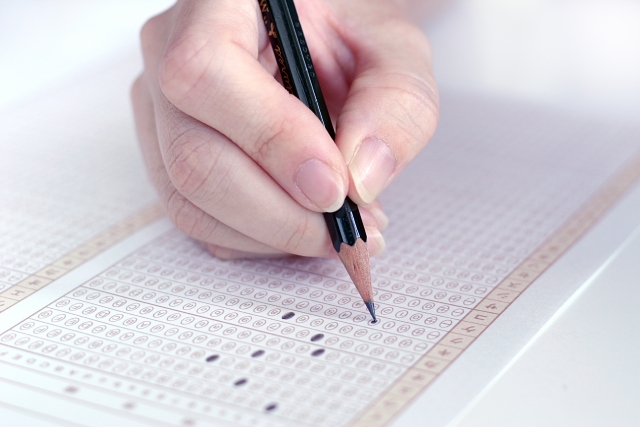
医学部模試は受けて終わりではなく、結果をどのように活用するかが重要です。
ここでは、模試の結果を合格につなげるための活用方法を紹介します。
間違い・苦手を確認、分析する
医学部模試の活用法としてまず行うべきは、自分の間違えた問題や苦手分野を確認し分析することです。
模試といっても、すべての範囲から均等に出題されるわけではありません。
様々な単元から選ばれた特定のトピックが問題として出題されるため、模試ごとに自分の得意分野と出題内容の相性が良い場合もあれば悪い場合もあります。
模試結果をじっくり見れば、自分の苦手な分野がはっきりと浮き彫りになるので、今後どの部分を重点的に勉強すべきかが明確になります。
模試の結果が返却されたら、間違ってしまった問題に一つ一つ目を通し、なぜ間違えたのかをきちんと分析してください。
特に、手応えはあったのに得点が低かった問題や、解答に自信があったのに間違えていた問題などは注意が必要です。
それらは自分の勘違いや思い込みによるミスである可能性が高いため、原因を突き止めておきましょう。
模試の成績表には科目ごとの平均点やあなたの偏差値、さらには各教科・分野別の得点分布グラフなどが示されており、自分がどの教科の何の分野を苦手としているかがひと目で分かるようになっています。
すべての設問を細かく分析するのが理想ですが、それが難しい場合でも、主要な科目について「何が得意で何が苦手か」だけは必ず把握しておきましょう。
分析結果から、今後の対策を練る
次に、模試の分析結果を踏まえて今後の学習計画や対策を練ることが何より重要です。
例えば、英語の模試で並べ替え問題の正答率が低かったと分かったなら、その分野に関わる英文法の見直しや問題演習を強化するといった具体的な対策を立てましょう。
このように、自身の模試結果を分析することで明確になった弱点に対する克服プランを組み立て、日々の勉強計画をアップデートすることが大切です。
また、模試の判定結果を志望校選びの見直しに活用し、それに応じた対策を練ることも可能です。
例えば、「数学と理科の成績は良いが英語が低調」という結果であれば、英語の強化に努めるとともに、場合によっては英語の配点が相対的に低い医学部を志望校候補に加えるといった戦略も考えられます。
逆に、共通テスト模試の得点率が高く二次試験対策模試ではやや伸び悩んだ場合には、共通テスト重視型の大学を狙う、といった選択肢も出てくるでしょう。
このように医学部模試を通じて得たデータをもとに、今後の勉強計画の修正や志望校選定の見直しを継続的に行っていきましょう。
模試選びで失敗しないためのポイント
どの医学部模試を受けるか選ぶ段階からすでに受験は始まっています。
模試選びを誤ると自分の実力を正しく把握できなかったり、余計な出費や時間の浪費につながったりしかねません。
最後に、医学部模試を選ぶ際に押さえておきたいポイントを解説します。
まず一つ目のポイントは、受験人数が多い医学部模試を選ぶことです。
模試を受ける目的の一つに、「今の自分が全国でどのくらいの位置にいるのかを知る」ことがあります。
受験者数が多ければ多いほど模試の母集団が大きくなるため、偏差値や判定の精度が上がり、より信頼性の高いデータを得ることができます。
また、参加者が多いということはそれだけ模試の知名度や信頼度が高いことを意味します。
受験料や日程の都合も考慮しつつ、多くの受験生が受けている模試を優先的に検討すると良いでしょう。
もう一つのポイントは、志望する医学部の受験生が多く受けている模試を選ぶことです。
すでに志望校が決まっている場合、その大学を目指す受験生たちがこぞって受験している模試に参加してみましょう。
同じ志望校のライバルが数多く受けていれば、その模試の成績表から自分の志望校内での立ち位置を具体的につかむことができます。
さらに、その大学の出題傾向に沿った問題が出されることも多いため、対策すべきポイントが見えてくるという利点もあります。
同じ模試で上位の成績を取ることができれば、本番での合格可能性もかなり高いと言えるでしょう。
志望校に特化した模試や、各大学の医学部志望者向けに作られた模試などがある場合は、積極的に活用してみてください。
本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾
医学部模試を受けた経験を合格につなげるには、模試後の分析と対策が欠かせません。
医学部専門予備校 京都医塾では、三者面談などで学習状況を確認し、模試の偏差値推移や科目ごとの得意・不得意を踏まえて志望校選定までサポートするため、模試結果を客観的に捉えて効果的な学習戦略を立てることが可能です。
合格まで寄り添う手厚いサポート
医学部専門予備校 京都医塾は入試直前の前日まで指導が続くことも特徴です。
入試前日や当日の試験後でも授業が行われ、実際の入試問題を使った復習や弱点補強まで徹底します。
また、各生徒に担任講師が付き学習面・精神面の相談に乗る手厚いサポート体制も強みです。
遠方での受験には講師やスタッフが現地に同行し、宿泊から試験会場への送迎までサポートを受けられるため、緊張や不安を最小限に抑えて本番を迎えることが可能です。
模試の結果に落胆してしまった時も、担任やスタッフの的確なフォローによって気持ちを素早く立て直すことができるので、最後までモチベーションを維持したまま合格を目指せます。
13名の講師がチームで徹底指導
医学部専門予備校 京都医塾の強みは、生徒一人に対して平均13名もの講師陣がチームを組み、合格に向けて一丸となって指導することです。
各教科の担当講師が情報を共有しながら指導方針を統一しているため、科目ごとの学習バランスが崩れる心配がありません。
今どの科目を重点的に強化すべきか、予習・復習の課題配分は適切かといった点も講師全員で綿密に検討した上で授業を進めます。
さらに定期的に三者面談を実施し、模試などの偏差値推移や各教科の得手・不得手まで把握して受験戦略の相談に乗るため、常に的確な軌道修正が図れる万全のサポート体制が整っています。
柔軟なオーダーメイドカリキュラム
医学部専門予備校 京都医塾では一人ひとりに最適なカリキュラムを初回に作成しますが、作りっぱなしにはしません。
入塾後は週1回の個別カウンセリングや講師チームの会議で学習進捗を細かくチェックし、日々の学習効果や模試の結果を分析した上で、必要に応じてカリキュラムを随時見直し・最適化します。
実際に学習を進める中で理想と現実のギャップが生じれば、学習効率を高めるために計画を柔軟に改善する方針です。
得意科目は上位クラスで伸ばし、苦手科目は基礎クラスから補強するといった柔軟な受講が可能で、その組み合わせは1万通り以上にも及びます。
ここに各生徒専用の個別指導を組み合わせることで弱点を徹底フォローする仕組みが整っており、模試で判明した課題も効率良く克服できるのです。
まとめ

医学部模試は、本番前に自分の実力を測り弱点を洗い出す貴重な機会です。
制限時間内で解くことで試験本番さながらの緊張感を体験でき、結果データを分析して学習計画に活かせば効率よく実力を伸ばせます。
また大学別模試で志望校の出題傾向を知り、時間配分の練習を通じて本番でのミスを減らすことも有益でしょう。
ただし判定結果に一喜一憂せず、あくまで現時点での指標と捉えて冷静に分析し、次の勉強につなげることが重要です。
それでも、「このままの勉強法で大丈夫だろうか」「弱点を克服して志望校に届くだろうか」と不安に感じる受験生は多いでしょう。
そんな時は医学部専門予備校 京都医塾に相談してみるのも一つの方法です。
医学部専門予備校 京都医塾なら、講師陣がチームで指導する体制や進捗に応じて柔軟に変えるオーダーメイドカリキュラムなど、学習サポート体制が整っています。
プロの講師陣が総合的に学力を分析して最適な戦略を提案するため、自分では気づかない弱点も克服できるでしょう。
まずは「1泊2日医学部合格診断ツアー」に参加してみませんか。
このツアーでは校舎や寮の見学、個別授業の体験に加え、専門スタッフによる学力診断と学習計画の提案を受けることができます。
プログラムは完全無料で、交通費・宿泊費も全額負担するため遠方からでも安心です。
勉強方法の悩みや成績への不安を解消し、医学部合格への道筋を明確にできる絶好のチャンスです。
夢に一歩近づくために、この機会をぜひ活用してみてください。