医学部に入学した後は、大学での6年間の課程をこなすのはもちろん、医師国家試験を受けたり研修医としてカリキュラムを修了したりと、医師になるまでには長い道のりがあります。
通過すべき試験が多いため、「医学部に入学してから医師として活動できるまで何年かかるのか」分かりづらいと感じている人も多いでしょう。
そこで今回は、医学部に入学してから医師になるまでには何年かかるのか、必要な年数とその内訳について解説していきます。
目次
医学部は何年で卒業?卒業までの道のり

医学部は経済学部や文学部など他の学部よりも修業年限が長く、卒業までに原則6年間かかります。
1年次は一般教養を学ぶことが多く、それと並行して医学の基礎知識も学んでいきます。
総合大学の場合、1年次は他学部の学生と一緒に授業を受けることも多く、幅広い分野に触れることができます。
2~4年次になると基礎医学だけでなく、臨床医学や社会医学など専門性の高い内容の講義が増えていきます。
一般的に4年次の最後に「共用試験」と呼ばれる試験を受験し、合格することで臨床実習への参加資格が得られます。
臨床実習では大学病院や総合病院の各診療科をグループでまわり、基本的な診察の知識や技術などを学びます。
臨床実習は5~6年次に行われることが多く、それまで講義や演習で学んできた知識をより実践的なものにしていきます。
そして、6年次の2月に行われる医師国家試験に合格すれば、医師国家資格を取得することが可能です。
大学によって細かなカリキュラムは異なる場合もありますが、医学部の6年間は大まかにこのような流れで進みます。
(出典:文部科学省)
医学部での留年について
医学部では、最低修業年限(6年)で卒業できない、いわゆる「ストレート卒業」でない学生が一定数います。
文部科学省の最新資料(令和5年度集計)では、ストレート卒業率(最低修業年限での卒業率)は全大学計で84.9%。区分別では国立87.1%/公立87.9%/私立81.4%という結果です。
(出典:文部科学省 各大学の医学部医学科の入学状況及び国家試験結果等)
留年の主な理由としては、必修科目の不合格や進級要件未達、共用試験・実習要件の不充足などが挙げられます。
多くの大学では在学年限(上限年数)や同一学年に在学できる年数の上限を学則・規程で明確に定めており、「同一学年は原則2年まで」「在学年限は医学部で12年」とする例が見られます。
こうした上限は大学ごとに異なるため、志望校・在籍校ごとに確認しておくと安心です。
医師になるまでの試験

医学部合格後、医師になるまではいくつかの重要な試験をパスする必要があります。
主なものは卒業試験、医師国家試験、共用試験(CBT・OSCE)です。
ここではこれらの試験について順に見ていきましょう。
卒業試験
医師国家試験を受けるにはまず医学部を卒業しなければなりません。
そして卒業するための関門として各大学で課されるのが卒業試験です。
卒業試験を突破できない学生は留年となり、次のステップに進むことができません。
医学部の卒業試験は科目数が非常に多いのが特徴で、少なくとも10科目、多い大学では30科目近くもの筆記・実技試験が課されることもあります。
通常、卒業試験は毎年9~12月頃に実施されますが、概ね1~3か月間にも及ぶ長いスパンで行われます。
普段以上に勉強に追われる日々が続き、学生の負担は非常に大きくなります。
さらに、多くの学生は医師国家試験の対策も並行して開始する時期ですから、卒業試験期間中の生活は激変し、過酷なものになるでしょう。
このように、他学部では卒業論文や必要単位の修得だけで卒業できますが、医学部では卒業までに非常に高い壁を乗り越える必要があるのです。
学生によってはこの試験でつまずき、何年も卒業できないケースもあります。
過去問や対策資料を活用し、必ず卒業試験を突破できるよう早めに準備しておきましょう。
医師国家試験
卒業試験に合格した後に待っているのが医師国家試験です。
この試験は、医学部で6年間学んだ成果を確認し、医師になるための知識・技能の習熟度を判定する国家試験です。
医学部の卒業試験と同様、この試験に合格しなければ次の段階へ進めません。
医師国家試験は毎年2月頃に2日間にわたって実施され、医学部の卒業試験に合格した人(あるいは合格見込みの人)に受験資格が与えられます。
出題科目は、臨床現場を想定した問題はもちろん、循環器・呼吸器・感染症・整形外科など多岐にわたります。
マイナーな分野からも出題されることが多く、放射線に関する問題や麻酔に関する問題など、幅広いカテゴリーから出題されます。
この他、医師の法的義務や医療関連の法律問題も出題されるため、相当量の知識を蓄えておく必要があるでしょう。
共用試験
共用試験とは、臨床実習前に行われる実力判定試験の一種で、CBT(Computer Based Testing)とOSCE(Objective Structured Clinical Examination)という2種類の試験を指します。
共用試験に不合格となった学生は臨床実習に進めないだけでなく、状況によっては留年となってしまいます。
OSCE
OSCE(オスキー)は、医学部の学生が臨床実習に参加するにあたり、十分な臨床能力を備えているかどうかを判定するための試験です。
この試験では知識よりも基本的な診察技能や態度など実践的な能力が評価されます。
実施時期は大学によって異なり、早い大学では3年生に、遅い大学では4年生の時に行われます。
OSCEの試験範囲は全国共通で、以下の6項目について模擬患者に対する実技試験が行われます。
- 医療面接
- 胸部診察、全身状態の観察とバイタルサイン測定
- 腹部診察
- 神経診察
- 頭頸部診察
- 基本的臨床手技・救急対応
各課題には患者の設定や診察項目の指示が用意されており、学生は模擬患者さんを相手に制限時間内で課題に取り組みます。
科目によっては診察項目が多いため、制限時間をオーバーしないよう日頃から十分に練習を積んでおきましょう。
CBT
CBTはコンピューターを使用して行われる筆記試験で、学生の医学的知識や技能、問題解決能力を判定する目的で実施されます。
学生一人ひとりが専用のPC端末で画面上の問題に解答していく形式で、出題される問題は学生ごとにランダムに異なるのが特徴です。
医学部入学から医師になるまで何年かかる?

医学部を卒業してから医師として独り立ちするまでには、トータルで何年くらいかかるのでしょうか。
自分のキャリアプランを考える上でも、医師になるまでに必要な年数をしっかり把握しておきたいところです。
医学部入学から医師国家試験合格までは最短で6年ですが、医師として働くためにはその後の研修期間が必要です。
基本的には医学部在学6年+研修医2年の計8年程度で一人前の医師として働き始めることになります。
さらに専門医資格を取得する場合は後述する後期研修(専門研修)に3~5年かかるため、医学部入学から専門医として独立するまで合計10年以上かかることもあります。
もし浪人や留年を経験した場合や、大学卒業後にすぐ研修ではなく大学院に進学した場合には、医師になる年齢がさらに上がり、必要な年数もその分延びる点に注意しましょう。
※なお、上記は高校卒業後すぐ医学部に入りストレートに進んだ場合の年数です。
社会人を経てから医学部に再入学するケースや、医学部進学前に他学部で学位を取得しているケースでは、医師になるまでの年数・年齢は人によって大きく異なります。
医師国家試験と臨床研修について
医学部の課程を修了し国家試験に合格すると、晴れて医師免許を取得できます。
しかし、医師免許を取得しただけでは、すぐに自由に診療行為ができるわけではありません。
日本では、医師免許取得後に一定期間の臨床研修を積むことが法律で義務付けられており、これを修了して初めて一人の医師として独立して診療に当たることが認められます。
ここでは医師国家試験合格後に待っている初期臨床研修および後期臨床研修について解説します。
最低2年間の研修医期間は必須
医師国家試験に合格して医師免許を取得した後は、原則として2年間の臨床研修(研修医期間)が義務付けられています。
この初期研修を修了しなければ、医師免許を持っていても自由に診療行為を行うことはできません。
一般的に、初期臨床研修修了を経て保険医登録など勤務先での手続きを行い、公的医療保険下で診療に従事できるようになります。
ただし、基礎医学の研究などに進み診療行為に従事する予定がない場合は、例外的に研修を受けなくても差し支えないとされています。
将来的にも臨床の現場に出ず研究者として歩む場合には、研修医の道を選ばないケースもあり得ます。
初期臨床研修の内容
初期臨床研修は大学病院、または厚生労働大臣の指定する臨床研修病院で2年間にわたり実施されます。
一般的な診療に対処できるスキルを身に付けることが目的で、研修プログラム上は必修科目として「地域医療」「救急」「内科」「外科」「産婦人科」「小児科」「精神科」の7科目が定められています。
3~5年程度の後期臨床研修で専門性を高める
2年間の初期臨床研修を修了した後は、3~5年程度の後期臨床研修(専門研修)が行われます。
研修の目的は、自分が希望する診療科で専門的な知識や技能をさらに高めることにあります。
後期臨床研修への参加は法律上の義務ではありませんが、専門医資格の取得を目指す医師の多くがこの研修にも進みます。
後期臨床研修の内容
後期臨床研修では、各病院が定める専攻医向けの専門研修プログラムに沿って研修を行うのが一般的です。
例えば、急性期の大病院で研修を受ければ多くの症例を経験できますし、複数の診療科を学びたい人にはローテーションで様々な科を回らせてくれる病院もあります。
後期臨床研修を修了し所定の認定試験に合格すると、専門医を名乗ることが可能です。
専門医資格を取得すれば、報酬のアップや医師としての地位向上にもつながります。
医師免許を取得した後は、日々の診療を通じて長年にわたり患者と向き合うことになりますが、知識とスキルをさらに磨くためにも後期臨床研修への参加はぜひ検討したいところです。
編入の場合は例外もあり
「学士編入」という制度をご存知でしょうか。
学士編入とは、大学在学者や大卒者が他大学の2年次または3年次に編入できる制度です。
医学部は通常6年かけて卒業しますが、この学士編入制度を利用することで在学期間を短縮できるケースがあります。
例えば、他学部で学士号を取得後に医学部へ編入した場合、編入先の年次にもよりますが4~5年程度で卒業できる場合もあります。
社会人や他分野出身者に門戸を開く学士編入制度は競争率が高く難易度も上がりますが、うまく活用すれば医師免許取得までの年数を短縮することも可能です。
医学部卒業後の進路

何年もの歳月を費やし医学部を卒業し、初期臨床研修まで修了した後は、医師それぞれが自分の希望するキャリアに進むことになります。
多くの人はそのまま病院に勤務したり、あるいは開業医として自分のクリニックを構えたりと、様々な進路を選択します。
ここからは、医学部卒業後の代表的な進路について見ていきましょう。
病院勤務
医学部生の進路として最も一般的なのが病院勤務です。
研修医として働いた病院にそのまま就職する人、自分の専門分野をより伸ばせる病院に移る人など様々ですが、いずれにせよ大きな病院で多数の患者や症例に携わることでスキルを磨く道です。
専門医取得までの症例を積む場としても病院勤務は適しています。
自分に合った勤務先を選び、臨床経験を積んでいきましょう。
開業医
経済的な余裕や十分な経験がある人は、開業医の道を進むこともあります。
自らクリニックを開業すれば経営者としての責任も伴いますが、病院勤務と比べてスケジュールの自由度が高く、自分のペースで診療できるのが特徴です。
地域に根差した医療を提供し、患者と長期的な信頼関係を築ける点も開業医のやりがいと言えるでしょう。
大学病院
医学部入試で地域枠推薦で入学した場合、そのまま指定された都道府県の大学病院に一定期間勤務するケースがあります。
自治体にもよりますが、卒業後9年前後は当該大学病院などで勤務する義務が課されることが多いようです。
学費免除などの恩恵と引き換えに地域医療に貢献する制度ですが、都道府県の同意なく地域枠を離脱した場合には、従事義務のかかっている地域以外で専門医を取得できないといった制約や、離脱者を採用した病院へのペナルティが課されることもあるようです。
地域医療枠で医学部に入学した場合、卒業後のキャリアが一定程度制限される点には留意が必要です。
医者以外の道
医学部卒業後の進路は、必ずしも医師としての勤務だけではありません。
人によっては医師免許を取得した後に医師以外の職業に就くケースもあります。
例えば、研究者として大学や企業で医学研究に従事する人もいますし、義肢や医療機器を開発する医工学の分野に進む人もいます。
また、医療と情報技術を結び付ける医学情報学の分野で活躍したり、企業に就職して製薬や医療系ベンチャーの経営に携わる人もいるでしょう。
中には医師免許を持ちながら起業し、成功を収めている人もいます。
このように、医学部を卒業した後のキャリアは非常に多様であり、「医師」という肩書きにとらわれない道も開かれています。
医師免許を持っていること自体が大きな強みになりますので、それを活かして自分の興味のある分野で才能を発揮する卒業生も少なくありません。
将来的にどのような進路を選ぶにせよ、医学部で培った知識や論理的思考力は必ず役立つはずです。
本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾
医学部入試は極めて競争率が高く、生半可な努力では合格は困難です。
医師への道の第一歩となる医学部合格を勝ち取るには、万全の受験対策が必要でしょう。
しかし、一人ですべてをこなすのは簡単ではありません。
そこで医学部専門予備校 京都医塾では、独自の指導体制と充実したサポートで皆さんの夢を強力にバックアップします。
13名の講師チームによる徹底指導
医学部専門予備校 京都医塾では、各科目のエキスパートが指導を担当します。
生徒一人に対し平均13名の講師陣がチームとなり、情報を共有して指導方針を統一しています。
科目間のバランスをとりながら弱点を徹底補強し、全科目の底上げができることも特徴です。
1対1の個別授業とレベル別の少人数授業を組み合わせた指導により、一人ひとりの現状と目標に応じて最適な学習プランを実行します。
勉強に集中できる快適な環境&オーダーメイドカリキュラム
医学部専門予備校 京都医塾では勉強に集中できる快適な環境も整えています。
一人ひとり自分だけの個人ブースを完備し、朝から夜まで同じ席で授業・自習に集中できます。
校舎から徒歩5分圏内には家具付きの専用学寮を用意しており、遠方からの入塾でも安心して受験勉強に専念できる環境です。
現状の学力・習熟度を分析してオーダーメイドの個人カリキュラムを作成し、自分専用の学習計画のもとで効率的に弱点を克服し合格力を高めていきます。
合格まで寄り添う手厚いサポート&高い合格実績
医学部専門予備校 京都医塾は合格するまで徹底的に寄り添うサポートをお約束します。
出願校の戦略立案から願書作成指導、直前期の特訓はもちろん、入試当日も講師やスタッフが同行して100%の力を発揮できるよう支えます。
こうした手厚いサポートにより毎年圧倒的な合格実績を誇り、2025年度には一次試験合格率79%・最終合格率61%を達成しました。
まとめ
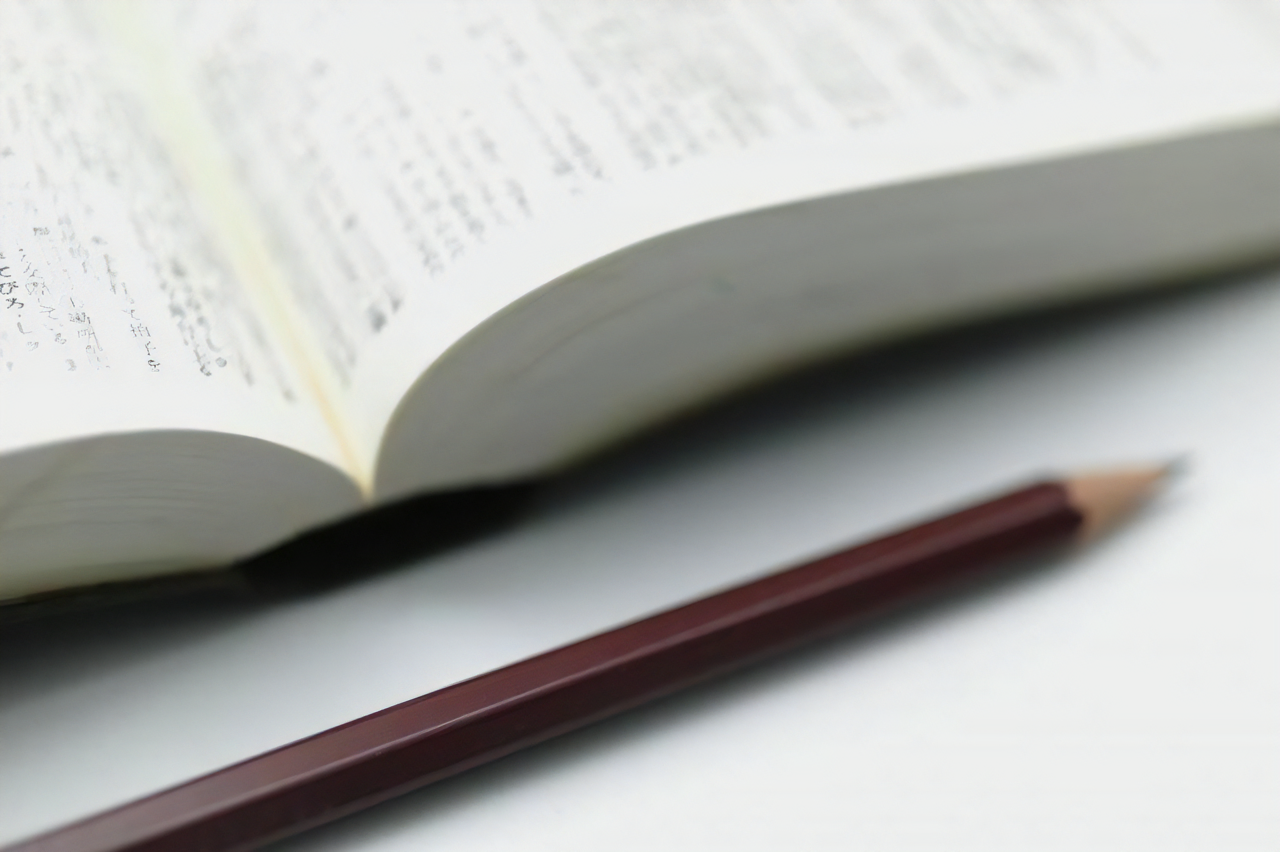
この記事では、医師になるまでの年数として、医学部6年制+初期研修2年(+専門研修3〜5年)という全体像を整理しました。
学年ごとにやるべきことを逆算し、科目間の配分と生活リズムを崩さずに走り切れる設計が勝負を分けます。
一方で、独学では進度や出願戦略の判断、直前期の優先順位づけで迷いやすく、途中で失速する不安も残りがちです。
医学部専門予備校 京都医塾なら、講師チームが専用カリキュラムと学習環境で合格までの学習をサポートします。
まずは現状と合格までの距離を見える化し、最短ルートを設計しませんか。
1泊2日医学部合格診断ツアーでは、学力診断と年間設計の提案、校舎・個人ブース・学寮の体験まで含めて確認でき、交通費・宿泊費は京都医塾が負担します。
迷っている時間も受験の一部です。今の位置を把握し、次の一歩を具体化するところから始めましょう。


