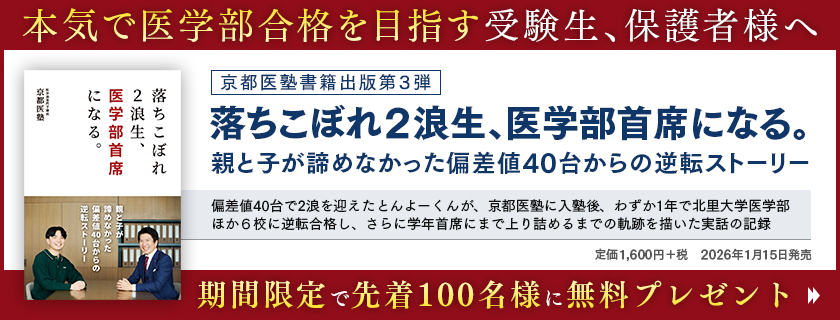医学部進学を考えるにあたって、どの医学部を選ぶべきか迷う人は多いでしょう。
医学部の選び方で失敗しないためには、重要なポイントをあらかじめ把握しておくことが大切です。
そこで本記事では、医学部を志望する受験生に向けて国公立大学と私立大学を比較して医学部選びのポイントを詳しく解説します。
目次
【医学部選び】まずは国公立大学と私立大学を比較する

医学部を選ぶうえで最初に決めるべきなのは、国公立大学医学部を目指すか私立大学医学部を目指すかという方向性です。
国公立大学と私立大学では学費や受験科目、難易度、所在地による通学環境まで、あらゆる点で大きく異なります。まずは主な違いを表で整理しました。
| 項目 | 国公立大学医学部 | 私立大学医学部 |
| 学費(6年間) | 約350万円~400万円 | 平均約3,200万円(1,800万~4,700万円) |
| 受験科目 | 共通テスト5教科7科目+二次試験 | 独自試験(英・数・理科2科目が基本) |
| メリット | 学費が安い、全国から志願者 | 併願しやすい、早期専門教育も可 |
| 注意点 | 科目数が多く対策範囲広い | 学費負担大、1科目の失点が致命的 |
この表で全体像を把握したうえで、それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。
学費
国公立大学医学部と私立大学医学部では、6年間でかかる学費に大きな開きがあります。
国公立大学医学部の場合、大学によって若干の差はあるものの6年間合計で約350万円前後(授業料年間53万円+入学金約28万円)とされます。
一方、私立大学医学部では6年間の学費総額が1,800万円台~4,700万円と大学によって差が大きく、平均は約3,200万円にも上ります。
最も高額な私立大学医学部では約4,700万円、反対に学費が安い私立大学医学部では1,800万円台というケースもあります。
(出典:文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移、朝日新聞デジタル THINK CAMPUS)
このように国公立と私立で桁違いの学費負担となるため、私立大学医学部を志望校に選ぶ際には、その学費を支払えるかどうかが大きな選択基準となるでしょう。
受験科目
国公立大学医学部では、大学入学共通テストにおいて5教科7科目もの広範囲な科目を受験する必要があります。
共通テストでは大学・年度で変動するものの8〜9割前後という非常に高い得点率が必要となり、そのうえで各大学ごとの二次試験に進むのが一般的です。
国公立医学部を目指す場合は、全科目をバランス良く学習し、高得点を狙える学力が必要になります。
二次試験の科目や配点比率は大学ごとに異なるため、自分が得点源にしやすい科目構成になっている大学を選ぶことで有利に戦うことも可能です。
一方、私立大学医学部では基本的に共通テストを課さず、各大学が独自に筆記試験(英語・数学・理科など)や面接・小論文を実施します。
私立大学医学部の受験科目数は大学によってさまざまで、英語・数学・理科2科目が標準的ですが、中には理科1科目で受験できる大学や国語を選択科目に含められる大学もあります。
大学ごとの出題傾向(スピード重視か記述重視か等)も異なるため、自分の得意科目や解答スタイルに合った傾向の大学を選ぶことがポイントです。
難易度
一般的に国公立大学医学部の方が難易度が高い傾向にあります。
学費の安さから志望者が集中しやすいこと、さらに共通テストを含め多教科の対策が必要になることが難易度を押し上げる要因です。
近年は私立大学医学部の人気も急上昇しており、偏差値上では国公立医学部と遜色ないレベルになっています。
私立医学部最難関の慶應義塾大学医学部は偏差値72.5程度とされ、国公立大学のトップクラスに匹敵します。
また、私立大学医学部は受験科目が絞られている分、1科目の失点が合否を左右するシビアさもあります。
私立大学医学部の入試倍率は大学や方式によって大きく異なりますが、一般入試では二桁倍率になることも珍しくありません。
入試方式や年度によって倍率は変動するため、最新の志願者数・倍率は各大学の公式発表や大手予備校の入試結果速報で必ず確認しましょう。
このように私立大学医学部だから簡単ということは決してなく、油断は禁物です。
むしろ私立医学部の場合は併願受験で受験チャンスを増やせる利点を活かしつつ、志望校の試験科目に照準を絞った対策で合格を勝ち取る戦略が求められるでしょう。
(出典:河合塾Kei-Net、プレジデントオンライン)
大学ごとの特色
大学ごとの特色や強みにも目を向けることが、後悔しない医学部選びには欠かせません。
同じ医学部でも各大学が力を入れている分野や教育方針は異なり、そこで得られる経験や卒業後の進路にも差が出ます。
例えば、研究志向の強い大学では最先端の研究設備や豊富な研究費が整い、医学部在学中から高度な研究に携われる機会があります。
一方で地域医療に重点を置く大学では、地元の医療機関で実習や研修を積めるカリキュラムがあり、将来地域医療に貢献できる医師の育成に力を入れています。
また、大学によっては著名な専門医が教授として在籍し、その分野で卓越した教育・臨床指導が受けられることもあります。
自分が将来目指す医師像に近づくために、有名な教授陣や得意分野で知られる大学を選ぶのも一つの方法です。
各大学医学部のホームページやパンフレット、説明会などで特色を調べ、「その大学で6年間学ぶメリットは何か」を考えてみましょう。
大学の所在地
医学部選びでは大学の所在地も重要なポイントです。
自宅から通学可能な範囲にある医学部であれば、経済的負担や生活面の負担を軽減できます。
ただし、通える範囲に医学部が少ない場合、選択肢が限られてしまいます。
一人暮らしを前提に遠方の大学も検討すれば受験校の幅は広がりますが、その場合は家賃や光熱費など生活費を含めた経済面の計画が必要です。
6年間という長期間の学生生活になりますから、地元を離れる不安や負担も踏まえ、自分と家族にとって無理のない選択を心がけましょう。
国公立大学医学部の選び方
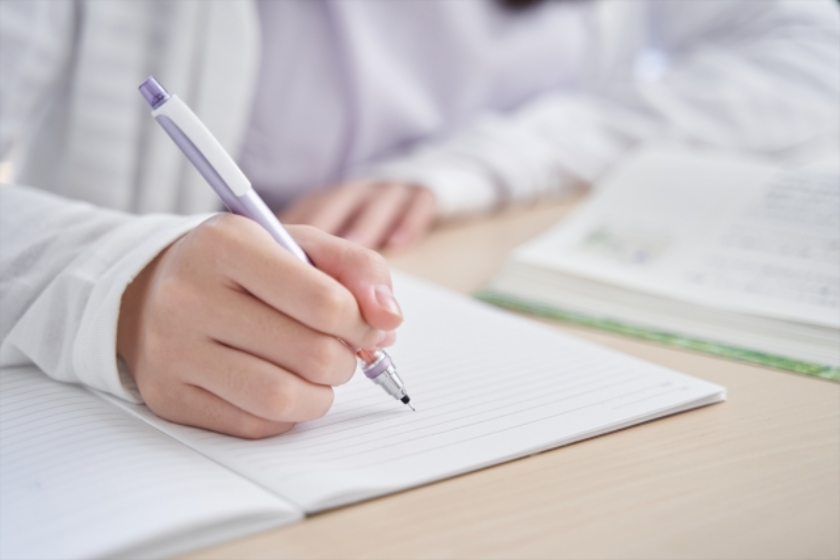
ここからは国公立大学医学部を具体的に選ぶ際のポイントを解説します。
国公立大学医学部を目指す受験生は、自身の学力や適性と照らし合わせて志望校を選ぶことが大切です。
二次試験の科目
国公立大学医学部の場合、合否は「共通テスト+二次試験」の総合点で決まります。
そのため、自分が総得点を最大化できる大学を選ぶことが合格への近道です。
特に各国公立大学医学部の二次試験は、大学ごとに実施科目数や配点比率が異なります。
例えば二次試験で英語・数学・理科2科目すべてを課す大学もあれば、英語と数学の2科目だけで実施する大学もあります。
自分が得意な科目に重きを置いている大学や、配点バランスが自分向きの大学を選ぶことで、限られた学習時間で効率よく合格点に達しやすくなるでしょう。
また、各大学の過去問を分析して出題傾向を把握し、問題との相性も考慮して志望校を決定することが重要です。
校風が合うかどうか
医学部では6年間という長期間を過ごすため、大学ごとの「校風」や雰囲気も重要です。
同じ国公立大学医学部でも、真面目に勉強に打ち込む学生が多い堅実な校風の大学もあれば、比較的自由で自主性を尊重する校風の大学もあります。
校風の違いは学習環境や学生生活に大きく影響するため、事前にリサーチしておきましょう。
情報収集の手段としては、実際にその大学に通う先輩や在学生から話を聞くのがおすすめです。
難しい場合は、インターネット上の学生口コミサイトや受験情報誌の特集記事などから雰囲気を掴むこともできます。
ただしネット上の口コミは主観的な情報も多いため、話半分に参考にする程度にとどめましょう。
医学部専門予備校には各大学の内部事情に詳しいスタッフがいる場合もあるので、そうしたプロに相談してみるのも一つの方法です。
いずれにしても、自分が居心地良く勉強に励める環境かという視点で大学を見極めることが大切です。
なりたい医師像に近づけるか
将来、自分が「どのような医師になりたいか」という明確なイメージがある場合、そのビジョンに近づける大学を選ぶことも重要です。
同じ医学部でも各大学のカリキュラムや得意分野が異なると、卒業後の進路や臨床経験にも違いが出てきます。
例えば「将来は研究者肌の医師になりたい」と考えているなら、在学中に研究に没頭できる環境が整った大学を選ぶのが賢明です。
大学によっては研究医を志す学生に奨学金を給付したり特別プログラムを提供しているところもあります。
逆に「地域医療に貢献したい」場合は、地域医療実習が充実していたり、自治体と連携した地域医療枠を持つ大学に進学すると在学中から地域医療の現場を経験できます。
大学が力を入れている分野を調べ、自分の理想とする医師像にフィットする大学を志望校候補にするとよいでしょう。
大学案内パンフレットや公式サイトには各大学の教育理念や特色が掲載されています。
それらを読み比べて、自分の目標に合ったメッセージを発信している大学かどうか確認するのもおすすめです。
私立大学医学部の選び方
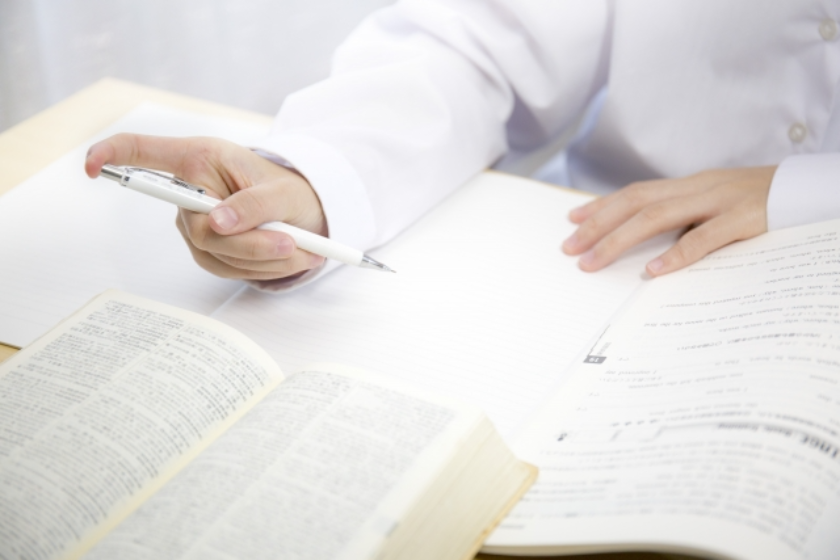
ここでは、私立医学部志望校選びのポイントを絞って解説します。
学費支援制度
私立大学医学部を選ぶ際には、まず6年間の学費を支払えるかどうかをクリアすることが大前提です。
私立大学医学部は6年間で平均約3,200万円と大きな経済的負担がありますが、近年はさまざまな学費支援制度が整ってきています。代表的なものは以下の通りです。
- 修学資金貸与制度(例:自治医科大学):入学者全員に学費相当額を貸与。卒業後に一定期間、指定病院で勤務すれば返還免除。将来の勤務地が限定されてもよい場合、大きな負担軽減となる。
- 地域枠入試+自治体奨学金:各都道府県と連携し、一定期間地元勤務を条件に奨学金を貸与。勤務を終えれば返済免除となる。
- 病院独自の奨学金制度:特定病院での勤務を条件に学費を貸与・支援する制度。将来の就職先確保にもつながる。
これらの制度を利用すれば、私立医学部でも実質的に学費を大幅に軽減できる可能性があります。
進学を検討する際は、各大学や自治体の情報を確認し、家族と十分に話し合って検討しましょう。
出題傾向や受験科目
私立大学医学部ごとに入試問題の出題傾向や科目構成が異なるため、志望校選びではまず各大学の入試傾向を確認しましょう。
例えば、標準的な問題をスピーディーに解く傾向なのか、あるいは論述や記述問題が多いのかなど、大学によって試験の特徴が分かれます。
多くの私立大学医学部では一般入試の受験科目は英語・数学・理科2科目(物理・化学・生物から選択)ですが、一部には理科1科目で受験可能な大学や国語を科目に含む大学もあります。
各大学の入試科目や問題傾向を把握し、自分の得意分野が活かせる大学や、逆に苦手科目を避けられる大学を選ぶことが合格可能性を高めるポイントです。
過去問演習や入試分析資料を活用して、志望校ごとの傾向を掴んでおきましょう。
カリキュラムや校風
私立大学医学部ではカリキュラムや校風にも各校で違いがあります。
6年間を充実して過ごすために、入学前に大学の教育内容や学生生活の雰囲気を把握しておくことが大切です。
大学案内パンフレットや公式ホームページには、各私立医学部の教育課程や年間スケジュール、プログラムなどが詳しく紹介されています。
例えば、一部の私立大学医学部では1年次から医療現場に触れる早期体験実習や専門科目の先取り学習を行っており、医学教育を早い段階から開始するカリキュラムを採用しています。
一方、多くの国公立大学では1~2年次に一般教養科目を中心としたカリキュラムが組まれる傾向がありますが、これは医学以外の幅広い知見を養う目的もあります。
したがって「できるだけ早く医学の勉強を始めたい」という人にとっては、初年次から専門教育が手厚い私立大学医学部のカリキュラムは魅力的かもしれません。
逆に「大学では幅広い教養も身につけたい」と考える人は、初年次に教養課程を含む大学の方がフィットするでしょう。
校風についても、私立大学医学部ごとに色があります。
大学によっては学年や学生間のつながりを深める伝統行事が盛んであったり、部活動や国際交流に力を入れているところもあります。
入試スケジュール
私立大学医学部は入試日程が大学ごとに異なるため、複数校を併願する場合は試験日程が重複しないよう注意が必要です。
大学によっては試験日が集中し競合する場合があり、日程次第で志願者数が増減します。
日程が重ならない大学同士であれば複数受験が可能となり、その分合格のチャンスも増やすことができます。
学費や偏差値の面から受験候補を絞り込んだ後は、各大学の入試日程カレンダーを確認し、効率よく併願計画を立てましょう。
例えば、1月下旬から2月上旬にかけて首都圏の私立大学医学部入試が集中しますが、その中でも日程にゆとりがある大学や、逆に人気校と試験日が重ならず穴場となっている大学を狙うといった戦略も取れます。
このように入試スケジュールの組み方次第で受験機会を最大化できるのが私立大学医学部受験の強みです。
願書を提出する前に各大学の試験日を整理し、自分にとって最良の受験スケジュールを作成しましょう。
合格可能性を高める出願戦略!最新入試情報の活用方法

医学部入試では年度ごとに試験科目や募集人数、出題形式などに変更が加えられることが珍しくありません。
そのため各大学の最新入試情報を入手することは、合格可能性を左右する重要ポイントになります。
志望校の過去数年の入試概要を比較し、どのような変更があったのか、今年度は何に注意すべきかを把握しましょう。
最新入試情報を入手できたら、現在の自分の成績・偏差値と照らし合わせて合格の可能性が高い大学を洗い出します。
共通テストの得点見込みや模試の成績データを基に、安全校・適正校・挑戦校のバランスを考慮して出願先を決定しましょう。
また、直前期までに各大学の予想ボーダーラインや競争倍率の動向もチェックし、必要に応じて志望順の入れ替えや出願校追加を検討します。
さらに、最新情報を活用して志望校ごとの対策をより的確に行うことも大切です。
例えば「今年から○○大学で英語の出題形式が変わった」「△△大学が面接重視の選考になった」等の情報があれば、それに合わせて重点的な対策をとる必要があります。
このように常にアップデートされる入試情報をキャッチし戦略に反映させることで、合格の可能性を最大限に高めることができるでしょう。
最後に、医学部受験は情報戦の側面も強いため、自力で情報収集が難しい場合は信頼できる予備校や情報媒体を活用するのも一つの手です。
入試情報の分析や出願戦略の立案についてプロのアドバイスを得ることで、自分では気付かない有利な受験プランが見えてくるかもしれません。
本気で医学部合格を目指すなら京都医塾

志望校の選び方のポイントが分かったら、次は合格に向けた本格的な準備です。
医学部専門予備校 京都医塾なら、医学部受験に特化した万全のサポートが受けられます。
大学選びから試験当日まで寄り添う
医学部受験は情報戦と言われます。
医学部専門予備校 京都医塾では、私立大学医学部入試の複数日程にも対応できるよう、出願校のスケジューリングから願書作成まで戦略的にサポートします。
生徒・保護者の希望を踏まえ、各教科の講師陣が過去問分析による相性まで考慮して出願プランを立案し、最終的な志望校決定を後押しします。
出願時期には担任が各生徒の願書提出状況を日々管理し、小論文・面接の専門講師が志望理由書の記入まで丁寧に指導します。
遠方での入試には、普段指導している講師・スタッフが同行し、宿泊先でも起床から試験会場への送迎まできめ細かくサポートします。
入試直前期も試験当日まで指導が続くため、最後まで学力を伸ばし切って合格を勝ち取る受験生が続出しています。
13名の講師チームによる万全サポート
医学部専門予備校 京都医塾の特徴の一つが、生徒一人を13名のプロ講師陣がチームで指導する体制です。
講師同士で情報を共有し指導方針を統一することで、どの科目に重点を置くべきかを常に最適に判断し、全科目をバランス良く伸ばせます。
この万全なチーム体制によって学習時間配分の偏りを防ぎ、効率良く総合点を高めることができます。
さらに開校時間中は校舎に講師が常駐しているため、授業の合間や放課後でも疑問点をすぐに質問・解決できる環境が整っています。
完全オーダーメイドの個別カリキュラム
一人ひとりの学力や弱点に合わせて、完全オーダーメイドの個別カリキュラムを作成します。
医学部専門予備校 京都医塾では英語は11段階、化学は12段階と各科目で習熟度別に細かくクラス分けを実施し、得意科目は上位クラス・苦手科目は下位クラスといった柔軟なクラス編成が可能です。
その組み合わせは主要4科目だけでも1万通り以上にも及び、個人指導と組み合わせることで生徒ごとに最適な学習プランを組むことができます。
また、生徒一人に講師担任+教務スタッフ2名=計3名が担当につき、週1回のカウンセリングで学習状況や生活リズムまで細かく把握し、必要に応じて柔軟に調整しています。
まとめ

この記事では、国公立大学医学部と私立大学医学部の違いをはじめ、学費・受験科目・難易度・大学の特色など、医学部選びの重要ポイントを詳しく解説しました。
医学部選びで失敗しないためには多角的に情報収集を行い、自分の学力や将来の目標に照らして最適な大学を選ぶことが大切です。
とはいえ、いざ志望校を決めても「本当に合格できるだろうか」「他に良い選択肢はないだろうか」と不安になる方も多いでしょう。
そんなときは医学部受験のプロに頼るのも一つの手です。
高い合格実績を誇る医学部専門予備校 京都医塾なら、最新の入試動向を踏まえた受験戦略の立案から日々の学習管理、志望校の出願サポートまで、経験豊富なスタッフが徹底的に寄り添います。
医学部専門予備校 京都医塾では2025年度に医学部医学科最終合格率61%を達成しており、多くの生徒が夢を実現しています。
まずは、医学部専門予備校 京都医塾が提供する「1泊2日医学部合格診断ツアー」に参加して、学習面の課題や合格までに必要な対策を明確にしてみませんか。
遠方でも交通費・宿泊費は無料ですので、お気軽にお申し込みいただけます。
この機会に参加して、医学部合格への第一歩を踏み出しましょう。