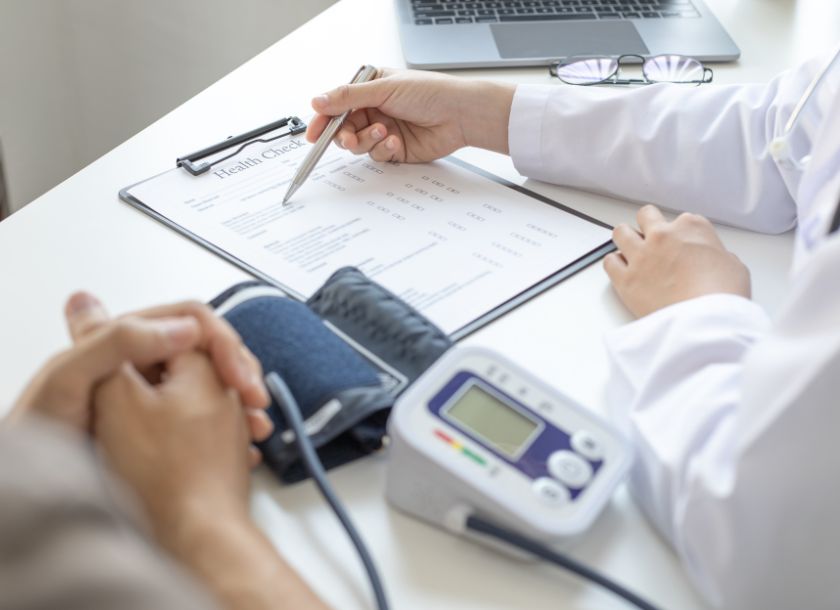医師は「人の命を守る尊い仕事」という華やかなイメージの一方で、長時間労働、訴訟リスク、高額な学費など厳しい現実にも直面します。
今回の記事では、勤務環境・精神的プレッシャー・養成コストという3大デメリットをデータで整理しつつ、社会的信頼ややりがいなどのメリットも併記。
医学部受験を検討する高校生から再受験生、保護者までが進路判断に役立てられるよう、統計と具体例を交えてわかりやすく解説します。
目次
医師という職業の現状と特徴

医師のキャリアは「勤務医」「開業医」「研究医」の3系統に大別され、勤務先や求められる役割が大きく異なります。
患者と向き合う臨床現場にとどまらず、研究や行政・企業の医務室など活躍の場が広い点が特徴です。
医師の主な働き方(勤務医・開業医・研究医)
| 勤務医 | 病院に雇用され、外来・病棟・当直業務を行う。夜間対応や急患が多く、労働時間が長くなりやすい。 |
| 開業医 | クリニックの経営者として診療とマネジメントを両立。地域のかかりつけ医として軽症患者を中心に診る。 |
| 研究医 | 大学や研究機関で基礎・臨床研究を推進。論文発表や新規治療法開発に携わる。 |
それぞれの道で求められるスキルや働き方が異なるため、早い段階で適性を見極めることが大切です。
今後求められるスキルとキャリア多様化
AI 診断支援や多職種連携の拡大により、医師には以下が欠かせません。
- テクノロジーを活用する力
- チームをまとめるコミュニケーション力
- 生涯学習への意欲
臨床以外にも産業医・企業のメディカルドクター・国際医療協力など選択肢が増えており、個々のライフプランに合わせたキャリア設計が可能です。
医者のデメリット1:長時間労働などの勤務環境
医師のデメリットと言われる労働時間についてまとめていきます。
勤務医の労働時間実態
夜間・休日のオンコールが続くと生活リズムが乱れ、疲労から医療事故につながるリスクも指摘されています。
厚生労働省の調査では、男性医師41%・女性医師28%が週60時間以上働いていると報告されています。
(出典:厚生労働省|令和元年 医師の勤務実態調査)
ワークライフバランスへの影響と対策
医師は当直明けに通常勤務へ入ることも多く、睡眠不足や家庭時間の欠如が慢性化しがちです。
こうした負荷を和らげるため、現場では以下の3つの施策が進んでいます。
| タスクシフト | 医師事務作業補助者(クラーク)が診断書や紹介状などの文書業務を肩代わりし、医師は診療に専念できる体制を整備。 |
| 交代制シフトの導入 | 夜勤・当直の連続時間を制限し、一定時間で次の医師へ引き継ぐ仕組みを入れることで、長時間連続勤務を防止。 |
| 勤務先・診療科の選択 | 当直回数が少ない慢性期病院や、手術件数の少ない診療科を選ぶことで、個々のライフステージに合わせた働き方を実現。 |
2024年4月に施行された「医師の働き方改革」では、時間外労働の年間上限(原則960時間)と連続勤務時間の制限が法律で定められ、労働環境は段階的に改善へ向かっています。
(出典:厚生労働省|医師の働き方改革)
医者のデメリット2:重い責任と精神的ストレス

医師は診療ミスが生命に直結し、訴訟リスクとも背中合わせです。
プレッシャーが大きい分、メンタル面の負担も避けられません。
医療ミス・訴訟リスクがもたらすプレッシャー
医者は、その責任の重さから、医療ミスや訴訟リスクに直結するため、それがプレッシャーやデメリットと感じてしまう方も多いでしょう。
2023年(令和5年)の医療訴訟新受件数は610件となっています。
(参考:医事関係訴訟事件の処理状況及び平均審理期間(平成11年~令和5年))
クレーム対応とバーンアウト(燃え尽き症候群)
患者や家族の苦情対応は診療時間外にも及び、累積ストレスがバーンアウトを招くことがあります。
主な予防策は以下の通りです。
- 同僚・上司への早期相談
- 専門家のメンタルカウンセリング
- 診療科・勤務形態の変更
精神的健康を保つには、無理をしすぎない働き方が重要です。
医者のデメリット3:長い養成期間と経済的ハードル
医師になるには、医学部6年+初期研修2年で最短8年。
私立大学医学部では学費が3,000万円超に達する場合もあり、奨学金や自治体の修学資金など支援制度の活用が不可欠です。
それぞれ解説します。
医学部学費と地方進学の負担
| 区分 | 6年間学費の目安 | 補足 |
| 国公立大学 | 約350万円 | 他学部と同水準 |
| 私立大学(平均) | 約3,300万円 | 最低1,850万円〜最高4,550万円 |
| 防衛医大 | 0円(給与支給) | 卒業後9年間自衛隊勤務 |
| 自治医大 | 0円 | 卒業後9年間地域医療に従事 |
(出典:朝日新聞)
地方医学部への進学では家賃・生活費も加算されるため、総費用はさらに膨らむ可能性があります。
研修医〜若手時代の給与と生活コスト
初期研修医の年収は400万円前後が一つの目安ですが、勤務先・地域・当直回数によって100 万円程度の幅があります。
大学病院は教育環境を重視するため手当が少なく、300万円台半ばにとどまるケースも珍しくありません。
3年目以降の専攻医になると夜勤・救急手当が加算され、600〜900万円へ緩やかに上昇する傾向があります。
ただし、都市部の民間病院では1,000万円近くに達する例もある一方、地方の公的病院では600万円台にとどまるなど差が大きいのが実情です。
医者のメリット:やりがい・安定性

医師は長時間労働や高い学費といった厳しい現実を抱えながらも、社会から厚い信頼を寄せられる存在です。
ここでは主なメリットを解説します。
社会的信頼と人に感謝されるやりがい
診療現場では「先生のおかげで助かった」と直接感謝される場面が少なくありません。
この感謝の言葉こそが、医師としての使命感と達成感を同時に味わえる最大の魅力です。
また、難関資格保持者として社会的信用が高く、住宅ローンなど金融面の審査が有利に進むことも多い点は、将来設計を考える上で大きなメリットと言えるでしょう。
高い専門性と多彩なキャリア・収入の可能性
医師は診療科を自由に選べるほか、開業医や産業医、企業のメディカルドクターなど、多様な働き方が可能です。
開業医の平均年収が勤務医よりも多い傾向があり、専門医取得や非常勤・産業医の副業で収入をさらに伸ばす道も開かれています。
高度な専門知識を持つ医師はAI時代でも代替されにくく、医療需要の拡大を背景に将来性が極めて高い職業だといえるでしょう。
本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾
医師の激務や高い学費を乗り越えるには、まず医学部に確実に合格することが肝心です。
医学部専門予備校 京都医塾は、完全個別カリキュラム・ICT環境を軸に、学習からメンタルまで総合的に支援し、最短距離であなたを合格ラインへ導きます。
13名チーム制で弱点分析&徹底補強
医学部専門予備校 京都医塾では、専門講師・プロチューター・メンターなど13名がチームを組み、あなたの学力データを多角的に分析。
弱点単元は担当講師が即時にカスタム課題を作成し、理解度を日次で共有。メンターは進捗と生活リズムをチェックして学習効率を最大化します。
学力・メンタル・生活管理を一体で支える体制だから伸び悩みを最短で解消し、合格可能性を高めます。
また、週に1回、模試結果をレビューし、戦略をすぐに更新します。
常に「いま必要な勉強」が可視化されるため、迷わず走り切れます。
完全個別カリキュラムで最速合格へ
医学部合格に必要な科目・配点は大学ごとに大きく異なります。
医学部専門予備校 京都医塾では志望校と現在の成績から逆算した「合格最短ルート表」を作成し、1週間単位で学習計画を提示。
得意科目は先取りで難問演習に集中し、不得意科目は基礎穴埋めから段階的に強化します。
カリキュラムは毎週見直すため、模試や学校行事で予定がずれてもすぐにリカバー。
教室と寮の学習時間も連動し、無駄な移動や空き時間をゼロに。
限られた時間を最大効率で使い切り、偏差値アップと志望校対策を同時に進められます。
寄り添いサポートで挫折ゼロへ導く
浪人生活の最大の敵は孤独とモチベーション低下。
医学部専門予備校 京都医塾の寄り添いサポート体制は、学習面だけでなく食事・睡眠・メンタルまで細かくケアします。
チューターが毎日声かけを行い、相談シートで悩みを共有、管理栄養士監修の寮食や生活リズム指導で体調をキープし、定期カウンセリングで不安を軽減します。
常に誰かが見守ってくれる安心感が、最後までやり抜く原動力になるでしょう。
まとめ

医師の道は長時間労働や高額な学費など厳しい現実がある一方で、人命を預かる使命感や社会的信頼といった大きな魅力もあります。
本稿では勤務環境・精神的ストレス・養成コストのデメリットを具体データで示し、対策やメリットも整理しました。
現実を数字で直視したうえで、自分の適性や価値観に照らして進路を選ぶことが肝要です。
しかし、不安や疑問を独力で解消するのは簡単ではありません。
そこで医学部専門予備校 京都医塾ならチーム制、完全個別カリキュラム、寄り添いサポート体制で学力とメンタルを同時に支え、合格への障壁を着実に取り除けます。
さらに「1泊2日医学部合格診断ツアー」では模試では見えにくい課題をプロが無料で分析し、交通費補助付きで最適な学習戦略を提案。
毎年多くの合格者を輩出した実績が、そのサポート力を裏付けます。
申し込みはオンラインから可能です。
迷う時間を行動に変えてみませんか。