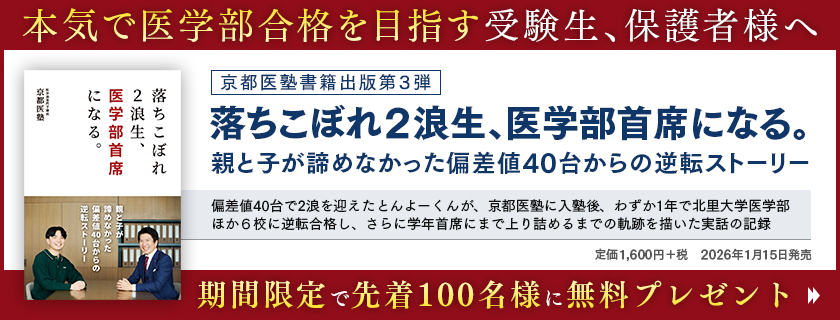2026年度大学入学共通テストは、新課程移行2年目にあたります。
前年2025年度は新課程初年度として出題内容の大幅変更がありましたが、平均点がおおむね6割と高めでした。(出典:旺文社)
しかし過去の傾向から、新課程2年目となる2026年度は難易度が上昇する可能性が高いとも言われています。
この記事では科目別に予想される難化ポイントを解説し、難化に対応する具体的な勉強法を紹介します。
受験生の皆さんが不安を解消し、2026年度入試で志望校合格を勝ち取るために今から取り組むべき対策を明確化します。
目次
2026年度共通テストは難化する?

新課程2年目の特徴
2026年度共通テストは、新学習指導要領に基づく入試改革の2年目にあたります。
初年度である2025年度は、受験生への影響に配慮した出題となり、全体の平均点が約6割と比較的高めでした。
一方で2年目からは本格的な出題へ移行し、難度上昇が予想されます。
これは初年度に易しめの出題で様子を見た後、2年目以降は本来の出題意図に沿った思考力重視の問題が増える傾向があるためです。
受験生にとって2026年度共通テストは、こうした2年目の難化に備えて一層の対策強化が求められる試験と言えます。
2025年度との違い
前年の2025年度共通テストとの最大の違いは、試験の難易度が上昇する可能性が高い点です。
2025年度は新課程初年度ということもあり、多くの科目で平均点が前年より上昇しました。
例えば、全科目平均の得点率は約59.5%と、前年の約57.7%から上がっています。
2025年度共通テスト本試験に新設された「情報Ⅰ」は、平均69.26点/100点と高めの得点率となりました。
初年度は受験生への配慮もあり比較的易しめの出題でしたが、2026年度以降はプログラミングやデータ分析など、より専門的な内容が本格化すると予想されます。(出典:大学入試センター)
このような初年度の易化傾向を踏まえると、2026年度は平均点が下がる=難化する可能性が高いと考えられます。
つまり、前年よりも難しく感じる科目が増え、得点力の差がより明確に出る試験になるでしょう。
そのギャップに備えるためにも早めの対策準備が重要です。
難化要因となる変更点
2026年度共通テストが難化するとすれば、新課程ならではの出題内容や形式の変化が主な要因です。
まず数学では、新たに「数学C」が加わったことで出題範囲が拡大しました。
また、情報Ⅰの導入も大きな変更点です。
初年度の情報Ⅰは専門的な内容が控えめでしたが、2年目以降はプログラミングやデータ分析など専門分野の出題が本格化し難化する可能性があります。
さらに出題形式面では、思考力・判断力・表現力を問う傾向の強化が挙げられます。
知識を暗記しているだけでは太刀打ちできず、初見の資料から必要な情報を抽出して活用する総合力が必要です。
これら新課程ならではの変更点が、2026年度共通テストの難化要因として受験生にとって大きな壁となると考えられます。
共通テストの科目別難易度予想

具体的にどの科目がどの程度難しくなりそうなのか、2025年度の平均点データを踏まえて整理してみましょう。
| 科目 | 2025年の平均点 | 2026年の見通し | ポイント |
| 国語 | 126.67 | 横ばい〜やや難化 | 5大問・90分に定着。複数資料読解が重要。 |
| 数学ⅠA | 53.51 | 横ばい | 難易度は例年並み。 |
| 数学ⅡB・C | 51.56 | やや難化 | C領域が追加。範囲拡大。 |
| 英語R | 57.69 | 横ばい | 2025年は8題・44問、語数は前年より約700語減。2026年の語数は未公表。 |
| 英語L | 61.31 | 横ばい | 1回読み中心で要点把握力が重要。 |
| 情報Ⅰ | 69.26 | 難化の可能性 | 初年度は易しめ。2年目以降はプログラミングやデータ分析が本格化か。 |
| 物理 | 58.96 | 横ばい〜やや難化 | 実験考察型が増加傾向。 |
| 化学 | 45.34 | やや難化〜同程度 | 平均点が大きく低下。計算+考察混合が時間を圧迫。 |
| 生物 | 52.21 | 横ばい | 資料読解型が中心。 |
| 地学 | 41.64 | 横ばい〜やや難化 | 2025年は最低水準。資料・計算問題が重い。 |
※出典:大学入試センター「令和8年度大学入学共通テスト 実施要項」
※出典:大学入試センター「令和7年度 大学入学共通テスト 実施結果の概要」
共通テストの難化に対応する勉強方法
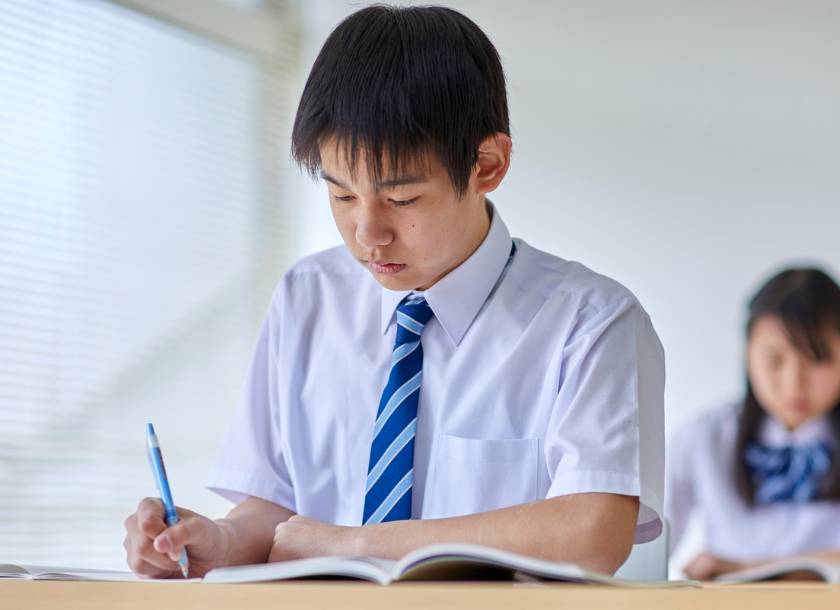
思考力・読解力の強化
共通テストが難化しても乗り越えるためには、思考力と読解力の強化が欠かせません。
知識暗記型の勉強だけでは、新傾向の問題に対応できない可能性があります。
与えられた文章・資料・データを素早く読み解き、そこから考察・判断して答えを導く力を普段から養っておくことが必要です。
具体的な対策としては、以下のような方法があります。
| 対策方法 | ポイント |
| 複数資料の読み比べ訓練 | ・国語や社会で複数の文章 ・資料を横断して読む・異なる情報源を行き来して要点を整理 ・新聞の社説と関連グラフを組み合わせて、共通点や相違点を要約するなど |
| グラフ・表の読み取り | ・理科や社会で統計資料を素早く解釈する力を育成 ・増減の傾向や数値の差異を押さえて分析 ・教科書のグラフを見て、自分の言葉で説明する練習を繰り返すなど |
| なぜそうなるかを考える習慣 | ・暗記した知識を因果関係や原理に結びつける ・「なぜその結果になるのか」を常に自問自答 ・歴史は原因と結果を論理的に説明、理科は原理に立ち返って理由づけするなど |
これらのトレーニングを継続することで、読解スピードや情報処理能力、論理的思考力が向上します。
共通テストは現役高校生の半数以上が受験する大規模試験であり、問題の出題傾向も徐々に落ち着いてきたと評価されています。
だからこそ今後は基礎力に加え、思考力・判断力をどう伸ばすかが合否の分かれ目となるでしょう。
教科横断的な思考力強化を図り、難化に負けない学力の土台を築いてください。
模試・過去問の活用
共通テストの難化に備えるうえで、模試と過去問は欠かせない教材です。
特に「時間配分の感覚をつかむこと」と「出題傾向の把握」に直結するため、ただ受けるだけでなく復習や分析まで徹底することが大切です。
以下の表に、模試と過去問を使った学習のポイントを整理しました。
| 対策方法 | ポイント |
| 模試の活用 | ・制限時間を本番同様に設定して演習 ・最新の出題傾向を体験できる・復習では「なぜその解き方になるのか」を突き詰めて理解する |
| 過去問演習 | ・制限時間内に解き切る練習で実戦感覚を養成 ・問題傾向の「安定部分」と「変化部分」を把握 ・英語リスニングの定番パターンや数学の頻出単元を研究し、予想問題で新傾向にも対応 |
模試や過去問を活用すれば、弱点の発見・修正や時間配分の改善が進みます。
本番前に繰り返し演習し、解法の選択や切り替えを自分のものにしておくことが合格への近道です。
苦手科目の優先対策
難化が予想される科目こそ、早めに克服しておくことが重要です。
苦手を放置すると失点のリスクが増す一方で、得点源に変えられれば周囲との差を一気に広げられます。
次の表に、苦手科目への取り組み方を整理しました。
| 対策方法 | ポイント |
| 基礎の総点検 | ・教科書・基礎参考書を一通り確認 ・新課程で加わった範囲を重点的にチェック |
| 頻出分野から攻略 | ・出題率が高い単元に集中・英語は長文リーディング、数学はデータ分析・図形問題などに優先的に取り組む |
| 学習計画の前倒し | ・高3夏までに苦手分野の基礎を完成 ・高2から高3内容を先取り学習しておくと効果的 |
| 質問と振り返り | ・独学で詰まったら早めに質問 ・模試や過去問の誤答はノートに整理し、同じミスを繰り返さないようにする |
苦手を克服することは「弱点を埋める」だけでなく「強みに変える」チャンスでもあります。
バランスよく全科目を学びつつ、特に弱点科目には優先的に時間を配分して取り組みましょう。
本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾
2026年度の共通テストは新課程2年目となり、思考力重視の出題が本格化するため難化が予想されています。
こうした状況で医学部合格を目指すには、効率的かつ徹底した学習環境が欠かせません。
ここでは、医学部受験生を力強くサポートする医学部専門予備校 京都医塾の特徴を3つご紹介します。
教科横断で学べる個別カリキュラム
医学部専門予備校 京都医塾では、医学部合格から逆算して設計されるフルオーダーメイドの学習カリキュラムを提供しています。
科目ごとに細かい習熟度別のクラスを設定することで、得意分野は上位レベルで伸ばし、苦手分野は基礎から強化することが可能です。
組み合わせは主要4科目だけでも1万通り以上に及び、一人ひとりに最適化された学習計画が実現します。
さらに定期的な進捗確認で柔軟にカリキュラムを更新するため、入試直前まで常に自分に合った内容で学習を進められるのが強みです。
知識の定着と応用力を段階的に高め、共通テストや二次試験で通用する実力を着実に養います。
伴走型のチーム体制で受験を支援
生徒一人に対して約13名の講師がチームで指導にあたる体制を整えています。
各教科の講師が情報を共有しながら連携するため、学習の偏りを防ぎ、効率的な進度管理が可能です。
また、三者面談を通じて学習状況を共有し、保護者とも密に連携しています。
生活面や精神面のサポートも含め、チーム全体で伴走する仕組みがあるからこそ、受験生活を安心して続けることができます。
ICTを活用した効果的な授業設計
授業にはタブレットやICT教材を積極的に導入し、進度や理解度を可視化しながら効率的に学習を進められる設計を採用しています。
演習結果や小テストのデータを分析することで、生徒ごとの弱点や理解不足を即座に把握し、次の授業や課題に反映させています。
共通テストにも対応できるよう、日々の授業から実戦的なトレーニングを行う環境が整っています。
まとめ
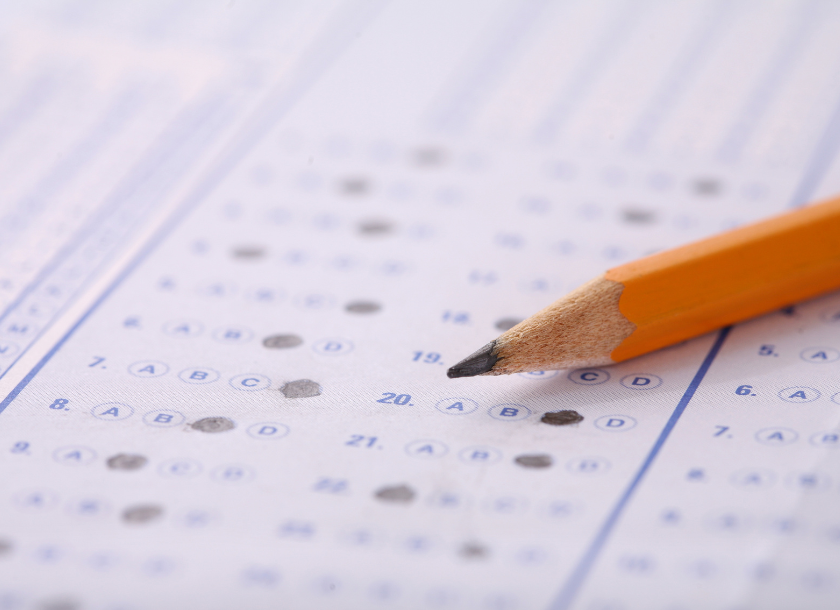
この記事では、2026年度共通テストが新課程2年目に入り難化が予想される背景や科目別の傾向、対応すべき勉強方法について整理しました。
全体としては、知識暗記だけでは通用せず、思考力や応用力を伴う総合的な学習が求められます。
この変化に不安を感じる受験生も多いですが、適切な環境と指導を受けることで確実に乗り越えることができます。
医学部専門予備校 京都医塾では、教科横断のカリキュラムやチーム体制でのサポートを通じて、共通テストの難化にも対応できる力を養っています。
まずは1泊2日医学部合格診断ツアーをご検討ください。
交通費・宿泊費は全額無料なので、費用の心配なく自分に合った学習環境を確かめることができます。
医学部受験に向けた課題を明確にし、自信を持って次の一歩を踏み出せる貴重な機会を、ぜひ活用してみてください。