医学部の受験では、理科3科目のうちほとんどの受験生が化学を選択します。
そのため、多くの人が受験本番を念頭に置き、早い段階から化学の学習をスタートさせていることでしょう。
そこで今回の記事では、医学部入試の化学の特徴や勉強方法などを解説していきます。
医学部化学の入試傾向と特徴
医学部入試の化学の傾向や特徴を知ることで、より効率的に学習に臨むことができます。
ここでは、医学部入試化学の主な特徴を3点ピックアップして解説します。
計算過程が採点の対象にならないことがある
医学部入試の化学では、回答形式として短答式(マークシートや穴埋め形式)の問題が中心です。
そのため、途中の計算過程がどれだけ正しくても、最後の答えを間違えてしまうと点数は一切もらえません。
論述問題が出題されることも
医学部入試の化学では短答式(マークシートや穴埋め形式)が主流ですが、一部の大学では論述問題も出題されます。
聖マリアンナ医科大学や順天堂大学医学部などでは毎年のように論述問題が課されており、知識の丸暗記では対応できない応用力を試す内容が多い点が特徴です。
論述問題の対策としては、化学の論述問題に特化した参考書を使って繰り返し演習を積むことが効果的です。
それでも不安が残る場合は、予備校などで専門の講師から指導を受け、万全の態勢で試験に臨むと良いでしょう。
有機化学で生化学関連の問題が多い
医学部入試の化学では、有機化学分野で生化学に関連する問題の出題比率が非常に高くなっています。
例えば、アミノ酸に関する内容で大問一つが丸ごと出題されるなど、医学的に重要なテーマから多く問題が出される傾向があります。
生化学関連の問題は難易度が高いため、こうした問題に対応できる力を磨いておくことが攻略に必要です。
単に過去問を解くだけでは真の対応力は身につきません。
基本的な有機反応や合成経路など、基礎をきちんと理解して応用できるようにしておく必要があります。
医学部化学の出題範囲
医学部入試の化学では、高校化学の全範囲にわたる問題が出題されます。
理論化学・無機化学・有機化学の各分野からバランスよく出題される傾向にあり、大学によっては高分子化合物(高分子分野)の問題も含まれます。
例えば、理論化学では化学平衡や酸塩基平衡などのテーマが頻出であり、有機化学ではアミノ酸や糖など生化学と関連する分野が重視されます。
全体として、医学部の化学では全領域にわたる広範な知識と深い理解が求められると言えるでしょう。
医学部化学で合格点を取るために必要な力
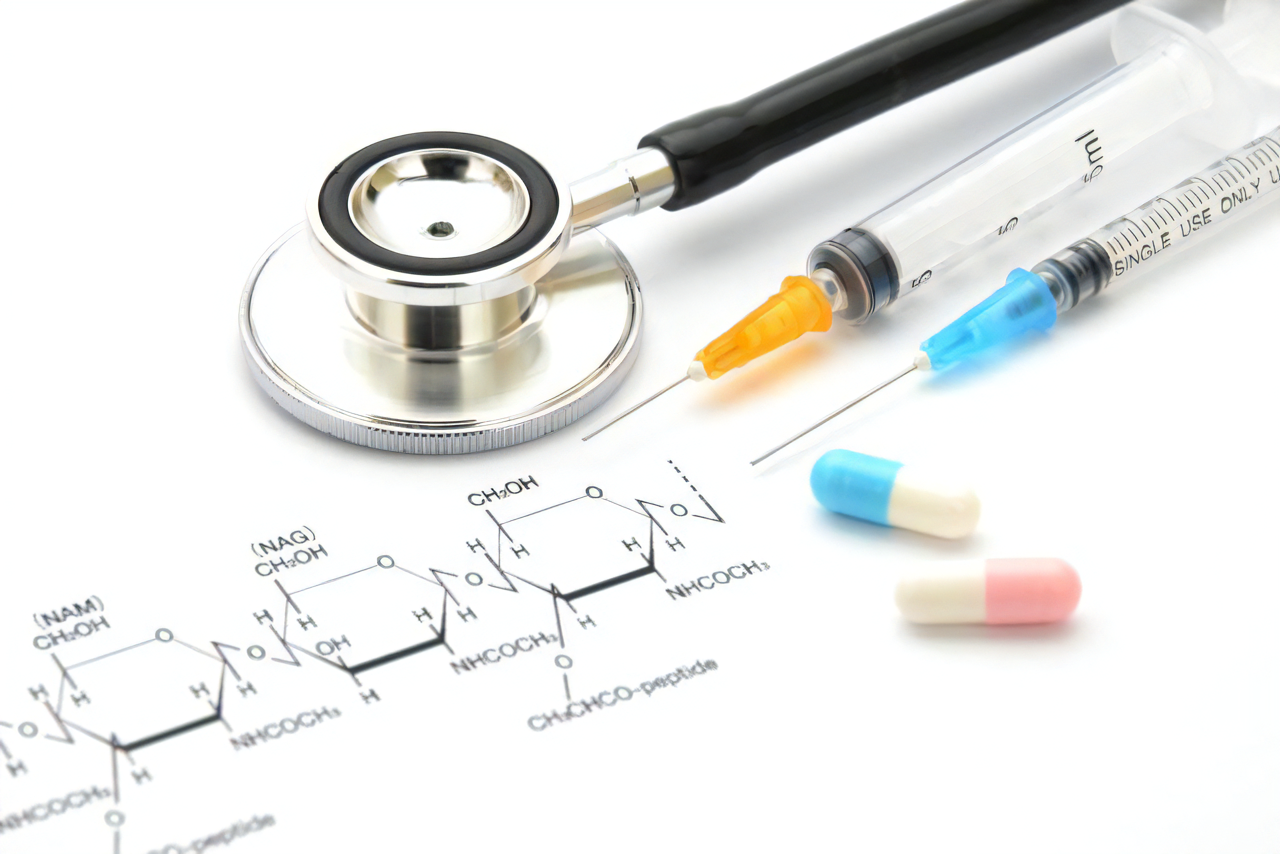
ここからは、医学部入試の化学で合格点を取るために必要な力を解説します。
重要な要素を4点に絞って取り上げますので、ぜひ参考にしてください。
計算力
医学部入試の化学では、非常に煩雑な計算問題が出題されます。
計算の難易度自体は数学や物理ほどではありませんが、それでも毎年多くの受験生を悩ませる分野です。
入試化学では、四則演算を早く正確にこなす計算力が必要となります。
解答後に検算するクセをつけておくことも、失点を防ぐうえで大切です。
問題を把握する力
医学部入試の化学では、問題文を正確に読み取り状況を把握する力も求められます。
化学の設問は数学のように明快だったり物理のように図表で視覚化されたりしていることが少なく、文章だけで回りくどく書かれていることが多いからです。
しかし、低学年のうちから訓練しておけば十分対応可能です。
写真やイラストが豊富な資料集や図説を活用してイメージを掴んだり、実験内容を自分で図に描いて全体像を把握したりするなど、普段から問題文を理解する訓練をしておきましょう。
とにかく基礎力が重要
医学部入試の化学に限ったことではありませんが、まずは基礎力をしっかり身につけておくことが合格への第一歩です。
学習初期の段階では、教科書や基礎的な参考書に書かれている事項を丁寧に読み込み、理解する作業が必要となります。
無機化学や有機化学の分野には暗記で対応できる問題もありますが、基礎が固まっていないと問題の本質を理解できず正答率が下がってしまいます。
教科書や基本的な参考書を活用して学習を進め、確かな基礎力を養いましょう。
応用力と実践力
基礎知識に加えて、それを応用し本番で発揮できる実践力を身につけることも重要です。
医学部入試の化学では、単純な暗記では歯が立たない初見の融合問題や複雑な設定の問題が出されることがあります。
日頃から過去問や応用的な問題演習に取り組み、学んだ知識を様々なパターンの問題で使ってみることで、試験本番で通用する応用力を養いましょう。
このようにアウトプット中心の学習を積んでおけば、本番でも落ち着いて初見の問題に対処できるはずです。
入試化学の勉強のポイント
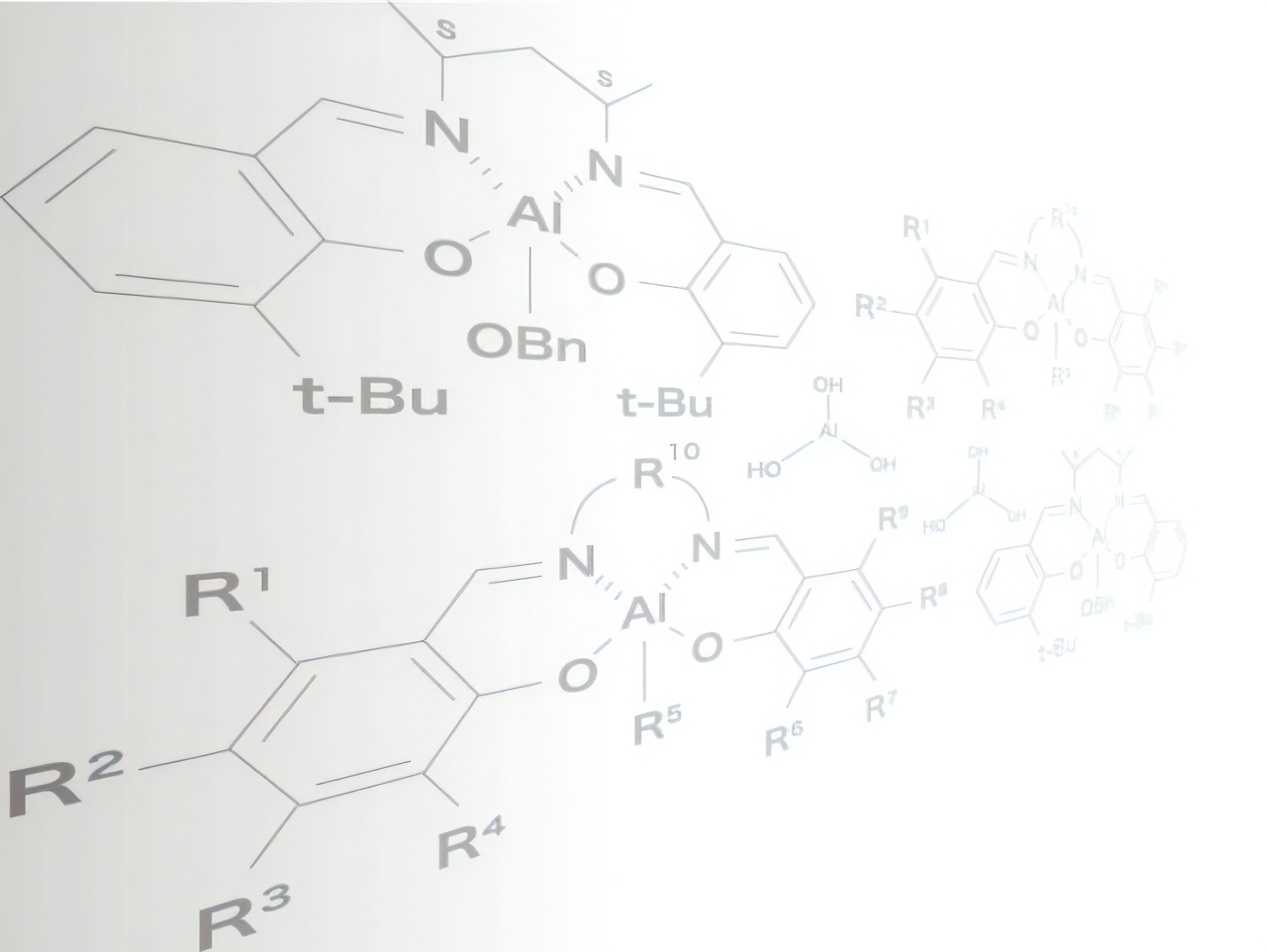
医学部入試の化学で成績を伸ばすには、いったいどのような点に注意すれば良いのでしょうか。
ここでは、勉強の際に意識したいポイントを4つに絞って解説します。
化学は短期間で成績を伸ばしやすい
化学は習熟に必要な勉強量が数学や英語に比べて少ないため、短期間で成績を伸ばしやすい科目だと言われます。
ただし、各分野ごとに一点集中で学習するよりも、理論化学・無機化学・有機化学を横断的・体系的に学習することが重要です。
化学の各分野は互いに深く結びついているため、小手先のテクニックで個別に対策しようとしてもかえって非効率になる場合があります。
常に「なぜそうなるのか」「何が起こっているのか」を意識して考える習慣をつけましょう。
特に難関医学部を志望する人は、全ての領域を広く深く身につけておかないと太刀打ちできません。
苦手分野を作らず、知識を万遍なく身につけるよう心がけてください。
計算力を身につける
前述のとおり、医学部入試の化学では高度な計算力が要求されます。
標準的な難易度の大学であっても、スピードと正確さを求められる計算問題が出題されることがあるからです。
必要なのは単純な知識量だけではありません。
問題の本質を見抜き、どの公式で解くべきか瞬時に判断する力や、計算方法を工夫して効率的に解く力を養いましょう。
もちろん最後に検算を行いミスを発見できる力も必要です。
このように、医学部化学では各自が工夫を凝らしながら高い計算力を身につける努力が求められます。
暗記事項の定着
医学部入試の化学では、計算力だけでなく各分野の知識量も合否を左右します。
苦手な分野で計算ミスによる失点が出てしまうこともあるでしょう。
そうした取りこぼしを補うためにも、無機・有機など各分野の暗記事項を確実に自分のものにしておくことが大切です。
知識問題は計算問題に比べてケアレスミスが起こりにくいため、暗記分野をどれだけ確実に得点源にできるかが合否を分ける場合もあります。
計算問題への対策だけでなく、教科書や参考書の解説を繰り返し読み込み、知識を着実に蓄えておきましょう。
理論化学の重要性
医学部の化学で得点力を伸ばすには、理論化学の習熟度を高めておくことも重要です。
理論化学で扱うモル計算や滴定計算は、無機化学・有機化学の問題を解く上での土台となります。
化学の問題は、計算力を問うもの・知識を問うもの・思考力を問うものに大別できますが、この中で差が付きやすいのが計算問題です。
理論化学を正しく学ぶことで、医学部入試の化学における重要問題にもしっかり対応でき、得点源にすることができます。
医学部入試化学の勉強法

ここまでは医学部入試化学のポイントについて解説してきました。
ここからは、理論化学・無機化学・有機化学の3分野それぞれの具体的な勉強方法について説明します。
理論化学
理論化学は化学全体を学ぶ上で土台となる非常に大切な分野です。
ここをおろそかにすると、後述する無機化学や有機化学で得点を取ることが難しくなってしまいます。
前述のとおり、理論化学で学ぶ反応の原理は無機・有機の問題を解く基礎となります。
理論化学を学習する際は、基本的な用語の習熟と公式の意味・使い方の理解から始めるのがおすすめです。
基本用語を覚え、公式の背景知識を深めたら、次は計算問題を解ける力を少しずつ養っていきましょう。
とはいえ、「計算」といっても数学のように単純な数字の処理では済まないのが化学の難しいところです。
常にどんな根拠があってどんな現象が起こっているのかをイメージしながら学習を進め、実力を高めていきましょう。
無機化学
無機化学は暗記しなければならない知識量が非常に多い分野です。
そのため、無機化学を学習するときは得た知識を頭の中でイメージ化し、一度整理してから定着させることを意識しましょう。
色や物質の状態に関する表を丸暗記するのが苦手な人は、教科書や資料集に載っている写真を参考に、反応の様子を視覚的に捉えながら覚えると理解が深まりやすくておすすめです。
知識の定着には、費やした時間以上に「触れた回数」がものを言います。
覚えるのが苦手でも繰り返しインプットを続けることで少しずつ記憶に残っていくでしょう。
無機化学は学習方法を工夫すれば確実に得点源となる分野です。
知識に穴を作らないよう丁寧に学習し、本番では無機分野の問題を落とさないようにしてください。
有機化学
有機化学では、知識の正確さと暗記量に加えて、得た知識を複合的に関連付けて活用する力が求められます。
例えば、有機化学の反応問題では、反応そのものを物質名だけで暗記するのではなく、その物質の製法やその物質に対して起こり得る反応まで含めて理解しておく必要があります。
有機化学を学習する際は、新しい知識を身につけると同時に、それを応用する力も養っていきましょう。
なお、官能基の種類や命名法は有機化学理解の要となる部分ですから、必ずマスターしておいてください。
本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾
医学部入試の化学は出題範囲が高校化学全域にわたる上、難度の高い計算問題や大学によっては論述問題まで出題されるため、独学だけでは不安を感じる方も多いでしょう。
本気で医学部合格を目指すなら、こうした難関入試に特化した指導が受けられる医学部専門予備校 京都医塾で効率良く実力を伸ばすことをおすすめします。
生徒一人に対し13名の講師陣がチームで指導
医学部専門予備校 京都医塾では、生徒一人に対して平均13名のプロ講師がチームを組み、情報を共有して指導方針を統一した上で、科目間のバランスを考慮した最適な指導を行います。
講師陣は京都大学をはじめ難関大学の出身者が多く、専門知識を極めたプロ揃いです。
学習で疑問が生じたら社員講師に質問して解決できます。これによりその日のうちに弱点を解消でき、効率的に学習を進められます。
一人ひとりに最適なオーダーメイドカリキュラム
医学部専門予備校 京都医塾では徹底的な現状分析にもとづき、一人ひとりに最適化した医学部合格までのカリキュラムをオーダーメイドで作成します。
集団授業は各教科の習熟度別に細かくクラス分けされており、得意科目は上位クラス・苦手科目は下位クラスで受講可能です。
組み合わせは主要4科目だけでも1万通り以上に及び、さらに個人授業を組み合わせることで弱点を徹底フォローします。
また、学習の進捗や模試結果に応じてカリキュラムの効果を分析し、必要に応じて途中でも柔軟に計画を変更・最適化するため、常に無駄のない効率的な学習が可能です。
合格まで生徒に寄り添う徹底サポート体制
医学部専門予備校 京都医塾は、医学部に合格するまで指導・サポートの手を決して緩めません。
出願計画の立案から願書の記入指導・面接対策に至るまで、経験豊富な講師陣が丁寧にサポートします。
遠方での入試では講師・スタッフが生徒とともに現地入りし、同じ宿泊先に滞在します。
起床や食事から試験当日の会場入りまで、京都にいる時と同様に万全のサポートを行います。
また、入試期間中も毎日指導が続けられ、入試前日・当日の試験後にも、その日の入試問題を使った重要事項の確認やミスをした箇所の改善指導を行います。
まとめ
この記事では医学部入試の化学について、その出題傾向や求められる力、効果的な勉強法を解説しました。
医学部化学では高校範囲全体から幅広く問題が出され、とりわけ有機分野では生化学系のテーマが重視される傾向があります。
また、多くの大学で短答式(マーク式・穴埋め式)の出題が中心となり計算の正確さが問われ、一部の大学では知識の暗記だけでは対応できない論述力も試されます。
したがって合格には、全領域にわたる知識の網羅と高速かつ正確な計算力、さらに初見の問題にも対応できる応用力をバランス良く身につけることが重要です。
しかし、これらを独力で習得するのは難しく、勉強法に不安を感じる受験生もいるでしょう。
こうした不安や課題を抱える方は、医学部専門予備校 京都医塾でプロのサポートを検討してみてください。
経験豊富なプロ講師陣が一人ひとりの弱点や課題を把握し、最適な指導で合格まで導いてくれます。
まずは医学部専門予備校 京都医塾が開催している1泊2日医学部合格診断ツアーに参加してみてはいかがでしょうか。
このツアーは1泊2日の無料体験で、遠方からでも安心の交通費・宿泊費無料です。
経験豊富なスタッフの授業を実際に体験でき、現在の学力を詳しく分析、合格までに必要な勉強法やカリキュラムを提案してくれます。
完全無料ですので、医学部合格への第一歩としてぜひお気軽にお申し込みください。


