医学部は6年間という長期の修学期間に加え、膨大な専門知識と実践的なスキルの習得が求められます。
一般的な大学生活とは異なり、医学部生は朝から夕方まで講義や実習が組まれ、さらに夜遅くまで自主学習に取り組むことも珍しくありません。
解剖学実習、臨床実習、共用試験、国家試験などの重要なイベントも目白押しです。
医学部での学びは確かに大変ですが、その分やりがいも大きく、将来の医療を支える重要な土台となります。
今回の記事では、医学部志望の皆様に、より具体的なイメージを持っていただくため、各学年や実習における忙しさの実態を詳しくお伝えします。
中でも、医学部の忙しさがよくあらわれる項目についてランキング形式で見ていきましょう。
目次
医学部には大変な時期や学年がある

医学部は確かに勉強量が多い学部ですが、6年間ずっと忙しいわけではありません。
実際、1年生は教養科目が中心で比較的余裕もあり、部活やサークル、アルバイトに打ち込める時期です。
ただし、学年が上がるにつれて専門的な学習や実習が増えていきます。
特に4年生以降は臨床実習が始まり、生活リズムが大きく変化します。
このタイミングでアルバイトを減らしたり、やめたりする医学部生は少なくありません。
「勉強漬け=忙しい」と捉えるなら、医学部生は確かに常に忙しいと言えるでしょう。
以下では、入学後に後悔しないためにも、医学部における学年ごとの忙しさや、本当に忙しいと言えるのかについて詳しく見ていきましょう。
医学部進学者は1日の大半を勉強にあてている
医学部生の1日は、朝8時頃から夕方16時頃まで講義や実習が組まれています。
特に高学年になると、大学病院での臨床実習が始まるため、一般的な大学生よりも拘束時間が長くなります。
また、講義や実習以外の時間もレポート作成や試験勉強に充てる必要があり、平日は2〜4時間、休日は8時間程度の自主学習が求められるのが一般的です。
ただし、すべての医学部生が同じように勉強漬けの毎日を送っているわけではありません。
効率的な学習方法を見つけ、メリハリをつけて学生生活を楽しんでいる人も多くいます。
進級のしやすさは1つの指標に
医学部の「忙しさ」を客観的に判断する1つの指標として、進級率があります。
もし忙しさ=勉強量と仮定するなら、進級率の低い大学ほど学習負担が大きいと考えられます。
例えば、5年次への進級率が70%台の大学では、相当な学習時間を確保しないと進級できない可能性があります。
一方で、90%以上の進級率を維持している大学もあり、カリキュラムの違いが学生の忙しさに影響を与えていると考えることも可能です。
もちろん、進級率だけで大学の忙しさを判断するのは適切ではありません。
自分の学習スタイルに合った大学を選ぶことが充実した医学部生活を送るために求められるものの、『低い進級率=忙しい』という見方もできるということです。
【学年別】医学部の忙しさランキング
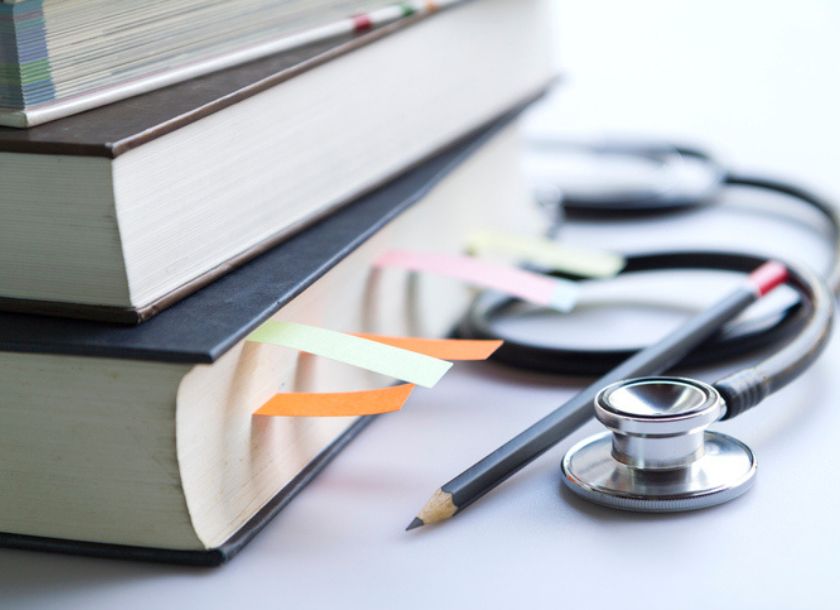
医学部の6年間は、学年によって忙しさのピークが異なります。
特に臨床実習が始まる高学年になるほど、座学中心の低学年とは比較にならないほど多忙を極めやすいです。
また、医師になるための知識と技術を段階的に習得していく過程で、各学年にはそれぞれの課題があり、乗り越えるべき山場も存在します。
ここでは、医学部生が経験する忙しさを学年別にランキング形式で紹介します。
第一位:5年生に臨床実習の本格化
5年次は病院での臨床実習(通称「ポリクリ」)が本格的に始まり、医学部生活の中でも特に多忙になります。
朝から夕方まで患者対応やカンファレンスなど実習漬けの毎日で、実習後もレポート作成や翌日の予習、定期試験対策に追われます。
多くの大学では5年生から診療参加型臨床実習(クリニカル・クラークシップ)が導入されており、医学教育カリキュラムの約1/3(最低63単位相当)は臨床実習に充てられる仕組みです。
近年は臨床実習期間を大幅に延長する大学もあり、5年生は長時間の実習と学内試験準備を両立しなければならない最も忙しい学年と言えるでしょう。
(出典:大阪医科薬科大学)
第二位:4年生以降の実習が始まるタイミング
多くの大学で4年生後期から臨床実習がスタートするため、このタイミングが次に忙しい時期となります。
座学中心だった生活が徐々に病院実習中心へ切り替わる過渡期で、新しい実習環境への適応に追われます。
特に4年生の終わりには共用試験が控えており、その合格に向けた勉強と並行して実習の予習も進めなければなりません。
講義・試験の負担に加え実習準備も重なる4年生は、「忙しさ」が一段と増す学年と言えるでしょう。
第三位:3~4年生の共用試験CBTとOSCE対策
3〜4年生で受験する共用試験CBTとOSCEは、臨床実習に参加するための重要な関門です。
CBTは基礎医学から臨床医学までの知識を問うコンピューター試験で、OSCEは基本的な診察技能や医療面接能力を評価する実技試験です。
この試験に合格しなければ臨床実習に参加できないため、3年生後半から本格的な対策が始まることになります。
特にOSCEでは、バイタルサインの測定や医療面接など、実技の練習に多くの時間を費やすことになるでしょう。
もちろん、CBTも膨大な範囲から出題されるため、3年生のうちから計画的な学習が求められます。
両試験の準備と並行して通常の講義や試験もこなさなければならず、時間的な制約も大きくなりやすいことから忙しいです。
第四位:6年生の就職活動と国家資格試験対策
6年生は医師国家試験と研修医マッチングという2つの大きな課題に取り組む時期です。
しかし、医学部受験時に培った学習習慣があり、また医師の需要も高いことから、他学年と比較すると精神的な負担は比較的軽いと言えます。
国家試験対策は膨大な範囲を扱いますが、これまでの学習内容の総復習という側面が強く、新しい内容の習得は限定的です。
就職活動も、医師不足を背景に比較的スムーズに進むケースが多く、一般企業への就職活動ほどの負担はありません。
ただし、希望する病院への研修医マッチングを目指す場合は、病院見学や面接対策など追加の時間が必要になることもあります
第五位:履修科目が多い1年生
医学部1年生は、医学の基礎となる生物学、化学、物理学に加え、教養科目や英語など、幅広い科目を履修します。
週のほとんどの時間が授業で埋まっており、一見すると忙しく感じられます。
しかし、医学部に合格するまでに培った学習能力があれば、多くの学生は比較的スムーズに対応できます。
また、この時期は部活動やサークル活動、アルバイトなど、学業以外の活動に時間を使える最後の機会でもあります。
授業数は多いものの、高学年と比べると自由度が高く、時間管理次第で充実した学生生活を送ることが可能です。
【大学別】医学部における勉強の忙しさランキング

医学部では「留年→再試験」「国試浪人」が発生すると学習時間が大幅に増えます。
そこで6年間ストレートで卒業し、そのまま医師国家試験に合格できた学生の割合=6年ストレート医師率を目安に算出しました。
以下では、学業負担が大きい大学を国公立大学医学部・私立大学医学部別に上位3校ずつ並べました。
6年ストレート医師率が低い大学ほど留年・国試浪人が発生しやすく、結果として学業負担(=忙しさ)が大きいとしています。
国公立大学医学部
| 順位 | 大学 | 卒業率 | 国試合格率 | 6年ストレート医師率 |
| 1 | 徳島大学 | 80.2% | 91.0% | 73.0% |
| 2 | 島根大学 | 82.5% | 93.1% | 76.9% |
| 3 | 宮崎大学 | 86.3% | 94.3% | 81.4% |
※6年ストレート医師率=(卒業率×新卒国試合格率)÷100
※出典:文部科学省|各大学の医学部医学科の入学状況及び国家試験結果等 令和6年度)
私立大学医学部
| 順位 | 大学 | 卒業率 | 国試合格率 | 6年ストレート医師率 |
| 1 | 久留米大学 | 66.4% | 90.7% | 60.2% |
| 2 | 川崎医科大学 | 68.0% | 91.5% | 62.2% |
| 3 | 近畿大学 | 68.7% | 94.0% | 64.6% |
※6年ストレート医師率=(卒業率×新卒国試合格率)÷100
※出典:文部科学省|各大学の医学部医学科の入学状況及び国家試験結果等 令和6年度)
【実習編】医学部で行われる忙しい授業・試験ランキング

ここでは、『医学部で単位が落とせない』『試験突破を必須とする』という2つの観点からランキングをご紹介します。
こちらも傾向の1つですが、プレッシャーに負けることなく学習を継続しなければならない特有の忙しさがあります。
第一位:解剖学・生理学・生化学
医学の根幹を成す3大基礎医学は、学習量と難易度から医学部でもっとも忙しい時期として知られています。
特に解剖学実習では、3か月にわたり週3回の実習が組まれ、300〜400個もの専門用語を英語と日本語で覚えなくてはなりません。
また、生理学では体の仕組みを分子レベルで理解し、生化学では複雑な代謝経路を暗記する必要もあります。
この科目は医学における「共通言語」となるため、ここでつまずくと臨床医学の理解に支障をきたします。
そのため多くの医学生は夜遅くまで図書館に籠もり、グループ学習で理解を深めながら必死に学習に取り組む独特の忙しさがあるのです。
第二位:臨床実習前OSCEとCBT
4年次に行われるOSCE(客観的臨床能力試験)とCBT(コンピューター試験)は、臨床実習に進むための関門として位置づけられています。
OSCEでは医療面接やバイタルサインの測定など基本的な診療技能が、CBTでは基礎医学から臨床医学までの総合的な知識が試されます。
一般的に、医学部では双方の試験に合格できなければ、5年次からの臨床実習に参加できません。
結果、医学生は膨大な量の知識と技能の習得に追われます。
特にOSCEでは実技試験のため、放課後や休日返上で練習を重ねる必要があり、精神的にも体力的にも忙しい期間となります。
第三位:国家資格
医師国家試験は、6年間の集大成として位置づけられる重要な試験です。
就職活動や卒業試験との両立が必要となり、時間管理が極めて重要になります。医師として働くためには絶対に合格しなければならず、たとえ研修医としての内定を得ても、不合格なら医師として働くことはできません。
そのため多くの医学生は、1年以上前から計画的な受験勉強を開始し、模擬試験や問題演習を繰り返し行います。
特に直前期は睡眠時間を削って学習に励む学生も多く、医学部最後の大きな山場として忙しい期間となるでしょう。
本気で医学部合格を目指すなら京都医塾
医学部受験は、単なる暗記や演習の繰り返しでは太刀打ちできません。
そこで京都医塾では、70名以上の正社員講師陣が1人ひとりの生徒に寄り添い、医学部への合格に向けて着実に歩みを進めるサポートを続けてきました。
以下では、医学部を目指している人に向けて、京都医塾の特徴を3つご紹介します。
難関医学部にも対応!独自のチーム指導
京都医塾では、京都大学出身者が7割を占める70名以上の正社員講師が、各教科のエキスパートとして指導にあたることで難関医学部にも対応しています。
月3回の教科別会議に加え、月1回の担当者会議で生徒1人ひとりの進捗状況を徹底的に分析し、結果を基に必要に応じてカリキュラムを柔軟に調整します。
また、完全1対1の個人授業と少人数制の集団授業を組み合わせ、弱点克服と実践力養成を同時に実現しているのも特徴です。
中学レベルまで遡った基礎固めから、医学部合格に必要な応用力の育成まで一貫した指導によって、将来的に忙しさを感じやすい医学部での学習に必要な力も身につけることができます。
数々の合格者を輩出!驚きの実績
京都医塾は、偏差値40台から医学部合格を実現させた実績を持ち、本気で医学部へ合格したい受験生をノウハウでサポートします。
また、生徒1人ひとりに担任と副担任の2名と教務スタッフ1名が付くほか、週1回のカウンセリングで学習進捗や悩みを丁寧にヒアリングして悩みも随時解決できます。
学寮での朝6時起床、深夜0時就寝という規則正しい生活リズムの確立から、食事の栄養管理まで、合格に必要なあらゆる側面からサポート可能です。
遠方からでも安心!学寮をしっかり完備
全国各地から集まる医学部志望者のために、京都医塾では充実した学寮環境をご用意しています。
校舎から徒歩わずか3分という好立地に位置する専用学寮には24時間体制で寮母が常駐し、家具・家電完備の快適な環境で、学習に専念できる生活が送れます。
京都医塾の『1泊2日医学部合格診断ツアー』では、一人ひとりに最適化された個別指導を体験可能です。
ツアーで受け取れる詳細な診断レポートで「何を・どこから・どのように」手をつけたら良いのか知ってみませんか?お気軽にお問い合わせください。
まとめ

医学部の忙しさは学年によって大きく異なり、特に5年生の臨床実習期間がもっとも多忙を極めます。
4年生以降は臨床実習が始まり、生活リズムが大きく変化する一方、1年生は比較的余裕のある時期です。
忙しい6年間を乗り越えるための土台作りは、医学部受験の段階から始まっています。
京都医塾では「空きコマスケジュール」による15分単位の時間管理や、栄養管理された食事など、医学生に求められる自己管理能力を受験期から身につけられます。
医師になるという夢の第一歩を、プロと共に踏み出してみませんか?
1泊2日の無料合格診断ツアーでは、あなたの現在地を把握し、合格までの道筋を明確にご提示しますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。


