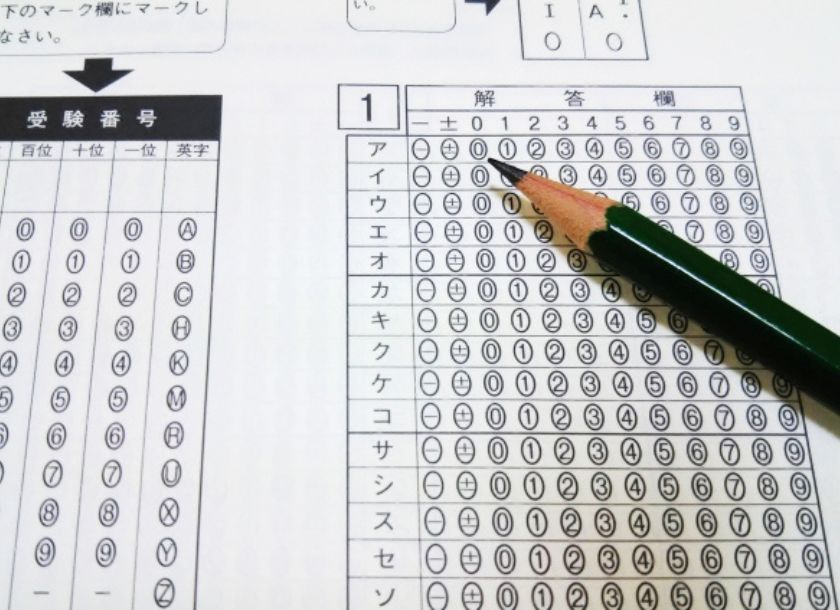社会が苦手な受験生のなかには、「医学部受験なら社会は必要ない?」「できるだけ苦手な社会を避けて医学部受験を乗り切る方法を知りたい」と考えている人もいるでしょう。
そこで今回の記事では、医学部受験における社会の配点比率をランキング形式で紹介します。
記事を読んで配点比率の違いや傾向についても理解し、志望校選びや受験戦略に役立てましょう。
目次
社会の配点が低い医学部ランキング【国公立大学】

まずは2025年度入試の共通テスト(前期)において、社会の配点が低い国公立大学医学部を紹介します。
【共通テスト(一次試験)で社会の配点が低い大学(上位15校)】
| 順位 | 大学名 | 配点比率 |
| 1位 | 横浜市立大学 | 5.0% |
| 2位 | 徳島大学 | 5.6% |
| 2位 | 奈良県立医科大学 | 5.6% |
| 4位 | 新潟大学 | 6.3% |
| 5位 | 大阪公立大学 | 7.4% |
| 6位 | 和歌山県立医科大学 | 8.3% |
| 6位 | 秋田大学 | 8.3% |
| 8位 | 弘前大学 | 9.5% |
| 9位 | 山梨大学※1 | 10.0% |
| 9位 | 広島大学 | 10.0% |
| 9位 | 愛媛大学 | 10.0% |
| 9位 | 信州大学 | 10.0% |
| 9位 | 大分大学 | 10.0% |
| 9位 | 琉球大学 | 10.0% |
| 9位 | 札幌医科大学 | 10.0% |
※1:前期試験の実施がないため後期試験データを使用
※2:同順位は全体の配点比率が低い順で記載
全50校中、共通テストでの社会の配点比率が10%以下の大学は23校です。
また、2025年度入試において、二次試験の科目として社会を使用する国公立大学はありませんでした。
社会に配点がある医学部【私立大学(共通テスト利用)】

2025年度入試において、私立大学医学部で一般選抜に社会を使用する大学はありません。
しかし、共通テスト利用入試を利用した場合に社会が試験科目に入る大学があります。
| 大学名 | 英語 | 数学 | 理科 | 国語 | 社会 | 配点 比率 | 備考 |
| 順天堂大学 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 11.1% | ※1 |
| 東京医科大学 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 11.1% | ※1 |
| 国際医療福祉大学 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 12.5% | ※2 |
| 関西医科大学 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 12.5% | ※2 |
| 産業医科大学 (一般選抜A) | 60 | 60 | 80 | 60 | 40 | 13.3% | ※1 |
※1:1科目選択(2科目選択した場合は第1解答科目を使用)
※2:1科目選択(2科目選択した場合は高得点の方を使用)
共通テスト利用入試がある全31大学のうち、社会が試験科目に入っている大学は5大学です。
また、配点比率も11~13%台程度と国公立大学と同様に低い水準です。
医学部受験で重要な「配点比率」とは
配点比率とは、大学入試における各科目の比率であり科目の重要度を示す指標です。
共通テスト(一次試験)・個別試験(二次試験)、あるいは全体の合計点を100%とした際に、各科目がどれだけの割合を占めるかを表します。
配点比率を見れば、受験する大学がどの科目を重視しているのかが分かります。
なぜ点数で示さずに配点比率で示すのかというと、大学ごとに満点が異なるため単純に点数だけで大学同士を比較しにくいためです。
医学部の場合は理科を重視する大学が多く、国語・社会は多くの大学で重要度が低い、など大まかな傾向はあるものの大学ごとに設定する配点はさまざまです。
また、国公立大学の場合共通テストと二次試験それぞれの試験内の配点比率があるため、志望する大学の共通テスト内での配点比率、個別試験内での配点比率に加えて共通テストと個別試験の比率についても知っておく必要があります。
特に複数の大学を受験する場合、各大学の配点比率についても考慮しておかないと合格ラインを見誤る危険性が考えられます。
医学部の社会の配点は大学によってどのくらい違う?
配点比率と重要性について確認したところで、医学部受験における社会の配点は大学によってどのくらい違うのかを共通テストを例に見てみましょう。
共通テストで社会の配点比率が低い医学部
| 大学名 | 外国語 | 数学 | 理科 | 国語 | 地歴公民 | 情報 | 一次配点比率 | 英語 | 数学 | 理科 | 面接 | 小論文 | 総合配点比率 |
| 横浜市立大学 | 300 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 5.0% | 400 | 400 | 600 | 〇 | 〇 | 2.1% |
| 徳島大学 | 200 | 200 | 300 | 150 | 50 | 〇 | 5.6% | 200 | 200 | – | 〇 | – | 3.8% |
| 奈良県立医科大学 | 200 | 200 | 300 | 100 | 50 | 50 | 5.6% | – | – | – | 〇 | 100 | 5.0% |
-:試験実施なし
〇:配点の明記なし(総合判定に使用)
3大学とも共通テストの6科目に対して、社会1科目の配点が占める割合は5%程度です。
また、二次試験では基本的に社会は試験科目に入らないため、全体で見ると配点比率は5%以下になっています。
共通テスト社会の配点比率が高い医学部
| 大学名 | 外国語 | 数学 | 理科 | 国語 | 地歴公民 | 情報 | 一次配点比率 | 英語 | 数学 | 理科 | 国語 | 面接 | 総合配点比率 |
| 京都大学 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 18.2% | 300 | 250 | 300 | 150 | 〇 | 3.9% |
| 岡山大学 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 18.2% | 400 | 400 | 300 | – | 〇 | 6.1% |
| 熊本大学 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20.0% | 200 | 200 | 200 | – | 200 | 7.7% |
-:試験実施なし
〇:配点の明記なし(総合判定に使用)
一方、共通テストでの社会の配点比率が高い3大学でも、二次試験では社会がないため全体に対する配点比率は4~7%台まで下がります。
したがって、試験全体で見ると社会の配点比率に大きな差はないといえるでしょう。
ただしいわゆる「足切り」があることを考慮すると、共通テストにおける最大15%の配点比率の差は大きいのではないでしょうか。
医学部受験における社会科目の位置づけと対策
大学ごとの社会の配点比率を紹介したところで、次に医学部入試における「社会」の位置づけと対策について解説します。
医学部受験での社会の配点の傾向
医学部入試においては、社会が試験科目に入っている場合でも配点比率は平均11%と、高くても20%程度と全体的にかなり低い割合となっています。
試験全体で配点比率を見るとさらに低くなり、国公立大学ではすべての大学が10%未満、私立大学でも15%未満です。このように、医学部受験において基本的に社会の重要度は低い傾向です。
特に私立大学医学部では、共通テスト利用で社会を課す大学をわざわざ選ばない限り社会の勉強自体が不要なことからもこの傾向が分かります。
元々社会は配点比率が低いことに加え、2025年度の「情報」科目の追加により以前よりもさらに配点比率が若干下がっていると考えられます。
医学部受験において社会の科目は何を選ぶべき?
新課程となる2025年度から、共通テストの社会の科目は以下の8つです(実際には地理総合・歴史総合・公共は1科目扱い)。
<歴史>
- 【必履修】歴史総合
- 【必履修+選択】歴史総合+日本史探究
- 【必履修+選択】歴史総合+世界史探究
<地理>
- 【必履修】地理総合
- 【必履修+選択】地理総合+地理探究
<公民>
- 【必履修】公共
- 【必履修+選択】公共+倫理
- 【必履修+選択】公共+政治・経済
このなかから、必履修科目+選択科目、または必履修科目(※必履修科目は必履修科目同士のみ受験可能)を1科目分として受験科目を決定する形になります。
可能ではあるものの学習分野が増えてしまう必履修科目同士の受験は現実的ではなく、実際には必履修科目+選択科目の組み合わせで選ぶことになるでしょう。
また、医学部受験において重要度が低い社会で選ぶべきは科目は「短い時間で得点アップが狙えるもの」です。
したがって、暗記量が比較的少ないとされる「地理総合+地理探求」×「公共+政治経済」または「公共+倫理」の組み合わせがおすすめです。
医学部受験で配点の低い社会は最小限の対策に絞ろう
高い水準の得点率が求められる医学部入試では、主要科目でなくとも「社会」対策を軽視するわけにはいきません。
しかし、配点比率の低い社会に時間を割くことで主要科目である英語・数学・理科の対策が不十分になってしまうのは最も避けるべき事態です。
そのため、社会については共通テストにおいて7~8割程度を目指すので十分でしょう。
社会は知識中心の科目のため、参考書を使ったインプット学習を中心に短期集中で対策するのが効果的です。
本気で医学部合格を目指すなら京都医塾
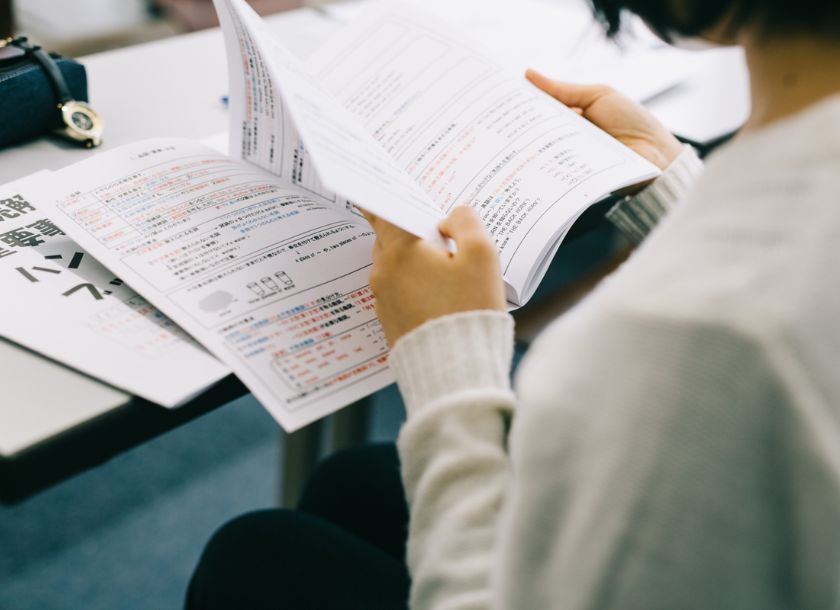
高い学力が求められる医学部受験において、得意科目の最大限の活用とともに苦手科目の克服も重要です。
特に文系科目である社会に対して、苦手意識を持ったり点数が伸び悩んでいたりする医学部受験生も多いのではないでしょうか。
得意科目・不得意科目の双方を効果的にサポートするのが、医学部専門予備校「京都医塾」です。
弱点の克服と長所のさらなる伸長を可能にする「完全1対1個人授業」
京都医塾では、受験生の方々に合わせた指導を実践して学力向上へと結びつけています。
そして、そんな指導方法の中でも大きな効果をあげているのがマンツーマンで行われる「完全1対1個人授業」です。
この個人授業のもとでは、受験生の方の不得意分野は中学生レベルにまで、さかのぼって絶対的な基礎力を身につけてもらい弱点の克服を行ってもらいます。
また、得意分野については適切な課題等で実力の伸長を促すため、短期間での驚異的な偏差値のアップが可能です。
不得意科目の克服と得意科目の強化の両立で、医学部合格に必要な総合的な得点力を育てます。
一泊二日診断ツアーで合格への最短ルートを見つけられる
医学部合格を目指すなら、まず自分の学力と課題を正確に把握することが重要です。
京都医塾では、一人ひとりに最適な学習戦略を見つけるために「一泊二日医学部合格診断ツアー」を実施しています。
ツアーでは、京都医塾独自の学力診断とマンツーマン指導を無料体験。
学力診断テストで現在のレベルを測定し、克服すべき課題を明確化。
今の勉強方法が本当に正しいかをチェックできます。
また、テスト結果をもとに分析し、あなた専用の受験戦略を提案。
過去の合格データを活用し、医学部合格までのロードマップを作成するので、「何をどう勉強すればいいのか」が明確になります。
お子様の習熟度を振り返るための三者面談も実施
京都医塾では、節目に合わせて年に5回の三者面談を実施中です。
この三者面談では主にお子様の習熟度を振り返りますが、そのほかにも各教科の得意不得意や偏差値の推移などもご報告しております。
加えて、受験校を決定する際のアドバイスも実施して、今後の方針についてのお手伝いもいたしています。
上記のような取り組みを通じて保護者様の安心を確保しているのは、まさに京都医塾ならではのサポート体制のたまものです。
まとめ
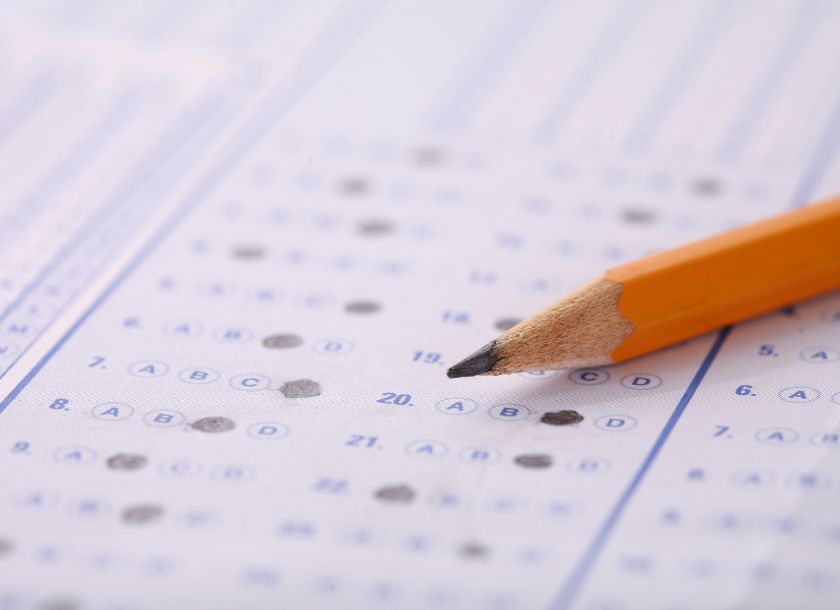
医学部受験において、科目の配点比率はある程度同様の傾向があるものの、国公立大学と私立大学、また大学ごとに異なります。
私立大学の医学部受験では基本的に社会は勉強の必要がありません。
一方、国公立大学では必須ですが配点比率は低いため、数学や理科などの重点科目により注力すべきでしょう。
医学部専門予備校の京都医塾なら、得意科目のさらなる伸長や苦手科目の克服だけでなく科目ごとの重要度に応じた受験戦略まで徹底的にサポートし、医学部合格の可能性を最大化します。
京都医塾では、現在の実力分析と体験授業が無料で受けられる「一泊二日医学部合格診断」を行っています。気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。