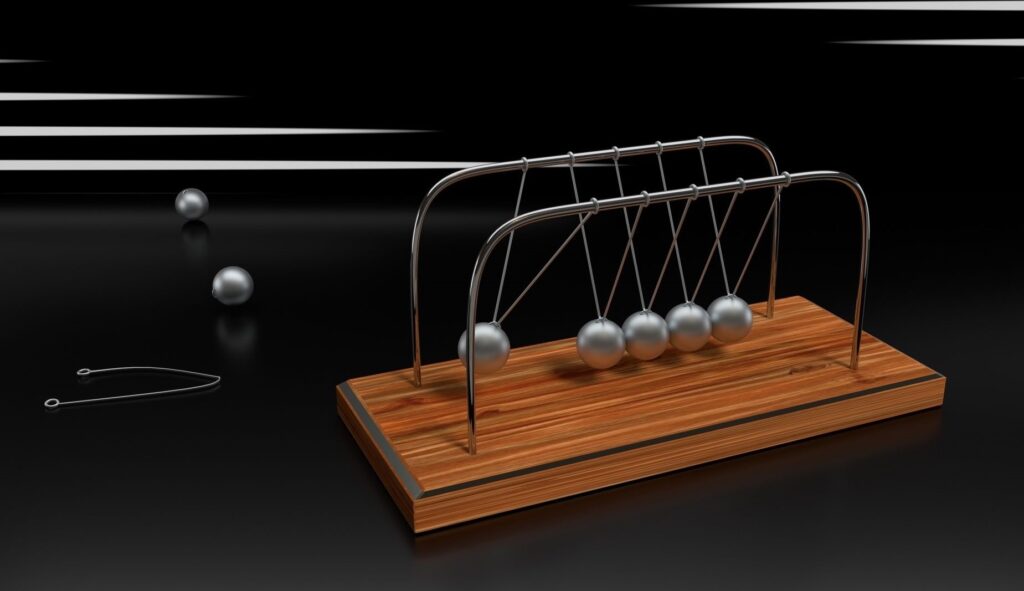医学部入試では理科2科目の選択が合否に影響するほど重要です。
特に物理は計算力を武器に得点源にしやすい一方、対策を誤ると難関となり得ます。
この記事では、物理選択のメリットとデメリット、最新の入試傾向や効率的な勉強法を整理し、志望校に合わせた戦略作りに役立つ情報をお伝えします。
目次
医学部入試における理科の科目選択
医学部の入試では数学や英語に加えて、理科から2科目を選択して受験する必要があります。
理科には化学・生物・物理の3科目がありますが、多くの受験生はこれらのうちどの科目を選ぶかで悩むのではないでしょうか。
科目選択は合否に大きな影響を与える重大事項ですから、悩むのも無理はありません。
まず初めに、医学部入試時の理科科目の選び方について整理しておきましょう。
以下では、医学部入試の理科科目選択に関する基本的な情報とポイントを解説します。
医学部の理科の入試について
医学部の受験では、多くの大学が生物・化学・物理の3科目の中から2科目を選択して受験する方式を採用しており、これが現在の一般的な形となっています。
国公立大学でもすべての医学部が理科2科目で受験できる形式を採用しており、受験生の負担軽減につながっています。
ただし、大学によっては理科の組み合わせに指定(例:物理+化学のみ可)がある場合もあるため注意が必要です。
また、今後の入試改革や大学方針の変更によって出題科目が見直される可能性もあります。
志望大学の最新の入試要項を毎年必ず確認し、受験科目の要件を正確に把握しておきましょう。
なお、理科の科目選択では多くの受験生が化学を選択するため、「化学+物理」または「化学+生物」の組み合わせで受験するケースが大半を占めています。
好きな科目を選んでもOK?
医学部の理科科目は基本的に「化学+物理」または「化学+生物」の組み合わせから選択できます。
つまり多くの医学部では、自分の得意科目に合わせて選択が可能です。
ただし注意が必要なのは、一部の医学部では理科が「物理+化学」の必須指定になっていることです。
必ず出願前に各大学の要項を確認する必要があります。
医学部受験の物理の特徴
医学部受験で物理を選択しようと考えている人に向けて、まず物理という科目自体の入試での特徴を押さえておきましょう。
他の理科科目と比べた際の物理の傾向や出題内容の特徴を理解しておくと、科目選択や勉強計画の参考になります。
ここでは医学部入試における物理の代表的な特徴を紹介します。
標準問題中心の大学と思考力重視の大学がある
医学部の物理の入試問題には、大きく分けて2つのタイプがあります。
一つは一般理系学部と共通するような、典型的・標準的な問題が中心のタイプです。
もう一つは思考力や高度な計算力を試す独自色の強い難問を出すタイプです。
前者は主に国公立大学で見られ、難易度自体は教科書レベルから大きく逸脱しません。
その代わり合格には高得点の安定確保が必要で、ミスなく解き切ることが求められます。
一方、後者のタイプは主に私立の医学部や一部の国公立で見られ、問題数が少ない代わりに一問一問が非常に難解です。
制限時間内に全て解き切るのが難しいため、取れる問題を見極めて解答する戦略が重要になります。
このような思考力重視型の出題では、物理が得意科目で高得点で差をつけたい人には有利ですが、基礎がおろそかだと太刀打ちできません。
志望校の出題傾向を研究し、自分に合った対策を立てましょう。
原子分野や医学関連の出題傾向が高い
医学部入試の物理では、他の学部と比べて原子物理分野の出題頻度が高い傾向があります。
過去問を分析すると、数年周期でコンスタントに原子分野の問題を出す大学もあり、医学部志望者は早めに典型的な原子分野の問題演習まで済ませておくと安心です。
また、多くの大学で医療機器など医学に関連したテーマと絡めた物理問題が見られます。
例えばX線撮影の原理や血流の物理など、一見医学知識が必要そうな設定が登場することもあります。
ですが、これらの問題でも求められる物理知識自体は高校範囲がベースです。
物理現象の本質を理解していれば、背景設定に惑わされずに対応できるでしょう。
力学・電磁気が物理の核となる
医学部の物理では全範囲から出題されるものの、中でも力学と電磁気学は特に重視される単元です。
多くの大学では、力学と電磁気の大問がそれぞれ1問ずつ出題され、残りの波動・熱・原子などから1〜2問が出題される傾向にあります。(大学によって比率は異なります)
したがって、まずは力学・電磁気を確実に得点源にできるように基礎を固め、必要に応じてその他の分野も弱点なく対策していくことが大切です。
力学分野の理解は他の単元の理解にも直結しますので、土台として非常に重要だと言えます。
物理を選択するメリット

医学部の受験で物理を選択するメリットには、学習効率や受験校の選択肢に関わるものなど様々な点が挙げられます。
ここでは、物理選択の代表的なメリットを2点取り上げて解説します。
生物と比較して高得点を出しやすい
まず挙げられる物理選択のメリットは、得点のしやすさに関する点です。
物理はミスさえしなければ高得点を狙いやすい科目です。
生物選択の場合、計算問題が少ない分一つのミスで大崩れすることはありませんが、暗記量が多いうえに考察・論述問題で読解力や記述力が求められるため、満点を取るのは容易ではありません。
一方で物理の場合、公式の意味や使い方を正しく理解していれば生物ほど細かな暗記は必要なく、比較的満点近くまで狙いやすい科目です。
暗記負担が少ない分、全単元を一通り学習するのにも生物より時間がかかりません。
短期間で全範囲を学び終えられるということは、その分演習量を増やして学習の深度を深められるということでもあります。
言い換えれば、物理は短期集中で実力を伸ばしやすい科目であり、得点源にしやすいとも言えるでしょう。
物理選択で受験校の幅が広がる場合がある
2026年度入試では、大学や選抜方式によって理科科目の指定が異なります。
たとえば、名古屋市立大学の学校推薦型選抜では理科が「物理・化学」の2科目指定です。
一方、九州大学の一般選抜では共通テスト理科は「物理・化学・生物」から2科目選択で、物理必須ではありません。
さらに、佐賀大学は2026年度から共通テスト理科を「物理・化学・生物から2科目」に変更し、過去の「物理・化学」固定を改めています。(出典:名古屋市立大学、九州大学、佐賀大学)
物理を選択するデメリット
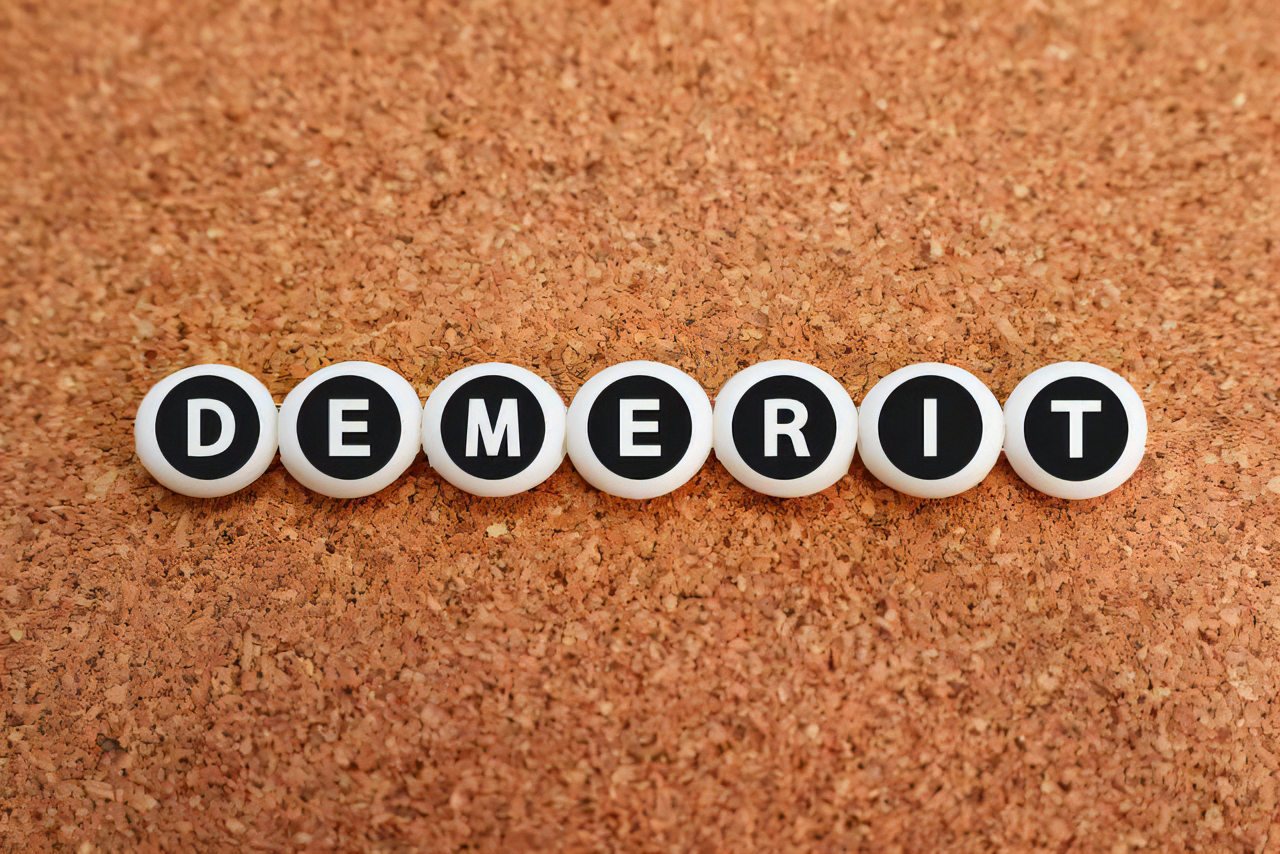
物理選択には多くのメリットがありますが、残念ながらデメリットも存在します。
物理を選ぼうか迷っている人は、デメリットについても把握した上で判断したいと考えるでしょう。
そこでここでは、医学部入試で物理を選択した場合に生じる代表的なデメリットを3点紹介します。
数学が苦手な人には向かない
ご存じのとおり、物理の問題を解くには高度な計算力が求められます。
この計算力は数多くの問題演習を積み重ねて少しずつ養っていくものであり、一朝一夕では身につきません。
また、一つの計算ミスが連鎖的に次の設問のミスにつながり、問題全体が解けなくなるケースも珍しくありません。
数学の問題を迅速かつ正確に処理する能力が求められるため、計算が苦手な人にとって物理はハードルが高い科目と言えるでしょう。
暗記が通用しない
前述のメリットでも触れたとおり、医学部入試の物理では暗記だけでは太刀打ちできない問題がほとんどです。
公式や定理そのものを覚えているだけでは応用問題に対応できません。
解法の本質を理解しないまま丸暗記で演習を繰り返していても、少しひねられた問題が出ると途端に対応できなくなってしまいます。
暗記力だけでは得点しにくいことが物理選択のデメリットの一つです。
大学に入ってから活用する機会が少ない
医学部入試で物理を選択することに関連するデメリットとして、進学後に直接役立つ場面が少ないという点も挙げられます。
例えば、生物の知識であれば解剖学や生理学、生化学、細菌学など大学の医学課程で広範囲に応用できます。
一方、物理で養われる論理的な思考力や全体を把握する力は有用とはいえ、生物ほど大学進学後に知識そのものを活かす機会が多くないのです。
また、高校で生物を履修していない場合、大学で学ぶ分子生物学や生命科学の内容が理解しにくいという声もあります。
もちろん大学に入ってから生物の知識を身につけて追いつくことは可能ですが、入学当初は生物選択者と比べて苦労するかもしれません。
このように大学進学後の学習面では物理選択者は若干ハンデを負う可能性がある点にも留意が必要です。
医学部物理の勉強法
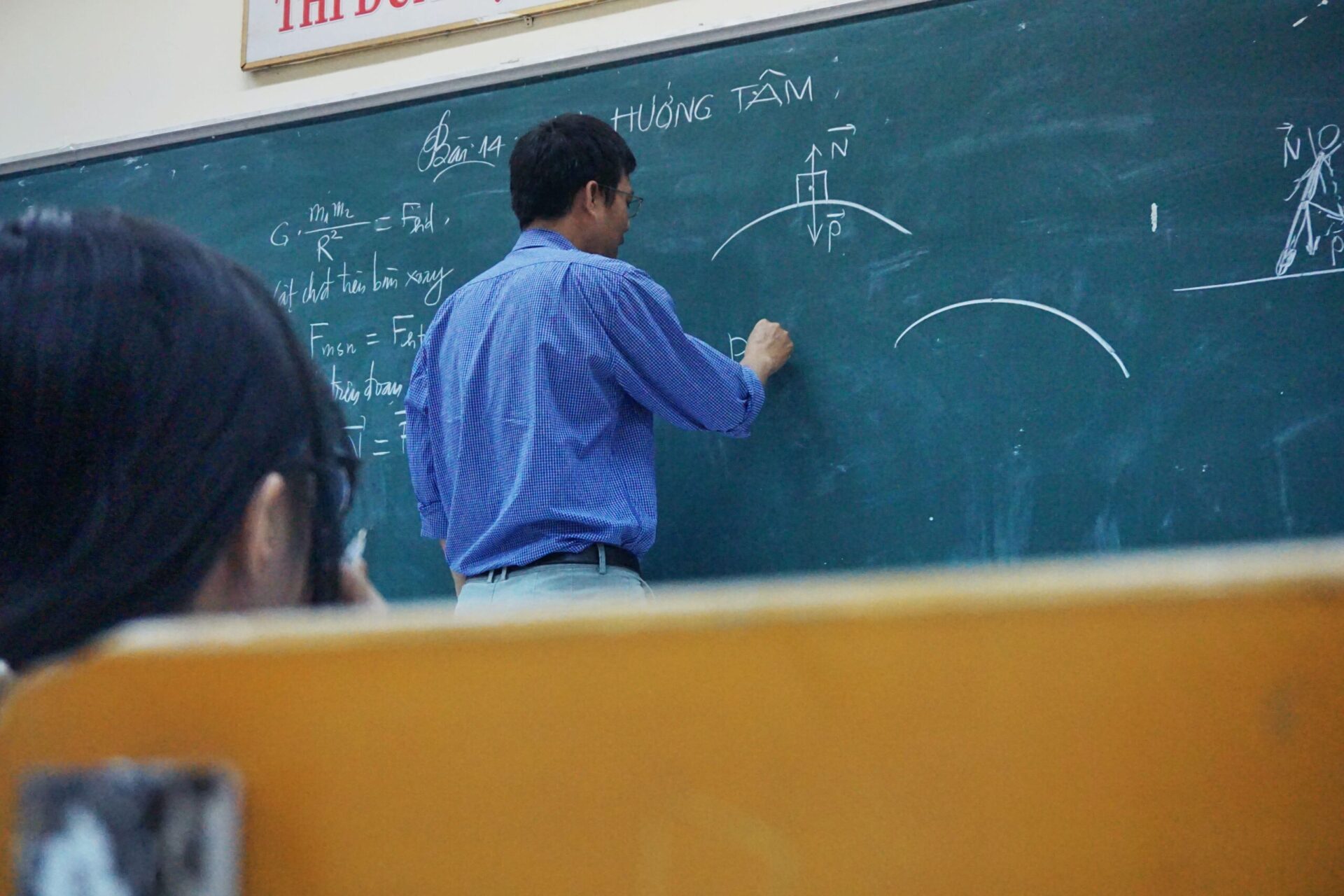
医学部合格を目指して物理を学ぶにあたっては、どのようなポイントを押さえて勉強を進めればよいでしょうか。
限られた時間で効率よく得点力を伸ばすためにも、効果的な学習法を知っておきたいところです。
ここでは、医学部入試の物理対策における代表的な勉強法のポイントを解説します。
力学を最初に押さえておくと良い
医学部入試の物理対策では、最初に力学から学習を始めるのがおすすめです。
理由は、高校物理の主要5分野(「力学」「電磁気学」「原子物理学」「熱力学」「波動」)のうち、力学が他の分野にも通じる基本知識を得られる領域だからです。
力学は他の単元の基礎とも言える分野ですから、おろそかにすると、物理全体の理解が浅くなるだけでなく、後の単元の理解にも影響してしまいます。
力学を早期に攻略できるかどうかが、物理全体の得点力を左右すると言っても過言ではありません。
勉強を進める際は、一問一問を深く考えながら解法を確実に身につけていくことが大切です。
物理は一つの問題を解くのに時間がかかる科目ですが、特に力学を学ぶ段階では「必要な時間」と割り切って腰を据えて取り組みましょう。
学習初期ほど一つひとつの問題にじっくり向き合い、解法の考え方を納得しながら覚えることが大切です。
基礎を固めることが大切
物理に限ったことではありませんが、何事も基礎を疎かにしていては結果を出すことはできません。
例えば野球でホームランを打ちたければ日々のバッティング練習が必要ですし、料理が上手くなりたければ食材の選び方や調理方法を覚える必要があります。
物理の試験対策も同様で、試験本番で結果を出すためには、基礎を固めて実力の底上げを図る作業が欠かせません。
物理の基礎固めをする際、最初に取り組むべきは標準レベルの問題集の徹底演習です。
医学部の物理ではハイレベルな問題が出題されますが、学習初期の段階では標準レベルの問題集で公式の意味や使い方を一通り確認しておくのが良いでしょう。
実力向上のコツとして、問題を解く際に自分で図やグラフを描いてみる習慣を付けるのも有効です。
描いた図表から何が読み取れるかを具体的に整理するクセを付けることで、より深く理解でき応用力も身につきます。
最終的にはスピードと正確さを求めていく
先ほど基礎固めの重要性について述べましたが、医学部入試では最終的にスピードと正確さが勝負になります。
医学部の物理では難度の高い問題が多数出題されるため、入試本番で勝ち抜くには限られた時間でミスなく解き切る力が必要です。
この2点(解答スピードと正確性)をクリアするには、基礎学習を通じて各単元の物理現象をイメージできるようにしておくことが大切です。
問題で扱われている事象がなぜ発生しているのか、どういう状況なのかを把握しながら勉強すると、問題文を見た瞬間に解法の方針が閃くようになります。
そうなれば入試レベルの難問にも落ち着いて対処できるでしょう。
物理に限りませんが、スピードを上げるには日頃の演習で時間を計りながら解く訓練も有効です。
どの問題にどのくらい時間がかかるかを普段から測定しておけば、本番での時間配分の感覚も養われます。
物理現象のイメージをしっかり掴み、基礎力+演習量でスピードと正確さを両立できる実力を育てていきましょう。
参考書の使い方
物理の参考書には大きく分けて以下の3パターンがあります。
- 初学者向けで、難しい内容を極力避けて平易に解説しているもの
- 難関大受験者向けで、大学物理や微積分を駆使し原理的な説明に終始しているもの
- 物理の本質的解説を捨てて、問題の解法パターン習得に特化したもの
物理を学習する際は、これら全てのタイプの参考書を横断的に活用することで強固な学力を身につけることができます。
もちろん、自分の現在の学力に合った参考書を選ぶことも大切ですが、それぞれの参考書には異なる狙いや特徴があるため、一冊に偏らず様々な観点から学習すると良いでしょう。
例えば初学者向けでざっと概要を掴んだら、次に本質的な難しめの参考書で理解を深め、最後に解法パターン集で演習量を積むといった使い分けがおすすめです。
本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾

医学部受験では科目選択や効率的な勉強法が合否を左右します。
本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾がおすすめです。
以下でその特徴を紹介します。
13名体制の講師陣が連携して指導
医学部専門予備校 京都医塾には、京都大学をはじめ難関大出身の講師が多数在籍しています。
生徒一人に対し13名の講師がチームを組み、指導方針を統一・共有しながら今どの科目を重点的に指導すべきかを検討します。
このチーム体制により、各科目のバランスを見極めつつ必要な科目に集中して学習を進めることが可能です。
医学部合格への個別カリキュラム
医学部専門予備校 京都医塾では、生徒一人ひとりに対して医学部合格のためのオーダーメイド学習カリキュラムを策定します。
入塾時の徹底的な分析に基づき、完全1対1個人授業と少人数集団授業をバランス良く組み合わせ、各時期に何をどこまで学習するかまで細かくプランニングするため、無駄のない効率的な学習が可能です。
合格まで寄り添う徹底サポート
医学部専門予備校 京都医塾では、生徒が医学部に合格するその日まで徹底した指導とサポートが続きます。
入試直前などに不安や緊張に悩まされ、押し潰されそうな時も、精神面の支えを含めて最後まで寄り添います。
受験勉強は孤独を感じやすいものですが、医学部専門予備校 京都医塾なら学力面だけでなくメンタル面でも支える万全のサポート体制が整っているため、受験生は安心して医学部合格まで走り抜くことができます。
まとめ
この記事では医学部入試で理科に物理を選ぶメリット・デメリットや難易度、効果的な勉強法について解説しました。
科目選択は志望校の受験科目要件や自分の得意不得意を考慮することが大切ですが、いずれにせよ基礎を徹底し継続的に努力することが合格に近づきます。
それでも物理を選択すべきか迷ったり、勉強法に不安を抱えたりする医学部受験生も多いでしょう。
特に数学が苦手な人にとって、物理の難問を独学で乗り切れるか心配になることもあるはずです。
医学部専門予備校 京都医塾なら充実した指導体制でそうした不安を解消できます。
13名の講師チームが一人の生徒を総合指導し、入試直前まで学習面とメンタル面を支えるので安心です。
まずは、現在参加できる1泊2日医学部合格診断ツアーで医学部専門予備校 京都医塾の学習環境と指導を体験してみませんか。
このツアーでは講師による授業体験や校舎・学寮の見学ができ、学力分析に基づいた今後の学習計画の提案も受けられます。
また、保護者と受験生の交通費・宿泊費が無料のため、遠方からでも安心です。
この機会にぜひお気軽にお申し込みください。