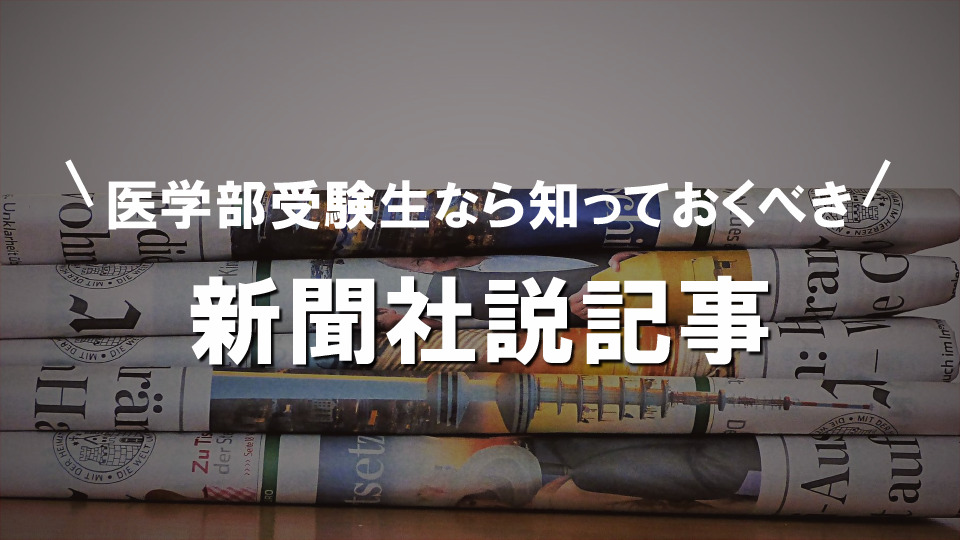京都医塾国語科では、週に1回『社説集』として、生徒に新聞社説記事を紹介しています。
今回は、『社説集』2023年2月まとめの③になります。➀で紹介した記事から、医学部受験生必見の記事を取り上げ、紹介したいと思います。
目次
注目二本
630-15.理工系学部の女子枠 多様性確保へ試みの一歩/2023/02/05 河北新報
631-7.飲む中絶薬承認へ 守りたい女性の体と権利/2023/02/08 山陽新聞
630-15.理工系学部の女子枠 多様性確保へ試みの一歩/2023/02/05 河北新報
本文
大学の理工系学部の入試で女子枠を設ける動きが広がっている。男性が多い学部に女性を増やすのが狙いだ。国際的に見てもその比率は低く、女性の選択肢を広げ、理工系分野での学生の多様性を確保する一つの試みと言える。
2023年入試では、名古屋、富山、島根といった国立大学でも学校推薦型で女子枠を設定。東京工業大も24年入試から適用するとしている。
例えば、名古屋大の場合、工学部の2学科の学校推薦型の定員計18人中、半数の9人を女子枠に設定した。2学科の定員158人の約6%に当たる。
より積極的な東工大の場合は、24年入試で4学院(学部に相当)の総合型、学校推薦型で58人、25年入試では6学院で143人の女子枠を設ける。こちらは募集人員全体の約14%。大学側は女子枠の導入により、全体の女性比率が20%以上になることを目指しているという。
いずれも女子枠を設けるのは一般入試ではない。ただ、総定員に変更がなければ、男性の志願者にとっては現状よりも狭き門となる。選抜方法を限定するなど男性側の不公平感への配慮は見られるものの、大学側が女性を入学させることに意欲的なのは、新たな学生の獲得という生き残り策の一環だからだろう。
630-15.理工系学部の女子枠 多様性確保へ試みの一歩/2023/02/05 河北新報
キーワード
- アファーマティブアクション
- 女子枠
解説
京都医塾公式コラムでは以前、医学部不正入試にかんする記事を掲載しました。日本の医学部入試において、ルールとして明確化されない形で、性別・年齢による差別が行われていたことが明らかになりました。
では一方で、理工系学部の入試において、男女の数的な不均衡を是正するために、女子限定の枠を設けることは社会的に許容されるでしょうか?「絶対に正しい」とは言い切れない問題だと思います(だからこそ、引用した記事でも「男性側の不公平感」に言及しています)。
2022年度から始まった「公共」科目の教科書(教育出版)では、「アファーマティブ・アクション」という語が、まさにこの不正入試・女子枠の設定という時事的問題と絡め、深掘りする形で紹介されています。一節を引用します。
K大学の(女子枠を設ける)試みは、積極的差別是正措置(アファーマティブ・アクション)と呼ばれる。日本では男女共同参画社会基本法に、積極的改善措置という言葉で、アファーマティブ・アクションが定義されている。これによると「男女間の格差を改善するために必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること」とされている。
しかし、いずれか一方だけに積極的に機会を提供することは、他方の機会を損なうことになりかねない。K大学の女子枠が批判されたのは、まさにこの点にある。女子受験生の優遇は、男子受験生にとって不利益となり、逆差別にあたると指摘されたのである。
上記の引用箇所を踏まえ、教科書では正義のあり方について、「通時的正義」と「共時的正義」がある、として、正義が一つの見方からはとらえられないことを示します。とてもおもしろいので、もし公共が選択科目でなくて、机の引き出しにしまいっぱなしになっている人は、ぜひその箇所を読んでください。白黒つけ難い問題について考えるためのヒントが得られます。
631-7.飲む中絶薬承認へ 守りたい女性の体と権利/2023/02/08 山陽新聞
本文
日本では手術だけに限られてきた人工妊娠中絶の方法に、ようやく飲み薬という選択肢が加わりそうだ。
英国の製薬会社が製造販売を申請していた経口中絶薬「メフィーゴパック」について、厚生労働省の専門部会が先日、承認して差し支えないと判断した。社会的関心が高いため意見公募を行い、3月にも結論を出す。
対象は妊娠9週までで、認められれば今春にも使えるようになる。嘔吐(おうと)など副作用のリスクはあるものの、女性の心身への負担軽減を進める一歩として歓迎したい。
ただ、中絶を巡る医療や制度は戦後から大きくは変わっておらず、女性のニーズを踏まえた検討が十分になされてきたとは言い難い。
キーワード
- 中絶
- パブリックコメント
解説
中絶については、アメリカ最高裁が昨年6月、「人工妊娠中絶は憲法で認められた女性の権利である」という判断を覆しました。それにより、各州が人工妊娠中絶の可否を含めたあり方について決めることになりました。性的暴行などによる望まない妊娠を余儀なくされた場合、自分の住む州が中絶を禁止していれば、別の州に移るなどして中絶をしなくてはなりません。中絶へのアクセスの地理的・経済的ハードルが上がったといえるでしょう。
日本では中絶が手術で行われることが一般的です。術後の不妊などについて一定のリスクがあります。一方で経口中絶薬にも一定のリスクがありますが、WHOも推奨する、体への影響が少ないとされる中絶法です。いずれにせよ、より安全な中絶を行うための選択肢が増えることは前向きな変化であるとして、今回、経口中絶薬を承認する方向性が確認されたのだと考えられます。
経口中絶薬承認については、特に「配偶者の同意を求めるかどうか」という点が議論の的となっています。中絶の可否の決定に際して、妊娠させた男性側の同意を得ることを要件とするかどうか、ということです。これは「女性が自分の体に起きたことに対し自分で決定してよいか」という自己決定にかんする根本的な問いにかかわります。
引用にある「意見公募」は「パブリックコメント」と呼ばれ、国の行政機関が政令・省令を定める際に、国民から意見や情報を募集する手続きです。今回、1万2千件のコメントが集まりました。それほどの社会的関心を集めている話題ですから、医学部受験生も無関心ではいられないはずですね。重要な時事トピックとして動向を注視していきましょう。
終わりに
いかがだったでしょうか。
京都医塾では、全国の社説集から精選した記事を収載した「社説集」を毎週生徒に配布しております。
付け焼刃ではできない小論文・面接対策。コツコツ知識を積み上げていくことが大事ですよ。