医師は将来増えすぎる?という疑問を、需給推計や人口動態・政策を踏まえ、地域・診療科の偏在と現場の不足を解説する記事です。
過剰化時の影響、受験生が意識すべきキャリア選択と制度の理解まで、誤解なく判断する視点を解説します。
近年、厚生労働省の医師需給推計や少子高齢化の進展を背景に、医学部の定員削減が議論されるなど、将来的な医師過剰が指摘されています。
一方で、現在の医療現場では地域や診療科によって医師不足が深刻な状況が続いており、働き手が足りず過酷な勤務環境も問題となっています。
この記事では、「医師余り」と言われる理由と実際の医療現場の実情を整理し、将来の医師需給を正しく理解する視点を解説します。
目次
医師が将来増えすぎると言われる理由
医師数の推移と将来予測
日本の医師数は長期的に増加傾向にあります。
厚生労働省の統計によれば、2022年末時点の全国の医師数は約34万3千人で、10年前から13%増加しました。
特に2008年度以降、深刻な医師不足への対策として医学部定員が段階的に拡大され、毎年輩出される新任医師の数が増えたことが背景にあります。
(出典:厚生労働省)
政策や人口動態が与える影響
人口減少・高齢化の変化と医療費の持続可能性を踏まえ、政府は医師数・配置の「適正化」を政策課題に位置づけています。
2026年度の医学部定員は「2024年度の総定員を上限」に設定、臨時増員の枠組みも暫定維持しており、2027年度以降は定員の適正化(見直し)を速やかに検討と明記されています。
本当に医師は余るのか?医療現場の実情

地域間での医師の偏在
全国の医師数が増えていても、「医師が足りている地域」と「依然として不足している地域」が同時に存在するのが実情です。
都市部には多くの医師が集中する一方、地方の過疎地域や医師数が少ない県では今も深刻な医師不足が続いています。
2022年のデータでは、人口10万人あたりの医師数は全国平均がおよそ262人ですが、最も多い徳島県では335人なのに対し、最も少ない埼玉県では180人と約2倍の差があります。
| 指標(2022年) | 数値 |
| 全国平均(医療施設従事医師/10万人) | 262.1 |
| 徳島県 | 335.7 |
| 高知県 | 335.2 |
| 京都府 | 334.3 |
| 埼玉県 | 180.2 |
| 茨城県 | 202.0 |
| 千葉県 | 209.0 |
※出典:厚生労働省|令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計
こうした地域格差のため、「全国の医師数が足りている」という主張があっても、地方では医師不足で患者が必要な医療を受けられないケースが依然起きているのです。
政府も偏在解消のため奨学金貸与や医師派遣などの対策を進めています。
診療科ごとの不足と過剰
医師の充足状況は診療科(専門科目)によっても大きく異なります。
例えば、産科・産婦人科や小児科、救急科などは勤務の過酷さや責任の重さから敬遠されがちで、慢性的な医師不足が指摘されてきました。
医師不足・余剰の問題は一括りに語れず、診療科ごとに見ても偏在が存在しているのが現状です。
医学生の専攻希望にも偏りがあり、外科や小児科は志望者が伸び悩む一方、人気の高い科目に希望者が集中する傾向が、さらなる偏在を生んでいます。
病院勤務医の不足という現場の声
「将来は医師が余る」と言われる一方で、現在進行形の医療現場では「勤務医が足りない」という切実な声が上がっています。
特に地域中核病院や大学病院では医師一人あたりの業務負担が大きく、長時間労働が常態化しているケースも少なくありません。
厚労省の調査によると、病院勤務医の約4割が過労死ライン(月80時間超)の残業を強いられている状況です。
本来であれば、医師が増えれば労働負担が軽減されるはずですが、現状では特定の地域・診療科に医師が集まらないために、人手不足の病院では一人ひとりの勤務医にしわ寄せがいっている状況です。
また、日本の人口当たり医師数はOECD平均の約2/3〜3/4程度しかなく、国際的に見ても決して医師が過剰な国とは言えません。
現場からも「絶対的に医師が足りない」という声が根強く、医師数の過剰よりも偏在や勤務環境の改善こそが喫緊の課題となっています。
(出典:厚生労働省)
医師が増えすぎた場合に考えられる変化
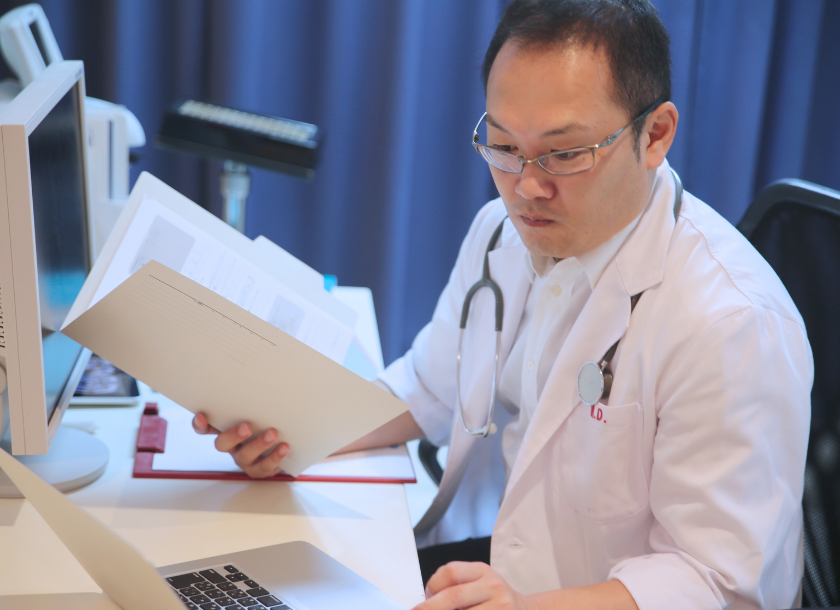
勤務医の待遇や収入への影響
仮に将来的に医師が供給過剰となった場合、医師の働き方や待遇面にも変化が及ぶ可能性があります。
まず考えられるのは、医師の「売り手市場」に変化が生じることです。
現在は医師不足の分野では病院側が高待遇で医師を確保しようとしますが、医師が余る状況では人気の高い都市部の病院求人に応募が殺到し、医師側の求人競争が激化することも予想されます。
また、「医師の生活確保が困難となりかねない」といった指摘があるように、医師過剰社会では従来より収入面の安定性が低下したり、人気病院・診療科への就職が狭き門になったりすることが懸念されます。
一方で、医師が十分行き渡れば一人当たりの負担が軽減し、長時間労働の是正につながる可能性もありますが、それには医師過剰を有効に活かす労務管理と制度整備が必要でしょう。
開業環境と地域医療への波及
医師が余る状況では、勤務先が限られるため、自らクリニックを開業する医師が増えることも考えられます。
その結果、特に都市部ではクリニック同士の競争が激化し、同じエリアに似た診療科の医院が乱立する恐れがあります。
患者の奪い合いによる経営競争が起これば、医療サービスの質向上や特色づくりが進む反面、過当競争で経営難に陥る医療機関も出てくるでしょう。
医師が余る場合でも、地方や特定の診療科では依然として不足が懸念されるため、医師偏在を示すこれらの状況に応じて、都市部での開業規制や地方での開業支援などの政策が強化される可能性があります。
医師過剰に伴うこれらの変化は、開業医だけでなく地域医療の提供体制全体に影響を与えるため、医療界全体でバランスを取る取り組みが求められるでしょう。
医学部受験生が進路選択で意識すべきこと

「余る・不足」ではなく「偏在」の理解
医学部を目指す受験生にとって、大切なのは「医師が将来余るか足りないか」という単純な二者択一ではなく、「医師の偏在」という視点で状況を捉えることです。
たとえ将来的に統計上は医師数が需要を上回る局面があったとしても、それは全国・全診療科の合算で見た話です。
実際には地域によって、あるいは診療科によって、医師が足りないところと余裕のあるところが併存します。
重要なのは、自分が将来どんな医師になり、どんな地域や科で働きたいかを考える際に、その分野で本当に医師が足りているのか足りていないのか、どこで自分の力が必要とされるのかを知ることです。
「医師は余っているから自分は苦労する」と思い込むのではなく、「どこに行けば自分の活躍の場があるか」を考えることが求められます。
専門性や地域性を踏まえたキャリア選択
将来のキャリアを考える際には、自分の興味や適性はもちろんですが、それに加えて専門分野や働く地域のニーズを意識してみましょう。
例えば、小児科や産科に情熱があるなら、それらは各地で慢性的に医師が不足している分野ですので、あなたの力が必要とされる現場が多く存在します。
一方、皮膚科や眼科など人気が集中しやすい診療科では都市部の競争が激しい可能性があります。
もちろん最終的には自分が情熱を持てる道を選ぶべきですが、将来どのような環境で働きたいかも含め、専門性と地域性のマッチングを考えることが大切です。
医師としてのキャリアは非常に幅広い選択肢がありますので、自身の目指す姿と社会のニーズをすり合わせながら進路を検討することが望ましいです。
制度や奨学金などの仕組みを知る
進路選択にあたっては、医学生を取り巻く制度や奨学金の仕組みについても理解を深めておきましょう。
特に近年は、地域の医師確保を目的とした「地域枠入試」や自治体の奨学金制度が充実しています。
また、多くの自治体では医学生に奨学金を貸与し、一定期間の地元勤務で返済免除とする制度を設けています。
これらの制度を利用する際は内容を十分理解しないと、「思っていた働き方と違った」という事態にもなりかねません。
地域枠や奨学金の条件や義務を事前によく確認し、自分の将来計画に照らして判断することが大切です。
本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾
医師の将来供給や偏在の問題を理解するには、まず医学部に合格し医師になるための第一歩を踏み出すことが欠かせません。
受験生にとっては厳しい学習を効率的に進める環境が必要であり、医学部専門予備校 京都医塾はまさにそのための体制を整えています。
ここではその3つの特徴をご紹介します。
苦手を徹底克服する完全1対1授業
医学部専門予備校 京都医塾では、徹底的な個別最適化を実現するために完全1対1形式の授業を行っています。
生徒一人ひとりの習熟度や志望校に合わせ、必要なら中学レベルにまでさかのぼって基礎を補強します。
担当するのは各科目の専門講師であり、他教科や志望校の進捗も共有されているため、点ではなく全体を見据えた授業を展開できます。
苦手分野や弱点を明確にして確実に改善し、短期間で大幅な実力アップを実感できるのが特徴です。
理解不足を放置せず、一つひとつを解消しながら着実に前進できる環境を提供しています。
仲間と高め合う少人数集団授業
完全個別授業に加え、医学部専門予備校 京都医塾では学力別に分けられた少人数集団授業も用意しています。
同じレベルの仲間と切磋琢磨できる場で、学習進度を確保しながらモチベーションも高められます。
他の生徒の頑張りを目にすることで「自分も負けていられない」という気持ちが芽生え、学習意欲がさらに強まります。
教科ごとのレベル分けによって無理なく学べ、個別と集団を組み合わせることで学習効果を最大化できます。
刺激と安心感が同時に得られる仕組みがあり、受験まで継続して力を伸ばせるのが特徴です。
無料参加できる1泊2日医学部合格診断ツアー
入塾前に自分の現状と課題を把握できるのが、医学部専門予備校 京都医塾の1泊2日医学部合格診断ツアーです。
学力テストや体験授業、個別カウンセリングを通じて、医学部合格までに必要な点を明確にできます。
結果は詳細なレポートにまとめられ、プロ講師から具体的な学習計画の提案も受けられます。
授業体験や校舎・学寮の見学もでき、環境を知る絶好の機会になります。
交通費や宿泊費は無料なので、遠方からでも安心して参加できます。
まとめ

この記事では、医師が将来「増えすぎる」と言われる背景と、実際の現場で続く偏在や不足の問題を整理しました。
全国の医師数は増加しているものの、地域や診療科での不均衡が大きく、単純に「余る」とは言えないことが分かります。
国際的にも日本の医師数は決して多くはなく、偏在や勤務環境改善こそ課題です。
こうした現実を踏まえると、受験生にとって重要なのは、どの地域や診療科で自分の力を発揮するかを考えることです。
とはいえ、「医師が余るのでは」といった声に不安を感じる方も少なくないでしょう。
そうした不安を抱えつつも医学部合格を目指すなら、専門的な環境での学習が必要です。
医学部専門予備校 京都医塾なら、個別授業と集団授業の組み合わせで効率的に力を伸ばせるほか、経験豊富な講師が一人ひとりに最適な戦略を提案します。
まずは1泊2日医学部合格診断ツアーに参加し、自分の現状を客観的に把握しながら最適な学習方針を知ることをおすすめします。
完全無料で、交通費や宿泊費も負担されるため安心して参加できます。
医学部合格に向けて一歩踏み出す機会として、ぜひお気軽にご利用ください。


